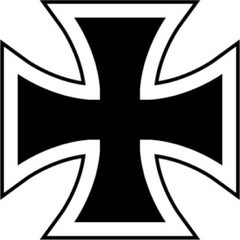しかしこれほどまでに主人公に優しくない少年漫画もそうはないじゃなかなぁ
あと一歩まで滅ぼされた家と幕府の再興に迫っていた侍王子でしたが、ラスボスのわけの分からない人間離れした力の前に敗北。育ての親をも失い、第1部の行動原理は全て比定されてしまった。
北条時行くんを主人公にした物語となると、この史実展開がネックになると予想されました。
もちろんこの根本展開を変えることはできない以上、そこをどうキチンと物語化していくか、まさに松井センセイの手腕が光る所でした。
そして今回でサヨナラとなった諏訪頼重さん。彼の意中がどこにあったか、その答えは史実での諏訪頼重さんが最期に取った行動から出されることになりました。それでは本編感想参ります。
〇頼重さんの手向け
涙の抱擁をもって遂に別れることになった北条時行くんと逃若党、そしてそれを見送る諏訪頼重さん。最期まで付き従っていた諏訪神党の祢津頼直や保科弥三郎たちも主君に最後の礼をもって立ち去りました。残っていたのは長らく共に付き添っていた解説上手の諏訪盛高さん。彼らは最後の準備をしていました。落命していた将兵の遺体を集め、「ある準備」をしていたのです。その中には時行くんと同じ年の子供もいました。
頼重さん「皆の死を無駄死ににはさせませぬ。時行様の逃げ上手は今宵より伝説となる」
そして遂に迎えた最期の時。諏訪盛高さんもまた長らく一緒に生きていた間柄だけに非常に辛いものとなります。その最期となる解説での頼重さんの最期を評すると…
諏訪盛高「『忠義に生き、忠義に死んだ神がいる』それ以外にございません」
解説「諏訪頼重が乱を起こした最大の理由は何だろうか。彼の死に様を見れば、それは凄絶な『忠義』としか言いようがない」
後世に生きる我々が過去に実在した人物の内心を図ることは残念ながら不可能です。もちろん当人の肉声なりは史料に残っていますが、それが必ずしもその人間の本心であるかは保証の限りではない。例えば「諏訪頼重が北条家の忘れ形見である少年を擁立したのは単なる旗印に過ぎない。最終的には傀儡にして自らが権力を握るつもりであったに違いない」という他者の推論もまた否定できる根拠は無いのです。我々が歴史上の人物の内心を測れるのは
その人間が如何に行動したか
が全てです。頼重さんという人の最期を見た場合、野心家であったのならそこにはどう考えても時行くんを単なる「傀儡」と見て行動したにしては、余りにも自己犠牲が過ぎるものがあります。自らと郎党一同が犠牲になることで「目くらまし」となり、更に時行くんを逃がす「囮」となると言う行動。そこに「忠義」が介在していないと誰が言えるでしょうか。最期まで自らが庇護した侍王子を守るために行動した。そう表現するしか彼の本心を測る術はないのです。
〇勝者となる南北朝のラスボスの棘
そして到着した足利軍の将兵たちが見たのは余りにも凄惨な光景。戦場で多くの死体を見てきた判官殿こと佐々木道誉や高師泰でさえ、思わずドン引きするほどのものでした。
おお…絶対にドン引きすること確定の凄惨な絵図…もちろん直接的には描けないとはいえ、想像するだに目を背けたくなるような光景になりそうです。これもまた盛高さんが用意していたものでした。その中には時行くんの恰好をした少年の「それ」もありました。史実通り「我ら一同先祖に合わせる顔が無し」という遺言と共に自らの顔を剝いで自害する状況です。当然ながら足利方の人間としては断定できぬ状態に乱の首魁とされる時行くんについても「この中に死んだのだろう」という推測をもって終了することになりました。
佐々木道誉「勝ったのにモヤモヤが消えぬ」
とはいえ、足利の将帥たちにとっては折角の勝利によって乱を平定したにもかかわらず、肝心の首魁の少年が死んだかどうかはっきりしないこの状況にはもやッとするものがあったようです。他ならぬ南北朝のラスボス足利尊氏もまた例外ではありませんでした。表面上は余裕たっぷりに
南北朝のラスボス「最期まで鋭い策士だったな諏訪明神は!『諏訪頼重の乱』の主として未来まで名を残すだろう!」
と時行くんの存在を無意識に否定したい心境で頼重さんへの賛辞を惜しまない態度。しかし、やはり彼自身にとっては時行くんの存在は…
一人の負傷した足利の兵士を見舞う尊氏。腹を刺されながら内臓への損傷を奇跡的に回避した幸運さを称賛した尊氏は気前よく恩賞を約束します。南北朝のラスボス足利尊氏が非常に気前のよい大将であったのはこれもまた彼の行動からも分かる通り、確定的な事実。
まあ余りにも気前が良すぎて肝心の足利家本家の力が弱くなり過ぎたのですがね
それでもその気前の良さがまた彼の人望を高める力となり、天下人の座を不動のものにしたのですから間違いなく「美点」と言えるでしょう。この尊氏には高兄弟やズッ友に判官どのもホッコリ。もちろん雑兵の武士も感涙極まり…
雑兵「お、俺如き雑兵になんと慈悲深い…『中先代の乱』の征伐に加わって本当に良かった」( ;∀;)
〇その名は「中先代」
その「名」でそれまで優しい目をしていた南北朝のラスボスの目つきが固まります。「中先代」それは足利の将兵の間で自然発生的に発生した北条時行くんに対する通り名。「時行」という実名より、その存在の大きさ故に彼を評した足形の将兵たちが付けたものです。
敵手であった足利からも賞賛の念を込めて付けられたこの渾名。そこには武運拙く敗れ、落命した(という設定)侍王子に対する追悼のつもりであったのでしょう。
時行くんの存在を矮小化し、否定したい南北朝のラスボスにとっては重大な地雷です。
つい先ほどまで優しく見舞っていた雑兵の命を無造作に奪い取った南北朝のラスボス。それだけ彼にとっては時行くんの存在は重大な棘となっていました。
無表情で兵士の命を奪ってその場を立ち去る尊氏。
解説「乱の直後から時行は「中先代」と呼ばれていた」
僅か10歳に満たない少年武将に二つ名がつくなど通常はありえないことであり、しかもそのことによって歴史に名を残すことになりました。それだけ彼の存在は単なる「傀儡」とは認識されず、人々の心に刻まれる存在であった…
おお、こういう形で時行くんが主人公となった漫画として
その存在意義を示すか!
大河『太平記』でもチラッとしか触れられていなかった時行くん。しかし、今こうして彼が歴史に名が残るに至った物語としては十分すぎるほど描いてくれました。
今や零体となった頼重さんは去り行く時行くんを見守り、メッセージを残していきます。彼の存在は第1話で言われていた通り、余りにもマイナーなもの。歴史に名を残すのはまさにこの「中先代の乱」によるほんの一瞬の時です。それは一発屋である事実も否定できないとはいえ、それでもその中でこの少年が駆け抜けた戦の物語でもあるのです。
解説「こうして北条氏最後の渾身の大戦はわずか20日の鎌倉占領で幕を閉じた」
中先代の乱は残っていた北条一族や家臣団の多くが落命し、鎌倉幕府滅亡後も残っていた北条氏が完全に勢力を喪失することになりました。最早北条による鎌倉幕府再興は不可能となってしまい、第1部での主人公の努力が全ての水の泡。余りにも時行くんにとっては過酷な展開です。かくして今や自らと僅かな郎党たちだけとなった逃若党、しかしそれは裏を返せば、彼がもうしがらみにとらわれず、自分の意志で動く契機となります。来る第2部の北条時行くんの行動原理、それは
身一つで巨大な存在となった南北朝のラスボスに単身挑む侍王子の物語はこれからです。
最後に暖かく「息子」の活躍を見守るかのように昇天していく頼重さんの笑顔と共に第1部は完了となりました。第1部での物語は決して無駄ではない。時行くんが頼重さんを通して、多くの事を学び、自分の意思でもって戦いの場に身を投じる武将へと成長する過程でした。そして「一人の存在」となった時行くんの更なる戦いは来るべき第2部に続きます。