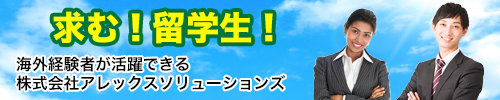今は在宅勤務が主の為、いろんなオンラインセミナーに参加しています。
オンラインセミナーのいいところは、もしも内容がこちらの想像したものと違かった場合に、セミナーを聞きながら、横で別の作業ができるところです。
時間を有効に使いつつ、面白い内容だけいいとこ取りできるため、手あたり次第うけまくっています。
いろんなセミナーを受ける中で、「しっかり受けるセミナー」と「横で仕事しながら聴くセミナー」の違いが見えてきました。それは、「説明資料の多さ」と「1ページの文字量の多さ」。
文字量が多いと、ちゃんと資料を見る気にならないし、プレゼンターも資料自体の説明を省くので、話と資料の関係性が分からなくなり、話を聞く気にさせなくなります。これなら、資料無しで話した方がよっぽど頭に入ります。
逆に面白い話は資料がシンプルで、文字が少ない為書かれている文字が覚えられる分、頭に残ります。あたまに残ったものを説明されるので、聞いていてもわかりやすい。
プレゼンターにしてみると、伝えたいことがたくさんあるので、それを資料に全て入れたくなる気持ちもわかりますが、たくさん書けば伝わるというものでもないのです。
私も週2回、会社説明会で当社の説明をしますが、その資料がわかりにくくないか、横で別の作業をしながら聴かれていないか、セミナーに参加することで反面教師になり、それが実はセミナーの一番の収穫になっているかもしれないなと思っています。
2020年4月の「週刊新潮」の取材を動画にまとめていただきました。
動画はこちら↓