今年初の谷川岳
今日は名前通りに(?)山へ行って来ました。
谷川岳です。私のブログを読んでくださっている方が首都圏以外にも多いようなので、くわしく説明すると群馬県と新潟県の境目の上越の山で標高は1996mでわずかに2000に届かない山です。ただ、高さの割に上越という立地条件で日本有数の豪雪地帯で、谷川岳の中腹にある天神平スキー場は関東にありながら春スキーを5月の連休のころまで出来るという場所です。
私が住んでいる埼玉はJR上越線一本で谷川岳のふもとの水上駅(さらに山の直下には土合駅というのもありますが)まで2時間弱でいけるので、私は年に数回、ここに登りに行きます。今回は雪解け直後(まだ途中にも雪があるし山頂直下は雪田でしたが)ならではの花を目当てに登りました。
まずはイワカガミ。光沢のあるやや濃い緑の葉の上に薄いピンクの可憐な花を咲かせます。初めて見たときに思わずウットリしたことがあります(あまりその姿を想像しないでください。。。。)。
ついで、シラネアオイ。薄い紺色のやや大ぶりの花が咲きます。関東近隣の山々にはあるのですが、日光白根山のものから名前がついています(ただし日光白根のは鹿にたべられて絶滅寸前だそうです。)。
それから、この時期に見られるかどうか微妙なのがカタクリ。昔は里山に普通に自生していたそうですが、いまでは里山のは保護したり一生懸命植えて増やしているものです。今の片栗粉は実体はじゃがいも粉のようですが、かつてはこの花の根からつくっていたのでその名が付いているようです。葉っぱや花の感じでたぶんシクラメンの仲間だと思います。
あと、この時期の谷川岳を代表するのがタムシバ。といっても一般的な名ではなく普通はコブシと行った方が通じると思います。山道を歩いていて目線よりやや上に白い大きな花が咲いているのを見つけると、何とも言えない気分になります。
今日はこの他にもショウジョウバカマ、スミレの仲間、シャクナゲ、ツツジといったおなじみの花にも多数お目にかかれました。
谷川岳は場所柄、日本海側と太平洋側の気候のぶつかるところで、一日中晴天に恵まれるのは非常にまれなのですが、今日は朝から快晴で、空気も乾いていて、登っていくうちにいささか脱水状態になるぐらいでした。山頂からは南方向には水上の町が見下ろせ、西には鋭く南側が切れ落ちている稜線が続き、北には蓬峠と言うところを通って新潟に抜ける稜線の道が続いており、東側には湯桧曽川をはさんで白毛門(しらがもん)という山があり、今日は全て見えました。
写真はまとめてフォトのコーナーにアップしておきますので、よろしければご覧下さい。
http://photo.ameba.jp/user/atsushi0615/
今日は眠いので、音楽はお休みです(後ろでバッハの無伴奏Vnパルティータが鳴っていますが。)。
魔弾の射手
私自身は、熱心なオペラ愛好家ではないが、人生最初にオペラですごいと思ったのが「魔弾の射手」。
小学校5,6年の頃だったと思うが、テレビで何となく見ていて気がついたら引き込まれていた。誰の演奏であったかは定かではないが、たぶんクライバーのドレスデンかバイエルンとの公演をNHKの教育テレビで流していたのを見たのだと思う。あのころは筋などは全く知らず、ただ音楽と舞台の流れを、字幕を頼りに見ていたのだと思う。その時に見たことを今でも覚えているのがマックスが山の中で魔弾を手に入れるシーンと狩人の合唱から終わりまでのところ。昔はNHKの教育でよく来日演奏家のコンサートの収録を土曜の午後などに流していた気がするのですが。
それから、音楽だけは断片的に耳にしていたが、高校時代に序曲の旋律がキリスト教の賛美歌で使われているのを聴き、また懐かしく思い、初めてLPのハイライト盤(子クライバー、ドレスデン)を入手。
その後、大学時代にLPからCDに世の主流がうつり、この頃にCDでカイルベルトの全曲盤を入手し、大学時代はこれをスコアを見ながらよく聴いていた。その後、クライバーの全曲盤やヨッフム、クーベリック、マタチッチの演奏なども入手し、度々聴いてきた。
ウェーバーの作品は、この曲の他は歌劇の「オベロン」、cl協奏曲やclの室内楽曲とピアノ曲をいくつかぐらいしか知らないが、19世紀末から20世紀にかけてのブルックナーやマーラー、ツェムリンスキー、フランツ・シュミットなどの巨大な管弦楽曲を聴いていると、その響きの中に魔弾の射手でなじんだホルン重奏の響き(コラール)をふと感じ取ってしまうのは、子供の頃のすり込みだろうか。
というわけで、今日は魔弾を斜め聴き?しています。ぐいぐい進めていくクライバーの華麗な演奏やクーベリックの流麗な演奏もいいけど、私にはカイルベルトやヨッフムの素朴な演奏の方がしっくり来ます。
マーラーの「復活」聴き比べ
マーラーの音楽に関するブログを書かれているabbadoiさんの記事で、マーラーの「復活」の2楽章に関する思い入れのほどを読ませていただき、先ほどから「復活」の聴き比べ。
指揮者によってここの楽章の処理はだいぶ違ったなという記憶はあったのですが、丁寧に聴いてみると色々と発見があって面白い。
2楽章は8分の3拍子で、頭に16分音符がまずあり、その後16分休符がはいってからメロディラインがはじまります。ここで、この頭の音をまず丁寧に鳴らす人と、聞こえるかどうかきわどいぐらいに軽く鳴らして、休符も軽く、すぐにメロディラインを演奏する人(ショルティ)もいれば最初の音を少し長めに鳴らし、その後の休符を正確に(短く)とったあとメロディにはいる人(多い)、休符も心持ち長めにとってタメを作った後思い入れたっぷりにメロディを鳴らす人(バーンスタイン、ラトル)など様々。また、バーンスタインはNYPとの最初の録音と新盤は傾向が似ていて、あいだにあるLSOとの演奏ではあっさり流していて違うのも面白い。
最初の主旋律も1音ずつアクセントをつけていくバーンスタインのタイプとあまりアクセントは強調していない人もいるし、テンポも実に様々。楽章内でテンポの起伏が大きい指揮者もいれば割と一貫している人もいる。個人的には、ここは全体にゆったりと、かといってあまり引きずらずにアクセントもやや利かせて演奏してくれるとありがたい。
以上の点で、今晩気に入ってそのまま聴いているのはラトルがBPOと2006年9月16日にやったコンサートのCDR(Harvest Classics HC06056)。
最近のライブのCDRは昔のいわゆる海賊盤の音質とくらべると格段によくなっていて、正規盤との差は何?と感じてしまうものも多いですね。中には「金返せ!」と言いたくなるものもありますが。
Pražská defenestrace
韓国の前大統領が訴追を受けて岩山からダイブして自殺したようす。
関係ないけど、チェコ史ではPražská defenestraceという、プラハ窓外投擲事件という訳語をあてはめる言葉があります。チェコ史には、プラハ市庁舎で窓から人が放り投げられ(突き落とされ)て歴史上の大きな事件がはじまるという、少し恐ろしい伝統があり、15世紀のフス戦争、17世紀の三十年戦争、あるいは20世紀の共産政権の誕生(これには色々な説がある)がはじまったとされています。
というわけで、今日は久々に「わが祖国」を聴いています。
ターリヒの1954年録音。モノラルながらしっかりと録られていて聴くのには問題ありません。音質云々よりも音楽の恰幅の良さ、指揮者もオケも共感をもって演奏しているがゆえの安定感が感じられ、これは別格の名演だと思います。
他にも最近ではマタチッチの演奏やクーベリックの演奏などですばらしいものがありますが、私が好きなのは
これ、スメターチェク、チェコフィルの演奏。派手なところはありませんが、手堅くしっかりと曲ごとの性格を描き分けていて、全曲を聴き終えると、長編の歴史小説を読んだ気分になります。
さきほどのチェコ史のフス戦争にちなんだ曲が最後の二曲で、ここで使われている主題はドヴォルジャークの交響詩の中でも使われていたり、最近では吹奏楽曲でカレル・フサという作曲家の作品にも使われていましたね。
番外編で結構面白いのが、ピアノデュオ版。いくつかありますがその中で気にいっているのが日本のLIVE NOTESレーベルのThe Mostly Piano DuoのCD。演奏もまずまずですが、ブックレットの解説がこの曲に関連するチェコの場所の写真が豊富に入っていて面白いです。
4手ピアノ
最近、家で仕事をしながら聴いていることが多いのがピアノやチェンバロなどの鍵盤楽器の曲。オケの曲も好きだが、どうしても集中して聴きたくなる。
ここしばらくのあいだで聴いた中で面白かったのがこれらのCD

これはバッハの管弦楽組曲を4手ピアノ用にマックス・レーガーがアレンジしたもの。楽譜を見たことはないが、原曲の音をほぼ全て再現し、さらにロマンはならではの厚いハーモニーにしてある。他にオルガン曲の編曲も数曲入っていてお得。
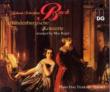
こちらもバッハの曲でブランデンブルグ協奏曲を上とおなじマックス・レーガーが4手ピアノ用にしたもの。
これは、単純に5番の編曲に興味があって購入したが、チェンバロパートを一人が弾き、他のパートをもう一人が弾いている様子。他の曲の編曲では4番、6番あたりも面白い。
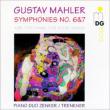
最後に、これはマーラーの交響曲第6番と第7番をそれぞれ、ツェムリンスキーとカゼッラが4手ピアノ用にしたもの。これはどちらももともと多い音を4手ピアノとはいえピアノの上に置き換えるのでどうなのかなと思ったが、結論から言えば別の曲と思って聴けば楽しめる。打楽器パートはどうしてもピアノにするのは厳しいが、他のパートはがんばって移した感じ。
7番を編曲したカゼッラは管弦楽曲でパガニーニの主題を使った変奏曲(たしかパガニーニアナ?とかいったような)を聴いたことがあるぐらいで、他の作品は知らない人です。
4月末の尾瀬
先日、尾瀬の山開きがありましたが、今年の4月末に尾瀬に行った時の写真をアップしました。
http://photo.ameba.jp/user/atsushi0615/07335bh345oo46e1t617hm/
4月27日に入山した時は雪がふっていて、28日から30日は快晴。
27日の夕焼けは雲があり、変化に富んでいたが寒かった。
28日は晴れていたが風が強く、尾瀬沼の上を歩いていても前日の雪がブリザードみたいに吹き付けて痛かった。午後は大江山に登る。夕焼けは今ひとつ。
29日は午前中は尾瀬沼北岸の樹林帯の中を散歩、午後から檜高山にのぼり小淵沢田代へ。29日の夕焼けがきれいだった。
30日は朝から写真撮影。寒く、靄も出ない。日の出前、ひうちが少し赤く焼けた。昼頃に大清水に下山してきた時は初夏の陽気でした。
今年は例年と比べると雪が少な目でした。
次回の尾瀬入山予定は未定。
裁判員制度
5月21日より裁判員制度がスタート、した模様。
仕事の関係で、新聞の記事やネット上の記事を検索閲覧したが、今のところ裁判員として呼び出された人が拒否していることが最大の話題になっている感じ。
裁判員制度がスタートしたことで、裁判がどう変わったのかはまだ未知の領域なので、しばらく見ていきたいと考えています。
てなことを考えながら今聴いているのは
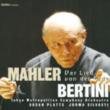
ベルティーニ指揮の大地の歌。
この人のEMIの全集は全曲が愛聴盤だが、この都響とのツィクルスも完成させて欲しかった。
この指揮者、年をとってもテンポが遅くなったり弛緩することがないのが凄い。
都響相手に、前のケルン放送響のときよりもむしろ掘り下げて細部を丁寧に表現しているのがいい。
都響も若杉弘の指揮で全集を出した頃よりは精度があがっている感じ。欲をいえばもう少し弦の厚みが欲しい気もするが、ライブ録音のハンディか。
最近、大地の歌にはまり、以前から持っていたCDを棚の中から掘り出してきて色々聴き比べています。
徒然なるがままに筆をとりつつ
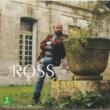
自分の趣味の音楽や登山、その他仕事のことなどについて思いつくがままに書いていきます。
仕事の話ですが、今春の中学入試の社会科の問題で世界の国々の「平和度」ランキングなるものを発見。
1位がアイスランド、2位がデンマーク、3位がノルウェーで日本は5位、アメリカは96位というもので、この順位から日本とアメリカの違いが生じる理由を述べよというもの。正直、小6のお嬢ちゃん(女子中です)にとってはしんどいのではというものだが、いかがでしょうか。
ちなみに、最下位はイラクでビリ2はソマリアなので、ここまで情報があると分かりやすくなる気もするが、学校が与えている情報だけだとかなり厳しそう。
学校発表の正解がないので何とも言えないが、たぶんアメリカの銃の所有率の高さや、米軍の海外派兵での死傷者数のことなどをふまえて書けば正解になるとは思います。
今、PCにむかいながら聴いているのはだいぶ前に亡くなったスコット・ロスによるゴールドベルク変奏曲。いいですよ。バッハの鍵盤曲で歌うというのはこういうことなのかなと考えさせられる演奏です。、

