80年代前半の時期のアメリカを
最も象徴している曲というと、
実はこれである気がしないでもない。
ケニー・ロギンスとおっしゃる。
エッセンシャル・ケニー・ロギンス/ロギンス&メッシーナ
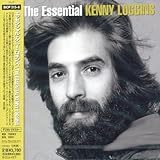
¥3,888
Amazon.co.jp
しかし、いつ聴いても
実に個性的な声である。
音域は相当高いのに
ヘヴィメタのハイ・トーンとは
全然毛色が違っているし、
かといって
中性的という訳でも決してない。
むしろこの人しか出せない
独特のツヤみたいなものがある。
そしてその声質が
一番ハマったのが
このトラックだといってしまって
全然いいのではないかとも思う。
この軽快さ、たぶんほかの人では
そう簡単には出せないだろう。
本当、かけるたびにいつも
ノリノリな気分に
させてくれるトラックである。
もちろん僕自身が
ハイ・ティーンだった時代に
同曲と出会っているという背景も
当然あるにはあるのだが。
実をいうと一時期はよく
カラオケでも歌ってました。
さて、知っている人には
いわずもがなのことだろうし、
あるいはもうタイトルからして
一目瞭然かもしれないけれど、
この曲は、同名の映画の
サウンド・トラックのために、
書き下ろされた一曲である。
今更あえていうまでもなく、
映画というメディアが
ポップ・ミュージックのシーンへと
与えてきた影響というのは
計り知れないものがある。
僕らの世代だと、
まずは70年代の末頃に、
ディスコ・ミュージックへの転身を
大胆に図ったビージーズ(♯129)による
『サタディ・ナイト・フィーヴァー』が
それこそあっという間に巷を席巻し、
O.N.ジョン(♯130)の
『グリース』やら『ザナドゥ』やらが
それに続いてラジオを賑わし、
そして80年代に入ったところで
リチャード・ギアの出世作となった
『愛と青春の旅立ち』が公開され、
主題歌Up There We Belongが
それこそ耳にタコができそうなほど
あちこちで流れる
大ヒットとなっていた。
同曲は本邦でも松崎しげるさんが
女性シンガーとのデュエットで
カヴァー・ヴァージョンを
録音してしまうくらいの勢いだった。
そしてさらに、ダンス・シーンを
強烈にフィーチャーした、
映画『フラッシュダンス』からは、
アイリーン・キャラによる
同名のタイトル曲を筆頭に、
同じ一枚のサントラから
異なるアーティストによる
複数のトップ10ヒットが
生まれたりといったような
現象さえ起きるようにもなった。
そういった潮流の中で
この『フットルース』は
我こそが真打ちとでも
いった感じで
それこそ意気揚々と
登場してきたような感触だった。
同作が画期的だったのは、
サントラ所収のほぼ全曲が、
この映画のために新たに
書き下ろされたのみならず、
映画本編の脚本家が自ら
ソングライターとして、
曲そのものにも参加するという
一応はそれまでには
試みられていなかった手法が
採用されていた点だったはずである。
厳密にはたぶんフォリナーの
The Girl Like Youだけは
既存曲だったと思うのだが、
手元のCDではこの
フォリナーのトラックのほかに、
ジョン・クーガー・メレンキャップと
クワイエット・ライオットの作品が、
ボーナス・トラックとしてまとめられ
シャラマーの曲の12インチと一緒に
最後の方の収録となっている。
いや、確か最初のLPの時にも
すでにフォリナーのこの曲は
一緒に収録されていたように
記憶していたのだけれど、
ちゃんとした確認が取れなかった。
もしどなたか正確なところを
覚えていらっしゃる向きがあったら
ご教示いただけると嬉しい。
さて、いずれにせよこの
書き下ろしで録音された
全9曲のすべてが
シングルとしてカットされ、
しかもその中からこの
ロギンスのタイトル曲のみならず、
デニース・ウィリアムスという
黒人女性シンガーの歌唱による
Let’s Hear it for the Boyの二曲が、
相次いでチャートのトップにまで
昇り詰めるような現象が
瞬く間に起きてしまったのである。
このサントラ、だからそういう
『サタディ・ナイト・フィーヴァー』にも
十分比肩しうるレベルの
滅多に類を見ない一枚に
あっという間になってしまったのである。
映画自体もまあそこそこの評判には
なっていたとも思うのだけれど、
どちらかというとサントラの方が
ヒットの原動力に
なっていたように記憶している。
ちなみに本邦でも、同作からは
オーストラリアのグループによる
Neverなる楽曲と、それから
ボニー・タイラーの
I’m Holding out for a Heroの二曲が
それぞれカヴァーされて
結構なヒットになっていたはずだし、
またAlmost Paradiseも
後年ドラマ主題歌に
起用されていたりもしたので、
そういったきっかけで
手に取った方も
少なくはなかったのではないかと思う。
それからこれは、
例によっての横道ではあるのだが、
ある意味ではこの
『フットルース』のすぐ後を
まさに追いかけるようにして、
あの『パープル・レイン』を
登場させることができた点にこそ、
プリンス(♯138)の
アーティストとしての天才を
認めるべきなのかもしれない。
時節を得るというのは
たぶんああいうことなのだろう。
さて、80年代の開幕とともに
ラジオからMTVへと舵を切った
ポップ・ミュージックの
プロモーションのアンテナが、
今度は映画というチャンネルにも
強力に触手を伸ばし始めたのが、
この時期に起きていた
出来事だったのかもしれないとも
今になればそんなふうにも感じる。
どの記事の時に名前を出したか
すっかり忘れてしまっているが、
一連のジョン・ヒューズ作品の
サントラ・アルバムなんかは
完璧にこのムーヴメントを
追いかける形で作成されていた。
それでもそういった中から、
シンプル・マインズ(♯14)や
あるいはOMD(♯16)など、
実力的には高く評価されながらも、
派手なチャート・アクションに
恵まれることのなかったバンド群が、
一躍脚光を浴びたりする事態が
起きてくる訳だから、
ある意味では幸福な時代だったと
いってしまっていいのかもしれない。
まあ一方ではジョン・パーの
St. Elmo’s Fireや、
あるいはロス・ロボスの
La Bambaみたいな
それこそ巨大な
打ち上げ花火の一発みたいな
ある種時代の徒花的なヒットも
中には少なからずあった訳だし、
サイケデリック・ファーズなんてのも、
プッシュしていた割りには、
あまり面白くない音だったように
記憶してもいたりするけれど。
そして、この映画産業と
ミュージック・シーンとの
強力な連携は、
たぶん92年のケビン・コスナーと
ホイットニー・ヒューストンとによる
映画Bodyguardとその主題歌
I Always Love Youの登場で
嚆矢を迎えることに
なったのだろうとは思うのだが、
だけどもうそろそろ、
ロギンス本人の話に
行かねばならない字数である。
いや、ここまで来たら
タイタニックにも
ちゃんと触れておくべきかなと
思わないでもなかったし、
それから映画絡みでなければ
スティングとロッド・ステュワート、
それに次回予定の
ブライアン・アダムスの
ビッグ・ネーム三人の共演による
レコーディングなんて事態は、
九分九厘実現しなかっただろうから
個人的には決してこういう動きに
否定的なつもりもないのだけれど。
いや、やっぱりキリがないから
とにかくそろそろそそくさと
今回の本題、
ロギンスの話に行くことにする。
さて、この方のデビューは
実に72年にまで遡るのだそう。
さらにいえば、この数年前、
十代のうちからすでにもう彼は、
大手レコード会社と
ソングライターとしての契約を
獲得しもしていた模様である。
この時期に書かれたものに、
House at Pooh Cornerなる
楽曲があって、
こちらもまた一目瞭然、
あの『くまのプーさん』を
モチーフにした曲なのだけれど、
米本国ではこの曲、
子供たちが喜んで聴く、
ある種のスタンダードのように
なっているみたいな感じなので、
いや多才というか、
最初から器用な人だったのだなと、
ちょっと印象を新にしもした。
たぶん「みんなのうた」みたいな
支持のされ方なのでは
なかろうかとも思うのだが、
まあこの印象は所詮
憶測の域を出るものではない。
さて、若きロギンスは
ほどなくシンガーとしての契約も
獲得することに成功し、
直後デビュー・アルバムに
プロデューサーとして
関わることになった、
こちらは
バッファロー・スプリングフィールドや
ポコのメンバーだった、
ジム・メッシーナなる人物と意気投合し、
ロギンズ&メッシーナとして
まずは世に出ることになる。
この時代にも前述の
Pooh Cornerを含めた
複数の佳曲があるようなのだが、
まあ70年代の
しかも前半の出来事なので、
正直あまり詳しくはない。
そして77年にソロに転身してからは、
フリートウッド・マック(♯44)の
スティーヴィー・ニックスや、
ドゥービー・ブラザーズの
マイケル・マクドナルド、
あるいはそれこそ
前回のジャーニー(♯154)の
スティーヴ・ベリーとの
デュエットなどで、
スマッシュ・ヒットを出してもいる。
そしてついに84年、
今回のFootlooseが
ロギンス&メッシーナ時代を含めても
彼にとってキャリア初の
トップ・ワン・ヒットを
もたらすことになったのである。
さらに86年には
あのトム・クルーズの
『トップ・ガン』に起用された
Danger Zoneが
これまた空前の大ヒットとなって、
彼の名声を
不動のものにしたといっていい。
ちなみにこちらの
サントラ・アルバムには
やはりなかなかビッグ・ヒットに
恵まれていなかった
ベルリンなんてバンドも
一緒に起用されていて、
『愛は吐息のように』の
邦題で有名になる
Take My Breath Awayなる
代表曲をもたらしてもいた。
そんなこんなで
この80年代の時期の彼は
サウンド・トラック・キングなんて
賞賛とも揶揄ともつかない
キャッチフレーズを
冠されたりもしてしまうのだけれど、
思うにこの方だから
何らかの映像的な
とっかかりさえあれば、
それを上手く形にできる
そういうソングライティングの
センスの持ち主なのだろう。
逆に振り幅が
広過ぎるとでもいうのか、
なんだろうなあ、
ある種の尖り具合みたいなものに、
ちょっと正体のよくわからない
食い足りなさが
残ってしまうという印象は
正直いって当時から
少なからずないでもなかった。
さらにいうと、
音楽とは別のところでこの人、
きっとすごくいい人なんだろうなと、
そんなふうに思うことがしばしばある。
いや、そんなによくは
知らないんだけれどね。
ちょっとロッカーとしては
大人しめな空気を
まとっていなくもないのである。
でも逆にだからこそ、
このFootlooseが
最高にハマったのだといったら
はたしていい過ぎになるだろうか。
映画の方の主人公は
田舎に転校してきた
高校生なのだけれど、
この歌の話者は、
おそらくは社会人である。
冒頭だけちらりと和訳すると
大体こんな感じになる。
タイム・カードをパンチし続け、
くたくたになるまで働いて
何のための8時間なのかも
正直よくわからない
誰か俺が手に入れたものを
教えてはくれまいか――
だからこういういわば
ワーキング・クラスの焦燥が、
重くなり過ぎずに描かれる。
むしろ笑い飛ばしたいくらい。
それこそ足下を軽くしてしまえば、
もっとなんとかなるんじゃないか。
そんな気分にさせてもらえるのである。
やっぱりこの手触り、
この曲からしか得られない。
さて、その後のロギンスは
90年代に発表した
House at Pooh Cornerへの
ある種セルフ・トリビューとでも
いった感じに形容できそうな、
RETURN TO POOH CORNERという
いわばファミリー向けの作品が
存外のロング・セラーとなって
健在ぶりをアピールしていた模様である。
そして今世紀に入った03年には
ロギンス&メッシーナの再結成も果たし、
また13年には
カントリー・ミュージックのジャンルの
ベテラン二人と一緒に、
ブルー・スカイ・ライダーズなる
トリオを組んで、
アルバムを発表してもいるらしい。
いや、思いの外休むことなく
活動を続けていらっしゃるようで、
今回リサーチをかけてみて、
ちょっとだけ
ほっとしたような気分にもなった。
さて、では締めの小ネタに行く。
今回はけっこう
それっぽいの見つけてきました。
このケニー・ロギンス、
今年御年68歳にして
実はまたも、映画の主題歌を
手がけられていたりする。
いや、相変わらずだなあと
最初は思わないでもなかったのだが。
――ところが。
この作品がなんともまた
ものすごい代物なのである。
タイトルを
THE ART OF THE DEALという
一本なのだけれど、
たぶん交渉の妙とでも
いったニュアンスに
訳すのだろうと思うのだが、
これが何を隠そう、あの
次期合衆国大統領である
ドナルド・トランプ氏が
80年代に発表した同名の自伝を、
原作とした作品なのだそうで。
しかも基本はパロディーらしい。
まさに大統領選だったこの年に
こういうものをやれるところが
今も昔も相変わらず
アメリカのアメリカたる
所以だよなあとも
思わないでもなかったのだが、
よく調べてみてさらに仰天。
同作の劇中にはもちろん
トランプ本人が登場するというか、
当然彼が主役な訳なのだけれど、
ここになんとあの、
ジョニー・デップが
キャスティングされているのである。
しかも好演が評価されてもいるそうで。
――え、なんで?
ジョニー・デップの新作なのに、
これ日本公開なかったの? と
まずはそう思ったのですけれど、
これがどうやら
FUNNY OR DIEなる
パロディ専門の
たぶんケーブルのチャンネルの
制作による一本なのだそうで、
だからまあたぶん中身は
相当の際物なのでは
なかろうかと思われる。
ちなみに今現在の段階では
ソフトを出している会社も、
どうやら見つからないようなので、
見ようと思えば結局は
ネットで探して見るほか
現状では手段がない模様。
で、このネタを紹介するに当たって
映画の方はさすがに未見なのですが、
主題歌のPVの方は
ようつべさんで確かめてみました。
もう本当に久し振りに
ご尊顔を拝見した
ロギンスさんだったのですけれど、
まず衣装からしてまるであの
ジェイムズ・ブラウンのような
全身に星条旗を
あしらったという代物で、
うわ、ケニー・ロギンス、
今も十分若いんだなあなんて
少なからず受けたりしました。
そしてそれよりも何よりも
何が驚いたかといって
この方、声がまったく
老けていらっしゃらない。
このままで全然
FootlooseもDanger Zoneも
軽々といけちゃいそうな感じ。
本当、あの頃からまったく
休んでいないらしいだけのことは
十分あるよなあと思いました。
以前よりファンになって
しまいそうかもしれない。