今年一月、ボウイの直後に
やはりこの世を去ってしまった。
グレン・フライとおっしゃる。
慎んでご冥福をお祈りする。
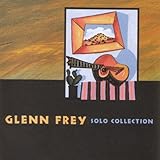 | ソロ・コレクション/グレン・フライ 1,851円 Amazon |
一応念のためだけれど、
このフライは、イーグルスの
ヴォーカリストの一人である。
のみならず、次回予定の
ドン・ヘンリーと並んで、
同バンドのいわば
双頭の一つだったといっていい。
事実、94年再結成以前の
イーグルスの七年あまりの
最初の実働期間中、
終始メンバーだったのは
この二人のみである。
Hotel CaliforniaやDesperado、
あるいは『呪われた夜』の
邦題で有名だろうと思われる
One of These Nightといった
強烈な楽曲群が
基本ヘンリーの方の
歌唱によるものだから、
こちらのフライの印象が
やや薄くなっている感は
否めないかもしれないし、
僕自身もやはり
イーグルスの声といえば
どうしても
ドン・ヘンリーの方が先に
浮かんできてしまいはするのだが、
同バンドの記念すべき
デビュー曲Take It Easyや
Peaceful Easy Feelings、
New Kid in Townなどで
リードを採っているのは
こちらのフライの方である。
今どれほどこのイーグルスが
聴かれているかは
正直よくわからないのだけれど、
個人的には、
このイーグルスこそ
現在に至るまでのアメリカの
ミュージック・シーンが産んだ
最も重要なバンドでは
なかろうかくらいに思っている。
そのくらいその
存在感は大きいといっていい。
まあでもこの印象には、いわば、
インプリンティングみたいな部分も
正直なくはなかったりもする。
それというのも実は
ELP(♯100)の
PICTURES AT EXHIBITIONと並んで、
僕自身が生涯で初めて
自分の手で
ターン・テーブルの上に置いた
洋楽のLPレコードが、
あのEAGLES LIVE
だったりするのである。
どちらも友人からの借り物だった。
音楽好きならこういうのを
聴かないとダメだよ、くらいのことは
その時いわれたような
気もしないでもない。
まあ記憶は当然
おぼろげではあるのだけれど。
当然中学時代の出来事だから
まさに80年代がようやく
幕を開けたばかりの時期である。
もちろんHotel Californiaを
初めて耳にしたのもこの時だし、
ほかOne of These Nightの
あのイントロのベース・ラインや、
Seven Bridges Roadの開幕の
恐ろしいほどまでに
美しいコーラス・ワーク、
そしてLife in the Fast Laneの
強烈なギター・リフ等々が
それこそ一発で
脳裏に刻みつけられた。
たぶんあれが
洋楽ってすごいんだなあと
心底思ったまさに最初の
瞬間だったのではないかと思う。
ちなみにアルバム単位での
全世界での歴代の売り上げでは
ここでも何度も書いているように
MJ(♯143)のTHRILLERが
頭一つどころではなく
抜けてしまっているのだが、
ことアメリカ国内に限っていえば、
同作とこのイーグルスの
75年発表の最初のベスト盤とが
今も凌ぎを削りながら
トップの座を争って
いるような状況であるらしい。
一時期はイーグルスの方が、
THRILLERの上に立った
場面もあった様子なのだけれど、
マイケルのあの突然の死もあって、
現在はTHRILLERが
これを抜き返している模様である。
しかもさらすごいのは
この一枚、ベストとはいうものの、
オール・キャリアの編成ではなく、
アルバムHOTEL CALIFORNIA
発表以前に組まれていた
コンピレーションなのである。
だから、解散直前の二枚からの
収録曲がなかったりするのに、
売れ続けているのである。
僕なんかはもう
自分のチャンネルが
洋楽に向いた時にはすでに
バンドは解散して
ほぼ過去の物に
なってしまっていた口なので、
基本はすべての楽曲を
後追いでしか
聴いていない訳だし、
Hotel Californiaの印象が
あまりに強烈過ぎるのだが、
それを欠いてもまだまだ
強力な楽曲群が
たくさんあるという訳である。
いずれにせよだから、
この事実からだけでも、
このイーグルスというバンドの
シーンへの登場が、
当時どれほど
センセーショナルな
出来事であったのか、
自ずと想像されて
来ようというものである。
この人たちをリアル・タイムで
経験できたというだけで
当時も今も、上の世代が
少なからずどころでなく
羨ましかったりもしたりする。
非常にざっくりとした
いい方になってしまうが、
イーグルスというバンドの
サウンドの一番の特徴は
明らかにカントリーや
フォーク・ロック
あるいはブルー・グラスといった
いわば白人由来の
メロディー・ラインを
どこかで継承していながらも、
彼ら以前に
存在していたそれらとは
まったく異なるものを
作り上げてしまった
点だったのではなかったかと、
今はなんとなくだが
そんなふうに把握している。
結局はロックとしか
呼びようがないことは確かなのだが、
でもやはりその範疇からは
確実にどこかがはみ出している。
AORの先駆けと
いってもよいのかもしれないが、
なんとなくその言葉の持つ
手触りよりはずしりと重い。
ミクスチャー・ロックという
スタイルに
先鞭をつけたといういい方なら
ひょっとしてできるのかもしれないが、
やはり彼らの音はどこか
アメリカ・オリエンテッドなのである。
しかもその独自の立ち位置は
現在に至るまで
微塵も揺らいではいないといえる。
僕の耳にまだ届いていない
だけという
可能性もなくはないかもしれないが、
今までに聴いた
どのアーティストの
どのレコードのどの楽曲も、
あ、これイーグルスに
すごく似ているなと
そんなふうに思わせられる場面は
ほぼまったくないといっていい。
この点にはあるいは
大きく首を縦に
振って下さるような方も
多少はいらっしゃるのでは
ないかとも思うのだが、
いかがだろうか。
ではこの辺りでざっくりとだが、
イーグルスの歴史みたいなものにも
一応言及しておくことにする。
デトロイトとテキサスから、
それぞれにロスへやってきた、
このフライとヘンリーとが
リンダ・ロンシュタットという
シンガーのバック・バンドなどの
活動を続けていくうちに、
ランディー・マイズナーと
バーニー・レドンの二人と出会い、
やがてこの四人が結成したのが
最初のイーグルスの形であった。
デビュー前の時期、
フライとヘンリーは、
やはり当時ロスに拠点を置いていた
ジャクソン・ブラウンや
あるいはJ.D.サウザー等とも
親交を持っていたそうで、
イーグルスの作品の中には、
こういったメンバーとの共作曲も
幾つか見つけることができる。
カリフォルニアの
安アパートの一室で、
まだ若かったフライとヘンリーと
時折り混じるほかの面々が
ギターやピアノを鳴らしながら、
モチーフを膨らませ、
それが一番活きる展開や
旋律あるいは言葉を
ああでもないこうでもないと
必死になって探している。
そんな光景が
時に浮かんできたりもする。
フライとヘンリーの卓越した
ソングライティングの技法は、
おそらくはこの時期に
徹底して磨かれたのだと思う。
デビューからたちまちにして
巨大な存在になったバンドには、
やがて五人目のメンバーとして
ギターのドン・フェルダーが
迎えられもするのだが、
その後、前述のレドンとそれから
マイズナーとが順次脱退し、
後任にそれぞれ、
ジョー・ウォルシュと
ティモシー・B.シュミットとが加入する。
80年の解散時と、
それから94年の再結成時は
この五人のラインナップである。
この点は触れようかどうしようか
迷わなくもなかったのだが、
残念ながらフェルダーは
ちょうど2000年前後の時期に、
バンドを解雇されてしまっている。
この方はHotel Californiaの
あのツイン・ギターの
一方を担っていたプレイヤーであり、
しかも同曲の成立に関し、
非常に大きな役割を
果たしていたことは
間違いのないだろう存在なので、
個人的には痛恨の出来事だと
いってしまっていいくらいの
衝撃ではあったのだけれど、
背景はどうやら
金銭的な面までも含めた
バンド内でのポジションの
問題だった模様である。
いや、本当、
どうにかならなかったかなと思う。
詳しいことはもちろん
僕にはわからないのだが、
確かにイーグルスの根幹が、
ヘンリーとフライの
二人であることは
どうしたって揺るがない。
それでもフェルダーにしてみれば、
Hotel Californiaの件も含め、
彼より後の参加の二人とは、
明らかに貢献度が違うといった
自負もあったに違いないとは思う。
どうやらその辺りの配分が、
騒動の根っこと
なってしまったらしいのである。
なんだか読むと嫌な気分に
なってしまいそうなので
このフェルダーの自伝については、
存在は知りつつも、
手を伸ばすことは未だしていない。
それでも同書の献辞が、
フライとヘンリー以外の、
メンバーへと捧げられているなんて
記述を見つけてしまったりもすると、
何もそこまで、と
思ったりもしてしまうこの頃である。
フライが他界してしまった今、
和解が為される可能性は
ほぼまったく潰えてしまった訳で、
返す返すも残念極まりなく思う。
――いや、やはりこの話題は
この辺りで止めておくことにする。
さて、イーグルスのトラックの中で
おそらくはフライが
中心になって作られただろうと
判断できる楽曲群の多くに
共通しているように思われるのは、
なんといえばいいのか、
身を任せ易さとでもいった感じの
不思議な空気感である。
穏やかとかメロウとか、
ある種そういうニュアンス。
しかもこのタイプのトラックには
グレンの声が見事にはまるし、
曲の展開もそれぞれ
本当に上手いよなあとつくづく思う。
肩の力というか心の緊張というか
そういうある種の
体に巣くった強ばりみたいなものが、
少しずつほぐれていくような
そんな錯覚さえ
時に起きてきてしまうのである。
それこそまさに
Peaceful Easy Feelingsと
いった感じであろうか。
ヘンリーのヴォーカルによる
トラックは大体の場合、
どこか深い、あるいは
日頃は隠れさているような場所へと
有無をいわさず切り込んでくる、
そういう鋭利な強さを持っている。
そういうある種の緊張が、
並んで登場するトラックで、
フライの声なり、あるいは
彼の書いたメロディーなりに
触れることによって、
なんというか
ほどよく中和されてくれるのである。
今になって見れば
この緩急自在ともいうべき匙加減が、
イーグルスというバンドの
サウンドの幅の広さの
根幹だったのかもしれないとも思う。
もちろん他のメンバーの
ソングライティングによる
トラックもたくさんあるし、
それに二人ではなく
ほかの共作者を加えて
ものされた作品群には、
微妙に不思議な手触りが
随時加わっていることも事実だから、
まあだから本当
イーグルスの作品には
飽きるということが
まったくといっていいほど
なかったりもするのである。
さて、どうやら結局は
イーグルスの話ばかりに
なってしまったようだけれど、
今回のチョイスは
彼のソロ時代の作品からである。
このThe Heat Is Onは
85年に二位まで昇り詰めた、
ソロ時代のフライ最大の
ヒット曲の一つである。
書き方がちょっと
歯切れ悪くなっているのは、
実はこの同じ年に
You Belong to the Cityなる
もう一つのトラックもまた
同じ位置まで上昇しているので、
こんな表現にならざるを
得なくなってしまっている次第。
それでも個人的な好みでは
こちらのHeat Is Onの
圧勝だったりする。
あるいはフライらしいといえば、
You Belong~の方に
軍配が上がるのかもしれないけれど、
こちらのHeat Is Onは
比較的アップ・テンポの
軽快なロック・ナンバーである。
同曲はエディ・マーフィーの映画
「ビバリーヒルズ・コップ」に
起用されていて
しかもいいところで流れてくるので、
聴けば多くの人が
ああこれか、と
思い出すのではないかと思う。
――しかしつくづくカッコいい。
イントロの最初の音からだけで
真夏の夜のあの
アスファルトの上に
ねっとりとわだかまるような
異質な熱の気配が
耳からだけなのに
むんむんと伝わってくる気がする。
そしてすぐに始まる
サックスのラインが
もう本当にどこにも文句の
つけようのないほどに
クールだったりするのである。
ひりひりとした
アメリカン・ロック・スピリッツ
みたいなものを、
痛切に感じさせてくれる。
無理矢理にでも気持ちを
持ち上げたい時に、
この曲を引っ張り出してくる場面が
今でもしばし
あることもまた本当である。
おかげさまで実は11年の
イーグルスの来日公演には
足を運ばせて
いただくことができた。
フェルダーが抜けてしまった
四人のステージではあったが、
あの完璧なハーモニーも
ロック・スピリッツも健在だった。
当然舞台の上でだけの
ことでこそはあるのだけれど、
実際に目にしたフライの印象は、
それまで持っていた通りの、
気立てのいい、しかも同時に
細やかな人物といった感じで、
一見して気むずかしそうな
天才肌のヘンリーや、
あるいはやや奇人の
趣さえ感じさせないでもない
ウォルシュといった個性を
たぶんこの人がバンドとして
繋ぎ止めているんだろうな、
なんてことを改めてつらつらと
想像させられもしたものである。
しかし、そのフライまで
逝ってしまったのだなあと思うと、
ついつい
People come, people goなんて
手垢のついたいい回しを
口にしたくもなってくる。
改めて、合掌したい気持ちが募る。
たぶんこのテキストが
仕上がったら一回本当に
するのだろうなと思っている。
なお、本テキストの仕上げの最中、
今度はピート・バーンズ(♯91)の
訃報まで飛び込んできてしまった。
関係ないんだけれど
あまりにびっくりしたので、
思わずここに書いてしまった。
まったく今年は
本当になんて年なんだろう。
さて、ではそろそろ締めの小ネタにいく。
今回はややあっさりめ。
以前ここでもとりあげた映画
リドリー・スコットの作品
『テルマ&ルイーズ』(→こちら)の
挿入歌に使われているのが、
このフライの91年のソロ作品
STRANGE WETHERからの
Part Of Me, Part of Youなる
トラックだったりする。
映画の隠し持ったテーマと
これほどマッチしている
タイトルもそうそうない気がする。
もっともある意味
決してハッピーエンドではない
映画のラストとは違って、
曲のタッチは少し明るめで、
これがエンディングに
かかってくることでやっぱり、
何かが中和されているような
気がしないでもないのである。
それからフライはイーグルスの
いわゆる活動休止期間中に
役者として結構
テレビやドラマにも
出演していた模様である。
僕自身は未見なのだが
トム・クルーズの
『ザ・エージェント』では
結構重要な役どころで
登場してもいるらしい。
本記事の仕上げまでに見ることは
結局叶わなかったのだけれど、
そのうちちゃんと
目を通してみようと思っている。