僕自身、自分が
デビューしてから後、
つまりは00年代に入って
少し過ぎてから、
いわば後追いみたいな形で、
初めて手を伸ばしてみた
アーティストが並ぶ。
まずはこの、
カーディガンズなるバンドから。
ライフ+5/カーディガンズ
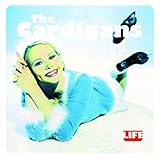
¥1,851
Amazon.co.jp
それにしても、90年代に入って、
前回のロクセット(♯123)や
次回予定のメイヤまで含め、
こういう、なんといおうか、
ある種ノスタルジックで、
かつ極めてポップな
メロディー・ラインを
有しているサウンドが、
英米のどちらからでもなく
スウェーデンという
ヨーロッパどころか、
世界でほとんど
一、二を争うとでも
いっていいような
高緯度の国から
登場してきていること、
しかもそれが、
どうやらこの日本でも
十分に衆目を
集めていたらしいことは
個人的にはなかなか
興味深かったりもする。
もっとも、
とりわけこの時期の
シーンの動向に関しては、
単に僕が知らないだけという
可能性も決して
否定できはしないのだけれど。
さて、いつだったかの記事に
ついつい書いてしまったけれど、
より正確を期していえば、
92年からの
丸々十年間というのは、
実際日々僕自身、
食うや食わずやのカツカツで、
週に二度、近所の総菜屋さんが
半額近くまで値引きして
売ってくれていたコロッケを
その都度まとめ買いしたり、
あるいは一枚の鶏の胸肉を、
大体五つに分けて冷凍し、
その一個ずつを
一食分の焼きソバの具に
使ったりもしていたのである。
こういうのは、
できればすっかり
忘れてしまいたいくらいの
記憶であるといってもいいのに、
今に至るまでなお、
ちっともまったく忘れられない。
むしろ焼きソバを
作るたびに必ず思い出す。
まあだからつまり当時は、
好き勝手にCDを買い求めるなど
夢の夢のさらにまた
見果てぬ夢みたいな、
いわばそんな状態だったのである。
それで仕方なく、
当時の手持ちのアルバムを、
アーティスト別に並べて、
Aから順に聴いていったら、
はたしてどのくらいかかるか、
なんてことをやったような記憶も
実はないでもない。
あの時ででも、確か三ヶ月では
全然終わらなかった気がする。
今はもっとかかるだろうなあ。
まあとにかくである。
おかげさまで03年の初頭に、
そんな日々もついにようやく
終わりを告げてくれることに
なった訳なのだけれど、
そういった理由で、
正直なところ、
主に90年代の中盤以降に、
脚光を浴びていた人たちというのは、
洋邦問わず、
全然明るくないのである。
まあそんな時期でも、
ふと耳にした途端に、
引っかかってくる音というのは、
やっぱり幾つかあった訳で、
たとえばLUNA SEAの
あの頃の破竹の勢いは、
かなり鮮明に見えてきていたし、
ほか、MY LITTLE LOVERの
Man and Womanとか
あるいはDRAGON ASHの
Grateful Daysなんかは、
耳に入るなりすぐ
あ、これ絶対すごい、
みたいな感じで、
持っていかれた記憶もある。
まあそのうち気が向いたら、
この辺りのトラック群も、
あるいはエクストラの方で、
追々取り上げるかもしれないが。
さて、いつもよりもずいぶんと
前置きが長くなってしまったが、
だから今回は、
カーディガンズなのである。
このCarnivalという曲が
本邦で脚光を浴びたのは、
どうやら大体
95年か96年頃の
ことであった模様。
当初はカヴァーでこそあったが、
車のCMに起用されたことが、
大きなきっかけとなったらしい。
たぶん僕自身も
その時期に一度や二度ではなく
耳にしていたのでは
ないかとも思うのだが、
さすがに記憶は定かではない。
I will never know,
Cause you will never show,
Come on and love me now,
Come on and love me now――
シンプルなこのヴァースを
繰り返して載せてくる、
ちょっと物憂げで
わかりやすいメロディーと、
それからその直後に登場してくる
ストリングスの
やや大仰で印象的なパターンが、
たぶん一発で記憶に残る。
もちろんCMで使われたのも
この箇所である。
きちんとストリングスのラインまで、
フィルムに載っているところがまた、
正しいというか、こうだよな、と思う。
しかも実はどうやらこの曲、
後年になって彼らの
オリジナルのヴァージョンも、
やはりコマーシャルに
採用されているらしいのだが、
この二回が二回とも、
車の宣伝なのである。
これもしかし、なんとなくだが
十分に頷けてしまう。
狙っているだろう雰囲気が
この箇所、本当にハマるのである。
いうなれば、日常の中の
非日常とでもいうのが
一番相応しいのかもしれないが、
確かに休日のドライヴ的といおうか、
無理までしている訳では
決してないのだけれど、
それでも頑張って、
いつもよりちょっとだけ
贅沢しているみたいな空気を
このトラックのこのパート、
絶妙に演出してくれるのである。
洒落ているかというと、
それは確かにそうなのだが、
実はそれほどそうでもない。
ああ、いい方が下手糞ですいません。
でもまあ、そんな感じです。
たとえばバーシア (♯108)や
あるいはSOS(♯21)ほどに、
作り込まれた音では決してないのに、
そういう種類のサウンドと
どこか似た手触りが確実にある。
もちろんヴォーカルのニーナの
ぎりぎりコケティッシュと
いってもいいような、
その独特の声も
明らかにこの雰囲気を
醸し出す効果の一端を
間違いなく担ってはいるのだが、
何よりもこの人たちの
作り出してくる
メロディーラインと、
バンド・アレンジの方法論が
実はひどく独特なのだと思う。
ヨーロッパ風の哀愁をまとった
旋律と音色でもいえばいいのか。
ありそうで、実は
なかなかなかった。
そんな感じがするのである。
今回のこのLIFEというアルバムは、
表題にしたCarnivalのみならず、
全編全曲、
そういうテイストに
隅から隅まで満ちている。
なかなかやっぱり、
代わりの見つかってこない種類の
サウンドではないかと思う。
前回のロクセットの
アルバムJOYRIDEの開幕と
どこか似たアプローチで、
本作もまた、
移動遊園地みたいな
雰囲気を漂わせてくる、
オルガンに寄せた音色の
シンセサイザーのSEから始まる。
開幕はもちろんCarnivalで
そこから10曲目の
Closing Timeまで
様々な工夫を凝らした、
でもやっぱりなんとなく、
そんなに大掛かりな
機械仕掛けではない感じの、
たとえばコーヒー・カップとか
あるいは射的や輪投げみたいな
そんなチープな
アトラクションを
時折チュロスやら、
ソフトクリームやらを
買い食いする場面を挟みながら、
順次乗り継いでいくようにして
アルバムの全体が展開していく。
いや本当に
ノスタルジックという言葉が
いかにもハマるサウンドなのである。
だからたぶん、
ずいぶんと以前に
ここでも取り上げた
フェアグラウンド・
アトラクション(♯29)なる
イギリスのグループの
得意としていたアプローチを、
すべての面で継承したとまで
いってしまったとしたら
あるいはいい過ぎに
なるのかも知れないけれど、
そんな感じのサウンドである。
同バンドや、あるいは
初期のEBTG(♯20)辺りが
お好きな向きであれば、
このバンドも九分九厘行けると思う。
本当に、佳曲ぞろいというか、
Carnivalの繊細な気怠さを
決して裏切らないトラックが続く。
しかもこの点は
追加収録されている
先行して発表されていた
五曲に関しても
まったく変わらない。
中でもCelia Insideは
個人的に
ひどく気に入っている。
ただ一つだけ
不満があるとしたら、
オリジナルの編成では
ラストの収録だったであろう、
上にもタイトルを出した
Closing Timeの展開である。
これ、10分の楽曲なのだが、
途中で三分くらい、
無音の状態が
挟まっているのである。
終わったかな、と思っていて、
いきなりまた音が出てくると、
毎回ちょっとだけ
びっくりしてしまう。
まあ目くじらを
立てるようなことでは
決してないのだが。
本作の後、アメリカへの
本格的な進出を
ターゲットにしたことで、
バンドの音や、あるいは
ソングライティングそのものが、
少し重めにシフトして
しまったらしいことは、
個人的には
ほんの少しだけ残念である。
もっとも、次のアルバムには
まだ手を出していないので
軽々しく断言するべきでは
ないのだが、
でもLovefoolやBeen Itなど、
同作所収の代表曲は、
正直、聴いてもいまいち
ピンと来なかったことは本当である。
さて、では締めのトリビア。
これは僕も、
今回ネタを見つけてきて、
本当にびっくりしたのだけれど、
このカーディガンズ結成の
中核となった、
ギターのピーターと
ベースのマグナスの二人は、
そもそもはメタルの
ミュージシャンだったのだそう。
しかもあのブラックサバスの
コピーとかをやっていたらしい。
だから彼らのレパートリーには
こっそりと、
あのオジー・オズボーンらの
ソングライティングによる
同バンドのナンバーが
幾つか紛れ込んでいたりもする。
しかしそれも、
このニーナ・パースンの
ヴォーカルと、
彼らのバンド・アレンジにかかると、
原曲がメタルだとは
想像すらできない仕上がりで、
むしろカーディガンズ独特の
サウンドとしか
響いてはこないから、
実に不思議である。
こういうのをやはり、
強烈な個性と
いうべきなのだろうなあと
改めて思った。
僕も今回この記事を
起こし始めてから、
Sabath Bloody Sabathに関しては
原曲を探して聴いてみたのだけれど、
いったいどういう発想をすれば、
この曲をこんな具合に
仕上げてしまうことが
できるのだろう、と
誇張ではなく
しばらく唖然としてしまった。
いや本当、全然彼らの
オリジナルみたいなのである。
むしろ原曲の持っていた美しさが、
巧妙に抽出されている印象もある。
原曲をすっかり
飛び越えてしまえる、
こういうレヴェルに
到達しているカヴァーは、
本当、すごいなと思う。
もちろんなかなか
見つかってくることはないけれど。
すぐに浮かぶのはロッドの
In My Lifeくらいのものである。