いや本当、こういう音楽が
スウェーデンなる国から
出てきたというのは、
なんだかとても不思議である。
マイ・ベスト/メイヤ
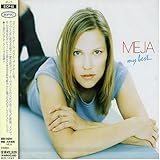
¥2,592
Amazon.co.jp
時々気が向いて、
90年代と銘打たれた
コンピレーションを
手に取ってみることがある。
自分がよく知らない時代に、
どんな音楽が
巷に流れていたのかを、
やっぱり時々は
確かめてみたくなるのである。
まあ近頃はそんな企画すら
ついぞ見かけなく
なってしまった気もするが。
いつのまにもう、
10年代に突入してしまって
いるんだもんなあ。
しかも、もう後半だし。
90年代でさえもう二つの
ディケイドの向こう側である。
改めてそう考えると愕然とする。
まあ、年をとるというのは
つまりはそういうことで
あるらしいのではあるのだが。
訃報もやっぱり目につくし、
しかも若い頃と比べて、
のしかかってくる重みが違う。
その人たちの活躍を
目の当たりにしていればこそ、
起こってくる感情もある。
さて、例によってまずはこのまま、
横道に逸れていくことにするが、
実はこの前思わずプリンスの
When Doves Cryの
シングル・レコードを
中学の頃よく足を運んでいた
レコード屋さんで
手に取っているという
自分でもやや
いかにもな夢を観てしまい、
目を覚まして
なんだかすっかり
途方に暮れた気分になった。
ああいう場面をもう一度
経験することは
絶対にできないのだな、と
改めてそんなことを
つくづく感じてしまったのである。
ついでなので書いてしまうが、
このWhen Doves Cryには当時、
『ビートに抱かれて』という
邦題がつけられておりました。
子供心に、なんでって思った。
いや、高校生だったけど。
ま、わかるっちゃあ、
わかるんだけどね。
さすがに「鳩が鳴く時」で、
シングルは切れないよなあ。
今ならたぶん
「ホエン・ダヴズ・クライ」で
そのまま行けるんだろうけれど。
そういうのもまた、
時代の変化だったりするのだな、と
この年になればこそ
痛感したりもするのである。
この前ちらりと何かで
観るなり読むなりしたのだが、
80年代というのは、
年末の紅白の裏番組として、
洋楽のアーティストの
ライブが編成されて
十分通用するくらい、
いわば史上一番本邦で
洋楽が聴かれていた時期らしく、
そういう時代に
ティーンネイジのほとんどを
送ってしまったが故に、
いまだに基本、その当時の音楽が、
僕の部屋には流れて続けている。
そういう音楽たちの力を借りて
ようやく最後まで出来上がった
作品というのもいっぱいある。
というか
書籍になってくれたものも
まだPCの中に
眠っているものも含めて
ほぼ全部だといっていい。
たぶん最後までずっと
こうなんだろうなあ、と思う。
だから本当、人の一生というのは
時代なるものと、切り離しては、
決して成立などしないのだよな、
なんて、
堅苦しいけど当たり前のことを
改めて思い知ったりもしてしまう。
で、まあ、こんなことを
つらつらと考えていると、
自ずと殿下の
Sign of the Timesなんて
曲名が浮かんできたりして、
ああ、それはとどのつまり、
僕ら自身のことだったんだと、
それをまあこの方は、
こんな短い一節で、
絶妙に切り取っていたんだなあ、と
感慨を新たにしてしまう訳である。
いや、横道はそろそろ
今回はこの辺りにしておこう。
そういう訳で、
たまたま手にした
90年代のコンピレーションの
とある一枚の中で、
一際異彩を放っていたのが、
今回ピックアップした
Hippies in the 60’sという、
いかにも風変わりなタイトルの
メイヤによる
この一曲だったのである。
カーディガンズ(♯124)の方は、
どこでまず名前を知ったのかすら、
正直きちんと覚えていないのだが、
こちらは忘れもしない、
間違いなくこの時が
彼女の音楽との
最初の出会いであった。
ちょっと古臭い音色の
適度にエッジを立てた
ハードなギターのパターンで、
同トラックは幕を開けている。
それだけでもう、
収録のラインナップの中で
なんというか、立っていた。
むしろちっとも
90年代っぽくないよな、これ。
そんなふうに思いながら
さらに聴き進めていくうち、
サビのラインが
出てきたところで、
あ、これ相当面白いや、
今回は当たり引いたな、
くらいに思った。
アルバム探してこないとな。
もうほとんど
即断であったようにも
記憶している。
こんな具合に、
予備知識などまったくなしで、
いいな、と思える
音源に出会える瞬間は
僕にとっては至福である。
さて、では問題の
そのサビのフレーズを、
例によってちょっとだけ
勝手に訳出してみる。
60年代のヒッピーたちは、
お金が神様じゃないって
ちゃんと知ってた
あたしもそこにいたかった――
まあこんな一節を
ポップ・ソングで真正面から
ぶつけられてこようとは、
正直身構えてすら
いなかったので、
虚を突かれたというか
はっとしてしまった部分は
確実にあったと思う。
しかも、歌詞カード片手に
改めて聴きなおしてみると
この曲、冒頭から結構強烈な
単語というか、
表現が並んでいて
さらにびっくりさせられた。
幸せを感じるために
セラピーなんか必要ないし
ディズニーもいらない
その方法をあなたに教えて
もらうなんて必要もなれば
テレビだっていらないの
ただ自由であればいい――
まあこんな具合に、
至極シンプルで、
でも十分以上に
アイロニックなヴァースが
矢継ぎ早に
畳みかけられていたのである。
2コーラス目に入っても、
美容整形やら、
エクスタシーやら
報酬やらアップグレイドやら
むしろ今現在の社会にも
十分通じてしまいそうな、
それこそ時代の表象みたいな諸々を
きっちりと韻を踏みながら
このメイヤは
真っ向からあげつらっていく。
快哉を上げるというのは、
こういう時に使うのが、
一番いいのかな、と思ったくらい。
ちなみに上のエクスタシーは
ここではドラッグの俗称として
捉えるのが
本当なのだろうとは
思うのだが、
別にどっちに取られても、
かまわないやくらいのつもりで、
この人は敢えてこの言葉を
選んだんじゃないのかなあ、などと
勝手に想像していたりもする。
それにしても、
Money isn’t Godである。
60年代のヒッピーたちは、
それをちゃんとわかってた、と
いうことはつまり、
言外に、今はそうではない、と
いおうとしていることになる。
いや、それは僕らだって
十分わかっているよって、
まずはやっぱりそう考えた。
少なくとも自分は
そんなふうには思っていない。
――そのはずだ、と。
でもこういうふうに、
正面からぶつけられると、
さらに自問せざるを得なくなる。
たとえば食事の前や就寝前に
神に感謝の祈りを捧げる習慣と、
毎日毎日ニュースの終わりに、
為替や株式市場の上下動を、
画面一杯の数字で確認することの、
どこからが違う行為で、
どこまでが似ているのだろう。
あるいはそういうやり方で、
僕らが経済と呼んでいる事象は
昔神様というものの
立っていたはずの場所を
自分のものにしようと
しているのかもしれない。
まあポップ・ソングを聴きながら
そんなことまでついつい
考えてしまった訳である。
しかもこのトラック、
旋律もアレンジも
それからノリも、
すごく気持ちがいいものだから、
ついついリピートしてしまう。
困ったものである。
でも本当、この前の
佐野さんのアルバムでも実は、
同じようなことを
感じさせられていたのだけれど、
音楽を聴くという行為の
いわば外側へとまで、
こんな具合に軽々と
連れて行ってくれるタイプの
サウンドというか、
アルバムなりトラックなりに、
出会えるということは、
本当に貴重な体験だと思う。
Hotel Californiaとか、
たぶんそういうタイプの
楽曲だったんだろうと思うし。
さて、思わずリリクスの
話ばかりになってしまったが、
このメイヤの
サウンドについてもう少し。
今回ジャケ写は
ベスト盤を選んだが、
Hippies~にしこたま
打ちのめされたものだから
アルバムも一応三枚は聴いている。
全体像を一言で表現するのは
もちろんすごく難しいのだが、
冒頭でも触れたように、
ヨーロッパの音と
いうよりはむしろ、
それこそ60~70年代の
アメリカで隆盛を誇った
カントリーの系譜に連なる
いわばフォーク・ロックとでも
いうべきジャンルの音楽の、
その進化形みたいな手触りである。
基本そういったスタイルに、
80年代っぽい、音の厚みと
散らばり具合が加わって、
どのアルバムも、
不思議に洒脱で、
少なくとも僕にはとても
心地よい仕上がりとなっている。
しかもトラックのそれぞれも
統一感を保ちながら、
適度にばらけていて退屈しない。
ラーガ・ロックと
いうのだそうだが、
時折シタールや
それに似た音色が奏でる、
微妙に歪んだ音階を
非常に上手く
使ってくるような場面もあって、
そんなところもまた、
70年代っぽいな、と思う。
今回取り上げた
Hippies~のみならず、
先行したHow Crazy Are You?と
All ‘Bout the Moneyとは
すでに名曲の域にまで
届いているといっていい。
きちんと作品ごとに、
その一枚を代表するに
十分に足るトラックが、
出てきているところなど、
このメイヤ、
只者ではなかったのだろう。
実際デビュー盤は
手元の商品のコピーによれば
国内だけで実に80万枚を
売り上げているのだそうで。
洋楽でこの数字は、
ちょっとどころではなく驚きである。
まあ、90年代が、
CDというものが
一番売れていた
時代であることを鑑みたとしても、
やっぱりものすごい。
ことこの人に関しては
ほかにも触れたかった曲が
実は一杯あるのだけれど、
そろそろもう十分長いので、
今回は稿を譲ることにさせていただく。
SpiritsとかMy Best Friendとか
Seven Sisters Roadとか
Land of Makebelieveとか
好きな曲が結構幾つも見つかるし、
やっぱり歌詞に
はっとさせられるような場面が
実は多々あったりもするのだが、
これらに関しては、
いずれまた機会を改めて。
さて、前回のカーディガンズにせよ、
あるいはこのメイヤにせよ、
そもそもが全編を英語で歌った、
アルバムを作ってくれていなければ、
さすがにたぶん、彼らの歌が
僕の耳にまで入ってくることは
やっぱりなかったんじゃ
ないかなあ、と思う。
そして、彼らがそういう決断を
しっかりとできたのはやはり、
まずアバ(♯122)が
そういったルートを切り拓き、
そして次回予定の
北欧メタルのヨーロッパや、
あるいはこの前の
ロクセット(♯123)などの
大きな先例があったからこその
ことなのだと思う。
そういう訳で
来週はヨーロッパの登場である。
では締めの小ネタ。
実はこのメイヤ、
ジブリアニメの、
かなり熱狂的な
ファンなのだそうで、
もちろん日本側から
持ち込んだ企画なのだろうが、
10年には、ジブリ・ソングスの
カヴァーアルバムも
発表しているのだそうである。
タイトルは、これは邦題だけれど
『アニメイヤ』というのだそう。
ちょっとどんな音になっているのか
すぐには想像がつかないけれど、
まあ、そのうち
手にとってみるかもしれない。
あ、でも確かに、
Country Roadは
それこそメイヤ自身の
ルーツっぽいかもしれないや。