ザ・コレクション~ベスト・オブ・クラウス・ノミ/BMG JAPAN
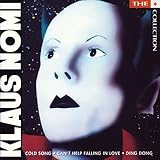
¥2,160
Amazon.co.jp
異形、という言葉が
やっぱり一番似つかわしいかなあ。
ジャケ写のイラストからだけでは
さすがにすぐには
わからないかとも思うのだけれど、
この方、一応男性である。
しかしながら、その音域は
ほとんど女声のそれといっていい。
こういったタイプの方、
以前にもここで、
ジミー・ソマーヴィル(♯31)なる、
ブロンスキ・ビート/コミュナーズの
リード・シンガーだった人物を
取り上げてはいるのだが、
このノミの場合、
おそらくその上をいっている。
完璧にクラシックの発声で、
しかもたぶん、相当上手い。
それも道理で、このノミは
幼少時からきちんとした
声楽の訓練を受けていたのだそう。
カウンター・テノールと
いってしまっていいのか、
まあそういう種類の声である。
その声が、黎明期にほど近い、
やや荒削りな
シンセ・サウンドに載っている。
そういう意味でもまた
異色の存在だったといえよう。
もちろんその限りではない
アプローチのトラックも
幾つか残されてもいるし、
実際過去の経歴では、
オペラへの出演経験も
わずかながらだがあるらしい。
確かに、どこを目指して
売っていけばいいのか迷う種類の
音楽性だったのだろうなとも思う。
ノミはだから、そういう
クラシックの教育を受けた後、
シンガーとしてでは
なかったようだが、
一応自国ドイツの劇場に
職を得てもいたようである。
それが十代の頃に出会った
プレスリーのレコードに魅せられて、
結局そちらが忘れられず、
ロックといおうか、
ポピュラー・ミュージックへの
転向を目指し、
72年、30歳を前にして
単身アメリカへと渡り、
ニュー・ヨークに拠点を定め
デリやそういう場所で働きながら
改めて音楽活動を
スタートさせた模様である。
パティシエとしても
それなりに優秀だったらしく、
ケーブルテレビへの出演も
あるとかないとか。
それでもまあ、
ボヘミアンチックとでもいうか、
なかなかチャンスの訪れない
行く先の皆目見えないような、
そういう時期が続いたことも
またおそらく間違いはないのだろう。
それでもついにその彼に、
一つの転機が訪れたのは、
おおよそ78年辺りの
出来事だった模様である。
さて、70年代後半から
80年代初頭にかけての
ニュー・ヨークという街は
それこそたぶんまさしく
ミュージカルの『レント』で
描かれていたような
世界だったのでは
なかろうかと思われる。
些か陳腐な表現になるが、
それこそ、このノミのように、
いつか訪れてくれるはずの
サクセス・ストーリーを
夢見る若者たちの
鬱屈したエネルギーの
たまり場のような趣に
満ち満ちていたのでは
なかろうかとも思われる。
イースト・ヴィレッジ・シーンなんて
いい方も時にするようではあるが、
クラブや小劇場、
もちろんオフ・ブロードウェイや、
あるいはむしろ
ストリートそのものに
その種の活気が迸っていた
時代だったのではないかと想像される。
ノミがまず衆目を集めたのは、
そんな流れの中で催された、
「ニュー・ウェイヴ・ヴォードヴィル」と
銘打たれたイヴェントでのことだった。
音楽やらコントみたいな寸劇やら、
そんな出し物の中に突然、
裃(かみしも)さながらに肩の尖った
宇宙人みたいな格好と
まるでデスマスクみたいな
極端なメイクで登場したノミは
そこでいきなり、
サン-サーンスのオペラ
『サムソンとデリラ』からの
アリアを披露したらしい。
ある種猥雑といっていい
クラブ・シーンの雰囲気の中で、
その極致ともいって
いいような格好の男が、
荘厳というか、透明というか、
美しいと形容してしまえば
やっぱり陳腐にしかならないけれど、
そういう種類の歌声を
高らかに響かせた訳である。
この時のインパクトは
相当強烈なものだったらしく、
このノミの名前は、
すぐさま好事家というか、
音楽関係者といっていいのか、
たちまちそういった界隈に
口コミで広がって
いったのだそうである。
しかもそれがついに、
当時プロモーションのために
渡米を企画していた、
またぞろこの方の登場で
些か申し訳なくもないのだが、
あのボウイの耳にまで
届いたらしいのである。
しかもこの時ボウイは、
予定されていたテレビ出演の際の
コーラスとバック・ダンサーを
このノミにオファーしてきたのである。
ノミはだから、
当時のバンドのメンバーと二人で、
メジャー・デビューに先立って
『サタディ・ナイト・ライヴ』への
出演を果たしたという訳である。
もちろん自分の持ち歌を
歌った訳ではないのだが、
この時のパフォーマンスを
一つのきっかけとして、
ようやく念願であった
メジャーとの契約を
獲得することに成功した。
こちらが79年の出来事だった。
ここがでも、
不思議な部分だなあ、と
思わなくもないのだけれど、
この時手を挙げたのは、
どうやらBMGのフランス
だけだった模様なのである。
確かにアメリカで
大きく受けそうには思えない
スタイルだったのかもしれない。
実際ニュー・ヨーク以外の場所での、
ライヴでの反応は
散々だったといった
話もあるようである。
結局このノミは、
デビュー作とその次のアルバムを
リリースした直後の81年に、
44歳という若さで、
この世を去っている。
死因はエイズによる合併症だった。
だから、この病気で亡くなった、
極初期の著名人の
一人であるという文脈で
このノミの名前は今もしばしば
巷間にて語られている模様である。
結局メイン・ストリームには、
ついに手が届くことが
なかった人だと
いってしまっていいのだと思う。
そういう訳で、僕も当時は、
さすがにこの人の作品にまでは
手を出してはいなかったのだが、
03年に彼の生涯を
題材にした映画が公開されたことと、
それから『北緯~』なる作品で
僕の大まかな嗜好を知って、
きっとこのクラウス・ノミは
浅倉さん気に入ると思いますよ、と
勧めてくれた方がいたもので、
遅ればせながら
手にとってみたという次第。
聴いたのは上に掲げた
ベスト盤一枚きりなのだけれど、
なんというか、
雑食といおうか、
実に取り散らかっている。
最初に触れたように、
シンセを前面に出した
ロックバンドの編成で
仕上げている楽曲もあれば、
ピアノやストリングス、
あるいはチェンバロにオルガン
みたいなサウンドだけの
バッキングで、
ぱっと聴いただけでは、
クラシックのトラックに
思えてしまうようなものもある。
実際シューマンや、
バロック期のイギリスの作曲家
パーセルの作品は、
好んで取り上げていたようなのだが、
かと思えば、それこそプレスリーや、
チャビー・チェッカーを
変化球気味にカヴァーしてみたり、
あるいはミュージカル・ナンバーに
手を伸ばしてもいたりする。
そういう取り合わせを
コンピレーションながらも
一枚の作品として
続けて聴くことを
可能にしてしまっているのは、
やっぱりこのノミの
独特の声だったりする。
ちなみにプレスリーのカヴァーは
ここでも以前、UB40(♯73)の
ヴァージョンを取り上げた
Can’t Help Falling in Love
なのだけれど、
これがビリー・ジョエルの
This Nightみたいに
ベートーヴェンの『悲愴』の
あの第二楽章のメロディーから
始まっていたりもしたりする。
さすがに最初は、
あれ、と思った。
それでもこの曲に
基本ピアノだけのバッキングが
それなりにはまっているから面白い。
個人的には、
『オズの魔法使い』からの
Ding Dongとか、
やや芝居がかった歌い方を
許される種類のトラックが、
本人も楽しんでやっているのか、
活き活きと歌っているように思えた、
ちなみにあのモリッシーが、
このノミを非常に
気に入っているらしく、
自分のコンサートのオープニングに
彼のトラックの幾つかを流したり、
あるいは自身が
大きく影響を受けた10曲の中に、
上でも少しだけ触れた
シューマンの『くるみの木』の
このノミのヴァージョンを
挙げていたりもするようである。
さて、今回表題に取り上げた
Total Eclipseとは皆既日食の意。
あたかも異界からの
来訪者といった雰囲気を、
終始演出していた
この人らしいかなと思って
このチョイスにした次第。
彼らのオリジナルだと思われるし、
後年自国のバンドに
カヴァーされてもいるようだから、
たぶん代表曲といっていいと思う。
なお、一応こちらは
バンド・サウンドのトラックである。
それからこれも
結局は余談の域なのだけれども、
一時期彼のバンドには
ジャン=ミッシェル・バスキアや
あるいはキース・ヘリングなども、
名前を連ねていたことも
極短い期間ながら
あったともいうから、
存外当時のいわゆる
イースト・ヴィレッジ・シーンでは、
影響力を誇っていたのかもしれない。
いずれにせよ、
ある種仇花みたいな方であった。
まあ、80年代の
まさに開幕の時期には
こういう人もいたのである。
では恒例の締めのトリビアへと行く。
本邦にかつて
スネークマン・ショウという名前の
ユニットがあった。
やはり80年代の初頭に、
何作かアルバムを発表している。
これ、なんて説明すればいいのか
正直よくわからないのだけれど、
あたかもラジオ番組の、
それもコントを中心にして、
そのままパッケージにして
しまったような企画だった。
そして、何故だか
そのスネークマン・ショウの
最初のアルバムに
このクラウス・ノミのトラックが
一曲収録されていたりするのである。
――うーん、そうだったっけか。
いや『ごきげんいかが123』辺りは
相当喜んで聴いていたはずなんだけれど、
こちらは全然といっていいほど
記憶に残っていなかったから、
たぶんアルバムまでは
手を出さなかったんだと思う。
あるいはギャグだけ聞いてたか。
それにしても不思議なのは、
本作の制作は
時期的にノミ本人のアルバムが
ようやく出るか出ないかという
タイミングだったのでは
なかろうかと思われる点である。
少なくとも日本盤は
九分九厘まだ発売されてはいない。
そうなると、そもそもいったい誰が、
こういうものをここに
引っ張ってこようと思いついて、
どうやって実現に結びつけたのか。
今さらながらひどく
興味深かったりもするのである。
なお、これもご存知の方には
釈迦に説法のレベルなのだが、
ちなみにこの
スネークマン・ショウのアルバムには
小林克也さんと
伊武雅刀さんとが、
ノリノリで登場して
いらっしゃるので念のため。