87年のアルバム
SAVAGEからのチョイス。
Savage/Eurythmics
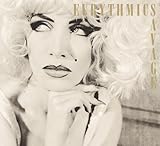
¥1,037
Amazon.co.jp
80年代の前半を通じ、
シーンを引っ張るというよりもむしろ
誰にも真似することのできない
ある種孤高の存在として、
敢然とマーケットに
君臨し続けてきたのが
このユーリズミックスである。
1984なるサントラ作品を
カタログには数えないとして、
通算六枚目の
スタジオ・アルバムに当たる
このSAVAGEは
先述の通り87年の発表だった。
81年のデビュー以来、
6年で6作だから、
ほとんど休む暇もなくと
いってしまっていいだろう。
シングル盤に至っては、
このChill in My Heartで
実に23枚目を数える。
もっとも英国のみ、
あるいは米国のみ、という
リリースも時にあった
模様ではあるのだけれど。
ちなみに、全部きちんと
十分なウラを取った訳では
決してまだないけれど、
基本これらの楽曲は
すべて二人の共作である。
それだけの数をこなしてなお、
このChill in My Heartみたいな曲が
出てきてしまうのだから、
やはりこの二人、
ソングライター・チームとしても
本当にすごかったのだと思う。
シンセサイザー/シーケンサーの
作り出す、80年代以前には
存在し得なかった種類の
斬新なリズム・パターンに、
D.ステュワートの
どこか荒々しいギターと、
A.レノックスの
ソウルフルとしか形容しようのない
エネルギッシュなヴィーカルを
載せてくるのが、
このユーリズミックスの
いわば基本的なスタイルである。
まずは81年のSweet Dreamsで
全米を席捲したこの二人は、
本編でも取り上げた
Here Comes the Rain Again(♯26)や
Right by Your Side(♭36)などを
勢いそのままに
チャートの上位へと送り込み、
その後も、ある種モータウン系の
ソウル・ミュージックにぴたりと寄せた
There must be an Angelや
あるいはロックの方向へと
ベクトルを思い切り振り切った、
Would I Lie to You?や
Sex Crime(1984)など、
とにかくほとんど間を空けずに次々と
しかも随時異なったアプローチで、
それぞれ十分な完成度を誇る、
トラックを発表し続けてきた。
これほどの振り幅の中で、
そのどれもが、ああ、やっぱり
これがユーリズミックスなんだよなあ、と
必ず感じさせてくる。
それは比肩し得るもののない、
バンド/ユニットとしての、
極めて強烈な個性だったのだと思う。
残念ながらこのSAVAGEの
次作に当たる
89年のWE TWO ARE ONEで
二人は一旦、その活動に
終止符を打ってしまうのだが、
いわば彼らの後期の傑作が、
今回のChill in My Heartであろうと
個人的にはまあ
そんなふうに考えている。
このChill in My Heart、
曲調はまず、ひどく明るい。
だがダンス・テューンかといえば
決してそうでもないのである。
テンポはそちらに近いけれど、
バラードという表現も拒む。
まったく捉えどころのない
不思議なトラックであるといっていい。
率直なところをいってしまうと、
僕自身はこの歌は実は、
ラヴ・ソングに見せかけた
讃美歌なのではないかと
まあそんな具合に把握している。
同曲のリリクスはまず、
冒頭からタイトルのフレーズを
幾度か繰り返したあと、
私を砂漠に連れて行って、という
ヒロインの懇願で本編の幕を開ける。
A Whole Heap of Nothing――
一面の砂の光景は、
ただちにこのようにいいなおされる。
何ものでもないものの、
堆く積み上げられた場所。
こういうのは、
英語でないと絶対できない
表現だよなあ、とつくづく思う。
無理矢理に無の堆積とでも
訳してしまうことは
あるいは可能なのかもしれない。
でもこの字面では、原詞の有する
荒涼とした広がりのイメージから
ややどころではなく、
離れていってしまうような気がする。
そしてこの無の砂漠と、
右手の色という言葉で、
この歌の対話の真の相手である
人ならざるものの存在を
十分に仄めかし終えたところで、
2コーラス目の冒頭から
歌はいきなり核心に入る。
愛は寺院
愛は神殿
そこらのコンビニで、
その愛ってやつを買うといい
対面型の店なら
もう少し手に入るでしょう
それでも足りなきゃ
クレジットカードを切りなさい――
シンプルな言葉が、
複雑に絡み合いながら、
少しずつテーマを
浮き彫りにし始める。
歌の後半で、
上に訳出したヴァースの
冒頭のパターンである
Love is~のフレーズを繰り返し、
かつ少しずつ意味をずらしながら
次々と畳み掛けてくる箇所は
まさに圧巻の一言である。
愛は純粋で、盲目で、
そして信仰の徴で、
私はそれを置き去りにする
愛は熱く、冷たくて
私はいつでも売り買いされて
だから愛はロックンロールで、
私はただ誰かを
抱き締めたいような
気持ちばかりに駆られていく――
なお、例によってだいぶ意訳して、
接続詞とか補っているので念のため。
ちなみにタイトルのChillとは、
寒気とか悪寒のこと。
人の胸、つまりは感情の中に、
一抹のそういう手触りの何かを
そっと置いていくことのできる存在。
この歌でYouの語が
一貫して指しているものは、
そういう存在でなければ
ならないはずである。
だからこの寒気の正体は
畏怖というやつなのだと思う。
そしてこの歌はおそらく、
アンとデイブの二人で一つの
ユーリズミックスなる存在と、
彼らをこの場所まで導いてきた
ミューズとでもいうべき存在との対話、
あるいはその彼女への
訴えかけなのだと思っている。
ま、些か小説的な解釈に
偏り過ぎていることは
自分でも認めるつもりはあるが。
さて、同曲のバッキングは
いつも通りに、というか
むしろ常にも増して、
なんというか、電気的である。
曲をリードするのは終始、
執拗なまでに加工された
ベースのラインで、
チェンバロみたいな音色の、
シンセサイザーが
その上に高音で
シンプルなパターンを載せている。
ほかに前に出てくるのは、
ヴォーカルだけだといってもいい。
それでも、鍵盤の白玉は
随所に薄く敷いてあるかなあ。
でも一方でギターは
ほとんどといっていいほど
聴こえてはこない。
鳴っているとしても
相当後ろに引っ込んでいる。
だからサウンドの構造は、
たぶんあのSweet Dreamsと
かなり似ているのだろうと思う。
その同じ手法のままで、
そのSweet Dreamsや、あるいは
Here Comes the Rain Againとは
まったく異なった手触りの、
ある種の敬虔さへと、
到達してしまうのだから、
もうただただすごいとしか
言葉が出てこない。
そしてそれを決定づけているのは、
やはりアニー・レノックスの
類稀なる声なのである。
随所に挟み込まれるスキャットが
極めていい味を出しているし、
いわゆるAメロのバッキングの、
クリシェの使い方なんかも
相当にカッコいい。
是非Must be an Angelだけでなく
こちらの方も、色々な場面で
耳にする機会があるといいのに、などと
思わず考えてしまう
今日この頃だったりする。