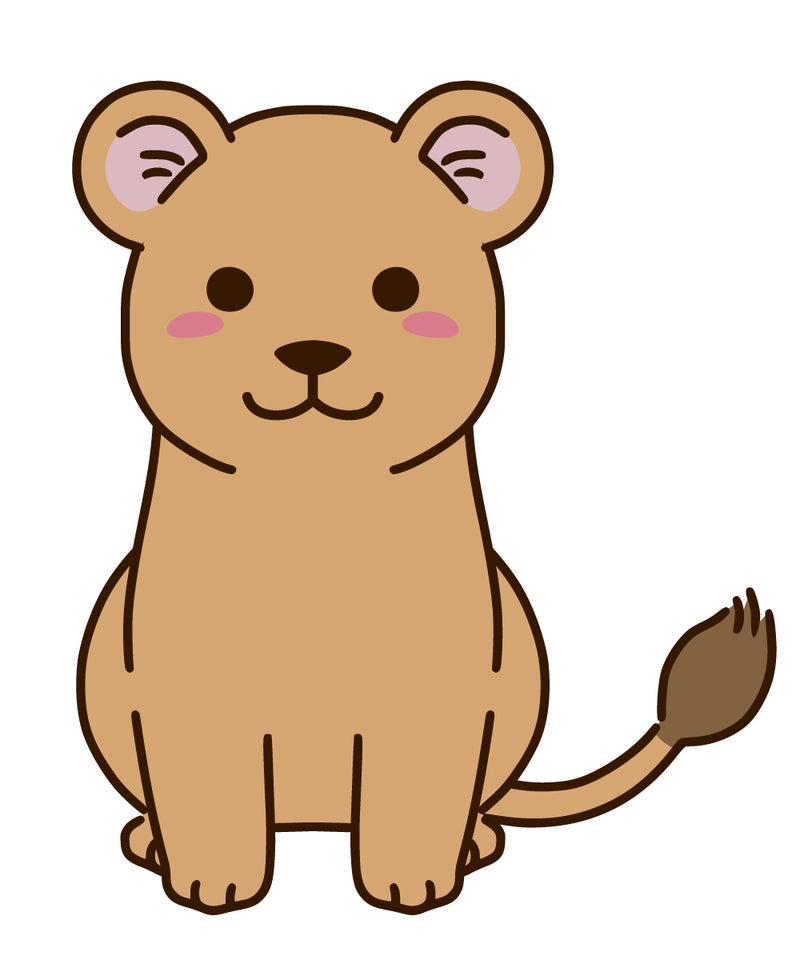「おおきなかぶ」
という、有名なロシアの民話があります。
あらすじは、
「おじいさんが植えた「かぶ」が大きく育ち、おじいさんだけでは抜けなくなって、みんなで力を合わせて引っこ抜く」
・・というものです。
この「かぶ」は、頭蓋骨の比喩的な表現な気がしています。
(凝り固まった思考を抜くというか・・?)
(ハロウィンのランタンも、元はかぼちゃではなく「白いかぶ」で、頭蓋骨を表現していました)
ちなみに、こんなドンピシャな風刺画がありました (^。^)
皇帝の首だそうです(Wikipediaより)
・・今回はそのことは置いといて。^ ^
物語の終盤に参加した「猫とネズミ」について・・
最後にネズミが加わって「かぶ」は抜けます。
「猫とネズミ」
「根っこ(ネコ)」と「根に住み(ネズミ)、根をかじる者」
「 永遠のライバル」
永遠の追いかけっこ、永遠につかまらない。
くっつかないことの比喩。
「➕極」と「➖極」 or 「S極」と「N極」だから、
接触しないよう、常に間をあけている・・?
くっついてしまうと、大きな力が発生してしまうから?
おおきなかぶの場合を考えると、最後に「猫とネズミ」が加わったことで大きな力が生まれ、かぶが抜けたといえたりして?(・∀・)
・・おおきなかぶの物語、実はそんな「猫とネズミの関係」を表している・・??
・・なんだかそんなふうに、思えちゃうのでした・・(^。^)