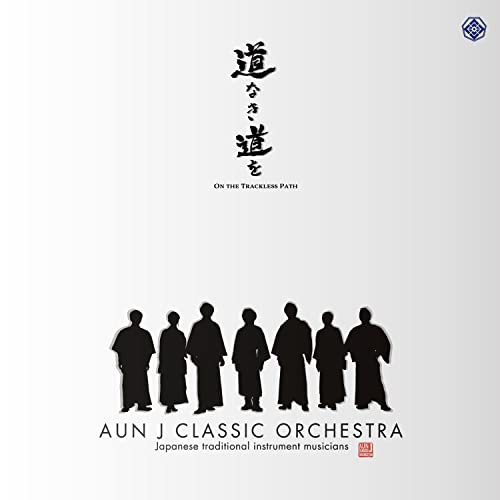前回の記事で「奴(やっこ)」について触れました。
↓
「奴(やっこ)」とは、江戸時代の、 武家奉公人の中でも低い身分(奴隷階級)のことを言います。
「奴(やっこ)」って、「奴隷」のことなんだ・・ ( ゚д゚)
・・と思いましたが、「奴隷」という字には「奴」が入っていますよね! (今気付いた! (・Д・))
・・そんなことが気になって、「奴」について、少し調べてみました・・
奴は、大名行列の際には「槍持奴(やりもちやっこ)」として、「毛槍(けやり)」や「挟み箱(はさみばこ)」を持ち、先頭を歩くこともあったそうです。
※ 挟み箱(はさみばこ)= 日用品を入れて棒を通した箱
「槍持奴(やりもちやっこ)」
「槍持奴」が振りながら歩くのが「毛槍(けやり)」です。
「毛槍」とは、先端に鳥の羽毛の飾りをつけた槍のことです。
もともとは「鉾(ほこ)」で、これを振り疫病を集め、羽毛の槍で祓ったとされています。
国入りなどの際には、くるくると毛槍を回して勢いよく投げる「毛槍の投げ渡し」が行われました。
「槍振り(やりふり)」「奴振り(やっこふり)」
そして、その「槍持奴」がモデルの「奴凧(やっこだこ)」
(奴の象徴「釘抜き紋」が描かれています)
「凧揚げ」は、凧を糸で操って空に飛ばしますね。
(昔は「タコあげ」ではなく「イカあげ」だったそうです!)
この、操られている というところが奴隷?っぽい気がします ^_^;
自分で飛んでいるつもりでも、実は糸で操作されている・・?
こういうところが、最近よく考える、ゲームの「アバター」と似ている気がして・・ ^_^;
(アバターの場合は、見えない糸、無線!! (・Д・))
アバターについてはこちら
↓
この「奴凧(やっこだこ)」の由来は、身分の低い奴が、高く上がって大名屋敷などを見下ろすという、身分の高い者に対するささやかな仕返し、という意味だったそうです。
凧のように高く舞い上がり、操られている糸を切って自由になりたい、という奴の願望にも思えますよね! ( ゚д゚)
そして、奴の象徴と言える「釘抜き紋」
打ち込まれている釘を抜けば、囚われから解放されて、奴隷から自由になれる・・ということを表現しているのかもしれません・・ ?^ ^