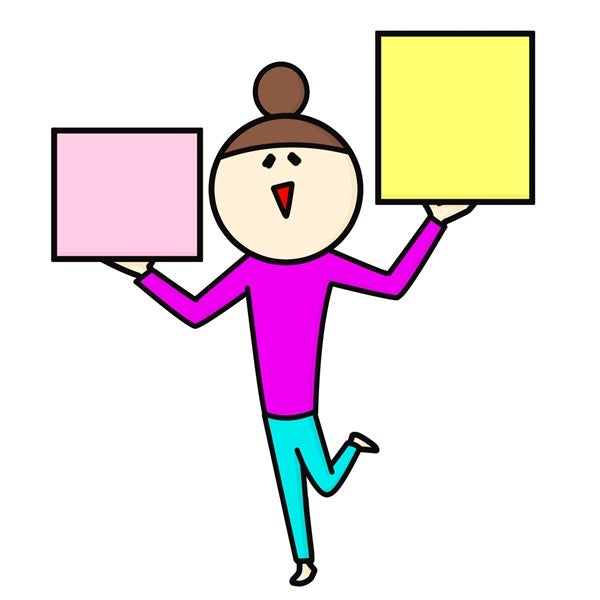前回、「数学的話し方」をすすめる深沢真太郎氏の本を紹介した。
客観的な数字を用いた比較や、モデルを使いながら、「数学的」に話すことで、説得力のある説明ができるようになる。
筆者の深沢氏はそう言いながら、一方でこうも言っている:
「結局のところ、説得力のある話とは正しそうな話のことです」
正しいことを証明する「数学」に対して、「数学的」とは、「正しそうに説明する」こと。
「正しそうな説明をする」ことと、「正しいことを証明する」ことは別物だ。
「正しそうな説明をする」ために、著者は「比較して話すことが大事」とも言っているが、その大原則として、「自分がしたい意味づけができる比較を選ぶ」ことが必要と言っている。
裏返せば、うまい話し方をする人は、自分に都合がよい比較ができる対象を選んでいるということであり、都合が悪い比較は避けている可能性もあるということでもある。
話を聞かされる立場からすると、「正しそうな説明」をうかうか信じてはいけない、ということにもなる。
前置きが長くなってしまったが、今回取り上げる本:「客観性の落とし穴」は、数字と客観性が支配する世界に警鐘を鳴らす本だ。
だが、「客観的で、いかにも正しそうな話に騙されないよう気をつけよう」という単純な内容ではなく、もっと深く、根源的な問題を扱っている。
筆者(村上先生)が大学で行っている授業で、ある日
「先生の言っていることには客観的な妥当性はあるのですか?」
という質問を学生から受けた。
それが、本書を書いたきっかけにもなっているという。
学生の質問の背景には、客観性や数値化されたエビデンスのない議論は、世の中で価値が認められないのではないか、そして、そんな授業や学問は役に立たないのではないかという疑問があるのではないだろうか。
その質問をした学生は、きっと真面目な性格の持ち主なのだろう。
だからこそ、筆者も深く考えさせられずにはいられなかった。
著者が長年にわたって取り組んできている仕事は、家庭に困難を抱えていたり、不登校になっている子どもたち、また子育て支援の援助職の人たち、看護師たちへのインタビュー、そして心のケアの実践活動である。
心の問題を客観的に捉え、数値化しようとすると、その過程でこぼれ落ちてしまうものがある。
それは、一人ひとりの心の中の経験であり、それは「数学的」に表現することが難しいとしても、確かに存在する、無視できない事実なのだ。
数値によって測定されたことや、客観的な事実しか信じないという価値観にとらわれてしまっていると、個人の心の中の経験がかえりみられなくなってしまう。
本書の主旨は、世の中を支配する、客観性への信仰に対する問題提起である。
確かに、数字にもとづく客観的なエビデンスはさまざまな意味で有効だし、むしろ、客観的な根拠のない主張がまかり通ることの方がよほど危険だ。
だが、客観的なエビデンスを重視する姿勢は、実は近代以降の傾向であって、人間が古来そうした考え方をしてきたのではない。
なぜ近代人が客観性を重視する価値観に行きついたのか。
18世紀後半の西欧社会で起こった啓蒙思想では、もはや真理を保証してくれる存在は神ではなく、人間自身が自然の中に真理を見出す必要があった。
真理を自然の中に見出そうとする自然科学は、機械を用いた測定や法則性・構造の存在の追求を重視する。
自然科学が進展する中で、自然が客観化されていく歴史に続いて、次には人間とは切り離せない社会を客観的に分析しようとする社会学が19世紀に生まれ、さらに20世紀になると、人間の心を客観的なデータとして研究する、行動主義心理学が登場する。
このように、あらゆるものを客観的に捉えようとする動きが、自然科学だけでなく、人文学や心理学の世界にまで広がってきたという歴史がある。
19世紀の初め頃には新語であったらしい「客観性」という言葉が、その後どのように日常生活にまで広がってきたかについての筆者の解説は興味深い。
ビッグデータをAIが分析し、統計の結果によって評価が決定される社会。
その流れは変えられないし、数字と客観的な根拠を見極め、それをうまく使っていかなければいけない。
けれども、そうした社会の中で、いつの間にか、数字と客観性を絶対視してしまい、数値化できないものの価値を忘れてしまっていないか。
知らず知らず、目に見えないバイアスに閉じ込められてしまってはいないだろうか。
そうした自省を促してくれる一冊であると思う。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~
今日もお読みいただき、ありがとうございました。
※当ブログ記事には、なのなのなさんとPoosanさんのイラスト素材が illust ACを通じて提供されています。