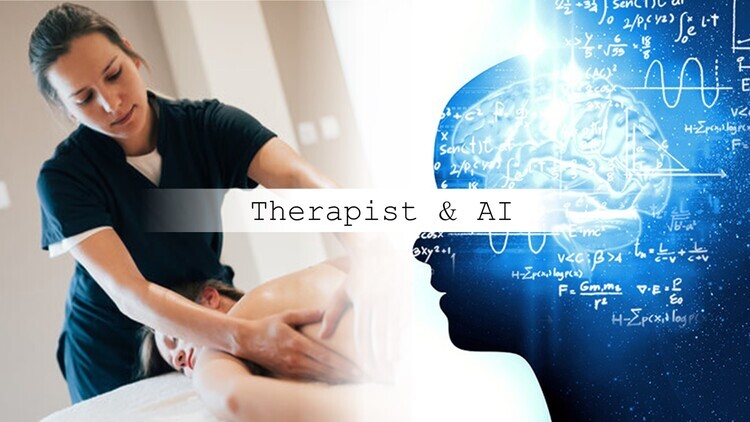年が明けて2週間が経過しました。今年は🐴午年、スクールも7日から授業が始まり2026年もよいスタートがきれたと思います。馬のように駆け抜ける年になりそうです。
私個人の今年のキーワードは、
「機会」と「構造」です。
「機会」
チームメンバーのチャレンジの機会(成長機会)をより多く創出すること。
会社員時代を振り返ってみると、勤めていた会社には、多くのチャレンジの機会をいただいていたと思います。その度にトライ&エラーによって学び、成果を出すことで自信をつけることができ、社員として成長実感を得ながら仕事をさせてもらうことができました。また組織への帰属意識を持つことができたと思います。
自分が逆に雇用する立場になってみて、社員/チームメンバーが挑戦できる機会を創ることは強い組織を創るうえでマストである、と改めて実感しています(挑戦してトライ&エラーをするなかで経験を積み成長する。ビジネスパーソンとして高いレベルの仕事ができるようになる。胆力も養われる。そして、そういった人材が会社を支える存在になる。)
創業して暫くは機会を創出する余裕は全くありませんでしたが、少しずつ会社が前進するなかで、近年やっとこういったことを考え実行する余力が出てきたところです。
チームメンバーの成長とともに会社が成長する。これを実現できるようにするために、成長に不可欠な「チャレンジができる場」をより多く創出していくことを大切にしていきます。
「構造」
持続可能な組織構造をつくること。
麻布十番の小さな一室/ベッド一台からスタートしたTRTAは、気がつけば今年で14年目になります。
創業時から、現場レベルでは、目の前のお客様に誠実に向き合うこと、コツコツ積み上げることを大切に、そして事業レベルでは(特に法人化した2016年から)、ブランドを育てることを大切にしてきました。
初めは個人事業でスタートしましたが、将来的に組織にすることを想定していました(故に、個人事業レベルで正解だけど、法人組織レベルでは適さない取り組みはしないできました)。
今年はオーストラリア事業というチャレンジを中心に様々な取り組みを行うことで、メンバーと組織の成長を実現させ、好循環を持続できる構造づくりに注力にしていきます。