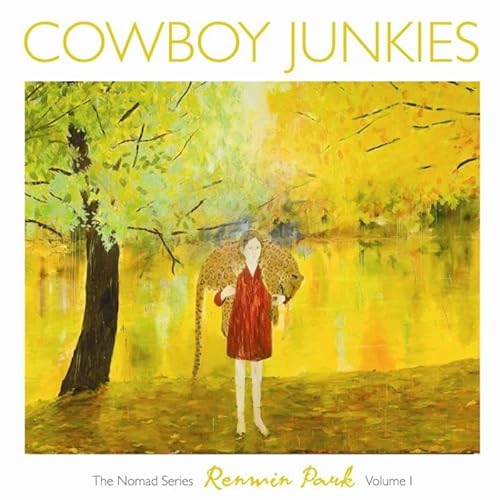知的な絞首人たち
1977年にレコードデビューしたストラングラーズはパンクロックのオリジネーターの一つだが、マルコム・マクラレン的なファッション重視の若いスタイルとは違って、近寄るとヤバそうな大人たちという感じのバンドだった。
サウンドもパブロック由来な感じがしない、ギターよりもキーボードとベースが目立つ部分が特徴で、いま聞くとドアーズのレイ・マンザレクと、ニューオーダーのピーター・フックが一緒に演奏しているような印象を受けるかもしれない。
1979年の最初の日本公演では、大人しい客に怒って「Something Better Change」を3回繰り返して演奏したらしい。最初は気が付かなかった客が、だんだんザワザワして不穏な空気になったようなことが音楽雑誌に書いてあったことを覚えている。
その歌詞にはこんなフレーズが入っている、「何かが起きていて、それはいま起きていることなんだぜ」、「お前は盲目すぎてそれを見ていない」。
初期のストラングラーズは、「No More Heroes/ヒーローはもういらない」というとてもパンクロック的なメッセージを出していたように、政治的で知的なバンドでもあった。
「No More Heroes」では、ロシア革命家のトロツキー、コメディアンのレニー・ブルース、贋作画家のエルミア・デ・ホーリー、ドン・キホーテの従者のサンチョ・パンサなど、悲惨な情況に陥ったヒーローたちを並べながらこう歌っている。
ヒーローたちに一体何が起こったんだ?
もうヒーローなんて二度と必要ない
No More Heroes & Something Better Change
最初の4枚のアルバムは、独得のシンプルかつ攻撃的でありながらどこか聞きやすいサウンドだったのだが、4枚目の『レイブン』あたりからポップな部分に加えてダークな部分も強まってきた。
このアルバムはリアルタイムで買ったので思い入れがある。パンクロックからはどこか離れているとも感じたが、ジャケットの一部が3Dのミラーになっていたことも、小遣いを溜めて買った立場としてはコレクター心が満足して嬉しかった笑。
このアルバムの中に「Meninblack」という変な曲が入っていた。頭のいかれた妖精のようなエフェクトをかけまくった声に不安を煽るスローなバックが付いた曲で、何だこれ?と強く思いながらも案外嫌いではなかった。
その変な曲のタイトルが5枚目のアルバム名についていた。大丈夫か?と思いながら聞いたそのアルバムは、キリスト教批判やオカルトっぽい感じのトータルアルバムで全然大丈夫じゃなかった笑。
特に日本ではこのアルバムで人気が急降下して、2度と戻ることはなかったそうだ。
中でも、1曲目の「Waltzinblack」は邪悪でユーモラスなインスト曲?で、初めて聞いたときはそのイカレ具合に衝撃を受けた(でも何回も聞いているうちに大好きになった)。
当時、周りのロックに関心がない友人に無理やり聞かせまくって、大変に嫌がられたことを懐かしく思い出すな。
Waltzinblack
その次のアルバムあたりから音楽性はかなり変わった。オリジナル・パンクのラジカルな部分はほぼ無くなり、内向的な感覚とヨーロッパ色が強まり、聞きやすくもなった。
1983年にリリースされた7枚目の『Feline』は、とても好きなアルバムだった。その中の、ヒューが歌う「Midnight Summer Dream」とジャンが歌う「European Female」は、ライブでよくメドレーで演奏されていたようだ。
ヒュー・コーンウェルとジャン・ジャック・バーネルには、どこかスタイリッシュで伝統的な歌手みたいな部分があり、それはモリッシーにも似た印象を受ける。ただ全員が嫌がるかもしれない。
ある良い日に目覚めた
そして世界は素晴らしかった
真夜中の夏の夢が、俺を魔法にかけた
Midnight Summer Dream & European Female
ストラングラーズはジャン・ジャック・バーネルを中心に現在も続いているが、ギターのヒュー・コーンウェルは「やり尽くした」という理由で1990年の10枚目のアルバムの後に脱退している。
2020年代に入ってから、オリジナルメンバーのデイヴ・グリーンフィールド(キーボード)とジェット・ブラック(ドラム)が続けて亡くなったことは、パンクロックムーブメントからの長い時間を自分自身のこととして感じさせるニュースだった(単に自分が歳をとったというだけの話)。
ストラングラーズは、自分の信念で変わり続け、一方で変わることなく続いてきた。オリジナルメンバーの4人は全員が人相は悪かったが、大した奴らだったと思う。
俺が犯した最悪の罪はロックンロールを演奏したことさ
だけど金にはならないぜ、自分自身をグリップするんだな
Get A Grip On Yourself