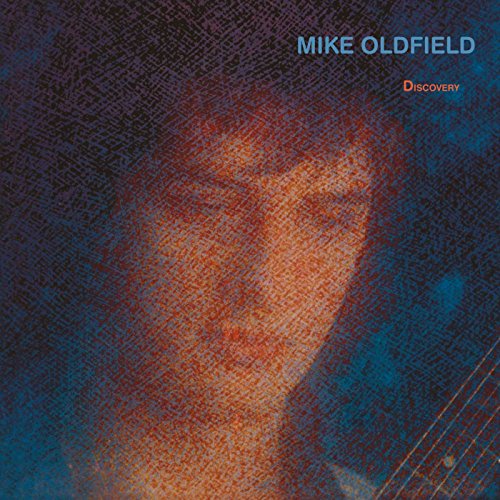ペイズリー・アンダーグラウンドの妹たち
ザ・バングルズは、1981年にロサンゼルスで結成された女性4人組のバンドで、1980年代に何曲も大ヒットを出した。
ギターのスザンナ・ホフスとヴィッキー・ピーターソン、ドラムのデビー・ピーターソン、ベースのアネット・ジリンスカスというメンバーで、1982年に5曲入りのEPでデビューしている。
The Real World
バングルズのサウンドは、パンクを経由した1960年代のポップなガレージロックという感じで、演奏はちょっとアレだがコーラスが得意で、聞いていて最高に楽しい。
それまでなかった自然体な女子のバンドという雰囲気は、同じ1981年に結成された少年ナイフにもどこか近いところがあるかもしれない。
1983年にはベースがマイケル・スティールに変わり、1984年にファーストアルバムをリリースした。マイケル・スティールは、何とザ・ランナウェイズの設立メンバーだったそうだ。
この頃のロスアンゼルスには、ペイズリー・アンダーグラウンドと名称を付けられた仲のいい音楽シーンがあった。
そこには、ドリーム・シンジゲート、スリー・オクロック、レイン・パレードなど、どこかアマチュアっぽさを残した、シンプルでちょっとサイケデリックな感じのバンドが集まっていて、バングルズはその中で最も売れたバンドになった。
Let It Go
当時ペイズリー・アンダーグラウンドに影響を受けたらしいプリンスは、ファーストアルバムを聞いてスザンナ・ホフスの大ファンになり(ストーカーになったという噂もあった笑)、「Manic Monday」という曲をプレゼントする。
そして1986年にリリースされたサードアルバムが大ヒットして、バングルズはあっというまにスターになる。
彼女たちは曲も自分たちでつくるが、このアルバムでバンドメンバー以外が書いた4曲「Manic Monday」、「September Girls」、「If She Knew What She Wants」、「Walk Like an Egyptian」は名曲ばかりだった。
バングルズが大スターになったのは、この4曲があったからだと思う。ただ、本来のシンプルなガレージバンドとのイメージの乖離もそこら辺から始まってしまったような気もする。
WALK LIKE AN EGYPTIAN
このアルバムでは、当時は忘れられた存在だったビッグスターのポップスタイルの曲「September Girls」を取り上げている。
それがアレックス・チルトンの再評価につながったことは、ちょうど同じ時期にビッグスターのダークサイドを取り上げたディス・モータル・コイルと同様に、彼女たちの功績のひとつだと思う。
September Girls
1988年のサードアルバムは、カバーなしで全曲をメンバーが書いている。それぞれ普通に良い曲だが、彼女たちはすごい名曲を書くタイプではない。
ただスザンナの書いた曲の共作者は有名なソングライターチームで、その1曲はバラードのすごい名曲になり、世界中で特大ヒットした。
しかしプロデューサーや外部の奴に、もとはシンプルなバンドをいろいろいじられたこと、とても目を引くスザンナばかりがピックアップされたりしたことなどから、バンドの人間関係が悪くなってここで一度解散してまった。
曲作りもボーカルも4人で分け合い、ほとんどの曲では4人でコーラスも付けていたバンドだったので、そのバランスが壊れたのは致命的だったんだろう。
バングルズは1998年に映画のサウンドトラックを制作したことをきっかけに再結成した。そして、これまでに2枚のアルバムをリリースしている。
バングルズにはポップバンドとしての一面とガレージロックバンドとしての一面があり、その両面ともとても良いし、いつだって楽しそうに演奏しているところは最高だと思う。
あとプリンスと同じ意見になってしまうけど笑、スザンナの声とキャラクターはとても魅力的だ。背が小さくて気が強そうだが、バンドの中で一人目立つことを嫌がっているようにも見える。多分普通に良い人なんだろう。
この映像は2000年の再結成後にアコースティック・バージョンで演奏された「Manic Monday」。みんな良い感じに年齢を経ていて、素晴らしい。
Manic Monday
現在のバングルズは、2005年にベースのマイケル・スティールが抜け、オリジナルのベーシストだったアネット・ジリンスカスが再加入している。
元気いっぱいだった女の子たちが、いろいろなことがありながらも相変わらずフェミニンな感じを失わずに、子育ても終えた大人の女性になって同じ仲間とバンドを続けている。
そんな彼女たちの2019年の「Hazy Shade of Winter」なんかを見ると、ちょっと感動するな。
Hazy Shade of Winter
少年ナイフ -ほんの少しだけ それで It's all right
Joan Jett & The Blackhearts -アイコンになったロッカー