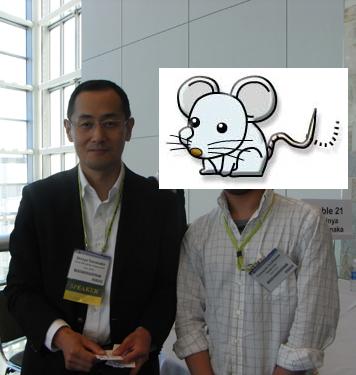再生医療が描く未来 -iPS細胞とES細胞-
京都の大学院生改め一研究員改め一大学教員が贈る、夢の未来への軌跡。 人工多能性幹細胞(iPS細胞)や胚性幹細胞(ES細胞)などの万能細胞、クローン、生殖補助医療技術 についてのトピック紹介・論文解説。
カレンダー
テーマ
ブログ内検索
ブックマーク
最新の記事
最近のコメント
月別
プロフィール
このブログのフォロワー
2008-06-09 15:00:00
ヒトiPS細胞樹立効率の改善とNILベクター使用の試み
テーマ:iPS細胞(基礎)今回紹介する論文はヒトiPS細胞樹立に関する第7報目の論文となります。
Stem Cells. 2008 May 29. [Epub ahead of print]
Improved Efficiency and Pace of Generating Induced Pluripotent Stem Cells from Human Adult and Fetal Fibroblasts.
Mali P, Ye Z, Hommond HH, Yu X, Lin J, Chen G, Zou J, Cheng L.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18511599?ordinalpos=8&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
ジョンズ・ホプキンス大学のLinzhao Chengらのグループによる報告で、山中先生の4因子(OCT3/4, SOX2, KLF4, C-MYC、SY4と記述)とJames A. Thomsonの4因子(OCT3/4, SOX2, NANOG, LIN28、JT4と記述)にSV40 large Tを加えることの影響を調べています。
また、染色体に遺伝子を挿入しないnon-integrating lentiviral(NIL)ベクターを用いたiPS細胞の樹立にも挑戦しています。
ジョンズ・ホプキンス大学がヒトiPS細胞を樹立しているらしいということは前から知られていたと思うのですが、発表は結構遅れましたね。
Chengらはまず、「ヒトiPS細胞の樹立 」でThomsonらが用いた胎児由来線維芽細胞IMR90に、SY4およびJT4に追加の遺伝子を加えたものと加えなかったものをレンチウイルスベクターを用いて導入して培養し、6日後にフィーダー細胞上へ継代、さらに1日後にヒトES細胞用の培地に交換して、14日目にアルカリフォスファターゼ(AP)を発現する細胞をカウントしました。
SY4もしくはJT4だけの場合、両者とも、20日後までにヒトES細胞様のコロニーを形成することが分かりましたが、14日目の時点では、JT4よりもSY4の方がより大きくてヒトES細胞様のコロニー形成を示す一方、明らかなアポトーシスや細胞の形質転換が見られることも分かりました。
追加の遺伝子としてH-Ras(G12V)を加えたところ、特に影響は見られませんでしたが、SV40 large Tを加えたところ、細胞増殖が促進され、APポジティブなコロニー数が、SY4では23倍(20から464に増加)、JT4ではSY4+Tよりもわずかに遅く、サイズが小さいものの、70倍(5から353に増加)増えることが分かりました。
また、TERTによって不死化した成体皮膚線維芽細胞(1087sk)を用いた場合、SY4だけでは24日以上培養してもコロニー形成は見られないのですが、SY4+Tでは14日目にAPポジティブのコロニー形成が観察されました。
他の組み合わせとして、OCT4/SOX2/NANOG(OSN)、OS、Oだけでも、Tを追加することで、14日目にAPポジティブのコロニー形成が見られた(それぞれ、153、176、117)一方、Tだけ、SOX2とTの組み合わせでは、細胞増殖の促進は見られるものの、コロニー形成が見られませんでした。
また、OSTにn-Mycを加えることで、大幅なコロニー形成の増加が見られる(176から1100に増加)ことも分かりました。
1087skを用いた場合でも、OSNL、OS、OSMの組み合わせにTを加えることで効率改善が観察されました。
次に、NILベクター(染色体への遺伝子挿入の確率は普通のレンチウイルスの1/10000)を用いて遺伝子導入することで、染色体に遺伝子を挿入しない、一時的な遺伝子発現誘導による安全なiPS細胞樹立に挑戦しています。
この場合、OSTMの組み合わせでヒトES細胞様のコロニー形成が1週間以内に見られることが分かりました。
1087skを用いた場合では、効率が悪いので、普通のレンチウイルスでSY4を導入し、さらにNILベクターでTを導入した時に、コロニー形成が見られました。(SY4+Tを普通のレンチで入れる場合よりも効率は劣ります。)
しかし、フィーダー上への継代の後に得られた5クローンを解析したところ、すべてのクローンでTの染色体への挿入が確認されてしまいました。
また、OSTMをNILベクターで導入して得られた7クローンでも、すべてのクローンでTの染色体への挿入が確認されてしまいました。
次に、最初の一連の実験で得られたコロニーを14~18日目にピックアップし、その細胞の性質を調べています。
コロニーには、AP, Oct4, Tra-1-60といった未分化マーカーを発現する典型的なヒトES細胞様のコロニー(MP2)と、フィーダー・フィーダーコンディションメディウム・FGFを必要とせず、AP, Oct4は発現するが、Tra-1-60は発現しないようなEC細胞様のコロニー(MP4)の2種類が見られました。
これらのコロニーはDNAフィンガープリンティングによりIMR900由来であることが示されましたが、MP2の核型解析を行ったところ、10回継代したものでは10%しか正常なものがなく、さらに10回継代するとすべての細胞が異常な核型を示しました。
さらに、鎌状赤血球貧血症遺伝子をもつ細胞からも、同様の手法を用いてヒトES細胞様の細胞を得ることに成功しています。
これらの研究で得られた細胞の分化能を調べるために、MP2とMP4を用いて、胚様体形成、テラトーマ形成を試みたところ、MP2では三胚葉に分化した胚様体やテラトーマが得られましたが、MP4は三胚葉分化能を示しませんでした。
という論文なんですが、少し残念な結果に終わっていますね。
SV40 large Tを用いることで確かに効率の改善はできるかもしれませんが、核型に異常が起こってしまうと、再生医療には使えません。
さらに、解析している細胞のうち、MP4など、一部の細胞は、「ヒトiPS細胞の樹立 」の4つ目の論文や、「独バイエル社ヒトiPS細胞論文詳細 」の論文で触れられているように、OCT3/4とC-MYCだけが導入されたiPS細胞になりえない細胞ではないかと見受けられます。
NILベクターを用いた実験も、結局のところ、染色体への遺伝子挿入が起こっちゃっていますし。。