
ウォン・カーウァイ監督、トニー・レオン、チャン・ツィイー、チャン・チェン出演の『グランド・マスター』。
音楽は、『南京の基督』などこれまでにも香港映画を手がけている梅林茂。
1930年代半ばの中国。南の詠春拳の宗師<グランドマスター>イップ・マン(トニー・レオン)は、故郷の佛山で他流派の宗師たちとの手合わせに勝ち、北の八卦掌の宗師ゴン・パオセンから中国武術の南北統一を任される。パオセンの娘ルオメイ(チャン・ツィイー)はイップ・マンを呼びだして、“奥義六十四手”を繰りだして彼と闘う。しかし、日中戦争は日に日に激しさを増し、やがて佛山は日本軍の占領下となる。
実在の武術家イップ・マン(葉問)の人生と、彼がかかわったやはり武術家の娘とのあいだに芽生えた「愛の夢」。
王家衛(ウォン・カーウァイ)の監督作品を観るのは、2004年の『2046』以来。
『2046』は予告篇がSF映画っぽい感じだったので観に行ったんですが、キムタクが出てたこと以外みごとなまでに内容をおぼえていません。
そのあとに撮られた『マイ・ブルーベリー・ナイツ』は未見。
ウォン・カーウァイの映画をはじめて観たのは、95年に日本で公開された『恋する惑星』でした。
その後、『天使の涙』『楽園の瑕』を劇場で鑑賞。
『いますぐ抱きしめたい』『欲望の翼』はTV放映で観ました。
ウォン・カーウァイというと、僕には岩井俊二とおなじく90年代に一世を風靡した人、というイメージがある。
『恋する惑星』は、やはり90年代に登場したタランティーノが褒めてたので脚光を浴びた部分もある。
2人以上の登場人物といくつかの場所、時間軸を交錯させた編集、しばしば映像のスピードをストップモーションのように加工したりモノローグ(独白)の多用など、そのスタイルには新鮮さをおぼえたし、感覚的につむがれているように見える物語は当時フォロワーも多かった。
僕も『恋する惑星』の、まるで日記を書くように切りとられたその映像に魅了された一人です。
この作品ではじめて見た金城武の流暢な日本語にもおどろかされたり、ショートヘアが可愛かったフェイ・ウォン、トニー・レオンの白いブリーフが妙に印象に残ってたり(^o^)
ただ、その翌年に観た『楽園の瑕』は、中国のスターたちが大勢出演していてたぶんお金もいっぱいかかってたんだろうけど、クリストファー・ドイルの撮影による癖のありすぎるキャメラワークや、とにかく登場人物たちが砂漠で酒呑んでメソメソしてたり急にポーズきめて水柱が立ったりして(このへんちょっと脳内でほかの武侠映画とチャンポンになってますが)、でもなにが描かれてるんだかよくわかんなくて困惑。
『楽園~』の舞台裏についての文章を読むと、かなり以前から撮影していたんだけどいっこうに完成しないので、おなじキャストで別の映画作っちゃったとか、ウォン・カーウァイは編集しながらお話を作っていくそうなので、どういう作品に仕上がるのか監督以外は誰もわかんなかったとか、よーするに、プロの映画監督としてはあまり褒められたものではないその制作体制が浮き彫りになってきて、なにより巨匠あつかいされて作ったような「ひとりよがり」っぽい作品にふれたことで急速に興味が薄れていったのでした。
なので、そのあとの『ブエノスアイレス』も『花様年華』も観ていません。
いま思えば『楽園の瑕』は彼の作品のなかでもかなりの異色作(制作規模も)だったのだろうし、『ブエノスアイレス』と『花様年華』の2本はけっこう評価も高かったり、特に『花様年華』が好きだという人は多いようなんですが、残念ながら一度うしなってしまったカーウァイの作品への興味は容易にはもどりませんでした。
で、それから数年後に『2046』を観て、やっぱり俺はウォン・カーウァイの映画からは90年代に卒業したんだな、と。
そんなわけで、ウォン・カーウァイという監督さんとその作品群は、僕にとっては90年代をふりかえるときにはかならず思いだされるのだけれど、すでに過去の存在になっていた。
それが今回、詠春拳の宗師イップ・マンを主人公にしたクンフー物を撮ったとかで、劇場でひさしぶりにその名前を目にしたのだった。
予告篇からの印象はなんとなく、かつて観た『英雄 HERO』や『LOVERS』みたいな映画だなぁ(今回確認するまでどっちがどういう話だったのかも忘れてたけど)、と。
どちらにもチャン・ツィイーが出てたし(いずれも監督はチャン・イーモウ。『LOVERS』の音楽は梅林茂)。
予告の「最強の流派を決める!」みたいな煽りに「あぁ、またこーゆーの撮ってんのか」と、悪いけどまるで興味をそそられなかった。
ただ、僕はけっしてチャン・ツィイーのファンというわけではないし、ウォン・カーウァイ作品とおなじく彼女の出演作はながらくごぶさただったけど、それでも以前からこの女優さんになにか魅力を感じていたのはたしかで。
僕がはじめてスクリーンで彼女の姿を見たのは『グリーン・デスティニー』だけど(おなじ年に公開された『初恋のきた道』は未見)、とにかくその身体の動き、意外な脱ぎっぷりのよさ、そしてなによりも彼女が時折見せる相手をにらみつけたり心底軽蔑するような表情に、ぞわぞわっとしている自分に気づいたのだった。
チャン・ツィイーににらまれたら、ドM男はイチコロでしょう(^o^)
スクリーンのなかの彼女には、どこか往年の映画女優のような風格がただよっている。


どんなに眉間にしわを寄せて相手をにらんでも、そのあとに見せるはかなげな表情や涙に、とてももろく壊れやすいものを感じる。
ひさしぶりに、映画館でチャン・ツィイーを見たいな、と思った。
前置きが長くてなかなか映画の感想にいきませんが、まだつづきますよ。
その前にまず、この映画をこれから観ようかと思っている人に忠告。
本篇の前には、日本の観客向けにご丁寧にも1930年代当時の中国の武術の流派についての解説があります。
まるで『レッドクリフ』のときみたいなノリで、いかにも天下一武道会みたいな血わき肉躍る迫力満点のトーナメントがくりひろげられるようにおもえるが、最初と途中に雨のなかで『マトリックス レボリューションズ』みたいな場面が、いかにも「まとめ撮り」みたいな感じでちょこっとあるだけで(武術指導は「マトリックス」シリーズとおなじユエン・ウーピン)、肝腎のイップ・マンがさまざまな流派の宗師たちと闘うシーンはじつにあっさりしてます。
なぜなら、この映画はクンフーアクション映画ではないから。
いちおうそういう場面はあるけど、たとえばドニー・イェンやジェット・リーの主演映画のような超絶的なクンフーアクションを期待すると、おそらくかなりガッカリさせられると思う。
『グリーン・デスティニー』みたいに、チャン・ツィイーがワイヤーで飛び回ったりもしない。
なので、迫力あるクンフーバトルがメインのアクション娯楽映画がお望みなら、ドニー・イェンがイップ・マンを演じた『イップ・マン 葉問』をDVDかブルーレイでごらんください。
それにしても、日本の配給会社はこの映画でねらうべき客層を完全に間違えていたとしか思えない。
むしろ、というか当然ながら、ウォン・カーウァイの作品が好きな女性客こそこの映画のメインターゲットだったのに。
あの予告篇観たら、派手な闘いを描いたアクション映画だと思った人たちが観にきて腹を立て、逆にそういうのに興味ない女性は観にこないから、結果的に誰も得をしない事態になることは目に見えてるのに。
これはほとんど予告篇詐欺でしょ。
もったいねぇなぁ。
どうでもいいけど、“Grandmaster”という単語の「グランド」と「マスター」のあいだになんでわざわざ「・ナカグロ」入れたんだろう。
ふつうに「グランドマスター」じゃなんか問題でもあったのか?
まぁいいや。
それで映画を観てみて、僕はどうだったかというと…
涙出ましたよ。
いや、父ちゃん情けなくって…じゃなくて、グッと胸にせまるものがあったから。
王家衛の映画で泣くなんて、はじめての経験かもしれない。
ただまぁ、先ほどからいってるように、すべての人におすすめできる映画ではない。
「爆睡した」という人や「ものすごく退屈だった」と不満を述べる人がいるのも、わかります。
登場人物のアップが多く、モノローグがず~っとつづく手法がまったく合わない人もいるでしょう。
それでも、この映画で描かれる“武術”というものを“人生”そのものに置き換えてみれば、普遍的な物語といえるんじゃないだろうか。
そのようなある種の「たとえ話」として観ると、映画のなかの空白の部分は自分自身の人生の断片や想像力で埋めることによって、作品がより芳醇なものになると思う。
以上のことを了解のうえで、それでも観てみたい、というかたはごらんになってみてください。
以下、ネタバレあり。
主人公のイップ・マンは裕福な家庭に生まれ育ち、「40歳まで生活の苦労を知らずに生きてきた」。
その武術の腕によって北と南の流派を統一する使命を託されるが、時代は日本軍が中国大陸に侵攻しつつあった頃であり、彼もまたそのために家財すべてと家族や多くの仲間をうしなう。
このあたりはイップ・マンのモノローグ主体で点描され、日本軍の蛮行が強調して描かれることはないが、それでもおなじ日本人として当然観ていていい気分はしない。
イップ・マンは日本軍への協力を拒んだために困窮を強いられ、幼い長女は餓死する。
たしかに戦争は天災とは違って人の手によっておこなわれるものだが、この映画では、それもまた人生における不条理なまでの苦難のひとつとして描かれているように感じられた。
どんなに武術の達人であっても、家族の命も守れないという無力感。
日本軍の兵士たちの姿は、そんな圧倒的なまでの絶望の象徴のようにおもえる。
ところで、この映画ではイップ・マンは妻と生き別れたままついに再会することはなかった、というふうに語られているんだけど、たしかドニー・イェン主演の『イップ・マン 葉問』では身重の奥さんといっしょに香港にきてなかったっけ。
あれは離ればなれになる前のことだったかな。劇場公開時以来観かえしていないので、忘れちゃった。スミマセン。
しかも『グランド・マスター』の方はしばしば劇中の時間が前後するので、1回観ただけでは僕の心許ない記憶力では物語すべてをおぼえていられなくて。
映画では一切言及されないけど、Wikipediaによればじっさいにはイップ・マンは地元で警察官をしており、またその財産を没収したのは(日本軍ではなくて)中国共産党だった、とあります。
1951年の香港辺境の封鎖によってイップ・マン夫妻が離ればなれになって、ついに再会することなく妻は60年に佛山で病死した、というのは事実らしい。
イップ・マンの息子たちはやがて香港にわたり父と合流、その仕事をサポートした。
息子の一人はイップ・マン関連の映画に出演したりアドヴァイザーとして参加しているんだそうな。
このあたり、じっさいにどこまでが事実でどのあたりがフィクションなのか僕にはくわしく確認するすべがないけれど、『イップ・マン 葉問』のストーリーの多くにフィクションがふくまれていたように、この『グランド・マスター』もまたかなりの脚色がほどこされている、と考えてよいかと思います。
ちなみにチャン・ツィイー演じるルオメイ(宮若梅)は架空の人物だそうですが、そのキャラクターにはモデルがいて施剣翹という女性。彼女はイップ・マンとは同時代の人だが、直接的にはかかわりはない。
だから、この映画でもっとも美しかった部分が、じつのところウォン・カーウァイによって作り上げられた「物語」であったのかもしれない。
手傷を負って日本軍に追われているところをルオメイによって救われた八極拳の宗師カミソリ(チャン・チェン)のエピソードもしかり。
父に勝ったイップ・マンと対戦して勝利し、やがて父を殺したマーサン(マックス・チャン)をも打ち負かした女丈夫ルオメイとは、武術の化身のような存在なのではないだろうか。
大切なことは、劇中でいく人もの登場人物たちによって語られている。
“武術”とは、自分を知ること、世間を知ること、人生を知ること。
どっかの誰かさんの「
僕は特にクンフー映画のファンじゃないけど、この映画よかったと思ったもの。
むしろ場合によっては、クンフー自体にはさほど興味がない人の方が、この映画が描いてることの本質がより伝わる、ってこともありうるんじゃないかな。
たとえば、これがダンスやスポーツ競技でも別にいいんだよね。あるいはそのほかの芸術活動などでも。
でも中国の歴史と切っても切り離せない“武術”だからこそ、それはそのまま人の“人生”にかさねることができる。
そういうことさえわかれば、クンフーの流派や技の名称とか歴史にくわしくなくたって、この映画は観る価値はあると思いますよ。
すくなくとも、この映画が好きな女性のかたがた(男性もいらっしゃるでしょうが)がみんなクンフーに興味があるわけじゃないだろうし。
ウォン・カーウァイの映画に特別思い入れがない僕でさえ、これほど肩入れしてるぐらいなんだから。
…ってゆーか、非常に瑣末な部分へのツッコミ(アクションがリアルじゃないとか、人物の描き方が表面的だとか…ってぜんぜん瑣末じゃないか^_^;)が多くて、一方でこの映画が描いてるもの、伝えてることを見逃してる、理解できてないらしい人たちがやたらといるんでこれはちょっと異議申し立てしたいな、と。
恋愛の要素が不要だとか、“カミソリ”の存在意義がわからないとか…いやいや、それこそが重要なんでしょうがっ!(>_<)
ようするに、くりかえしになるけど、この映画を観に行くべき人、好きになるはずの人たちが観に行ってないんだよ。
だから「良さがわからなかった」人たちによって、寄ってたかって「駄作」あつかいされちゃってる。
僕もこの映画を観る前に読んだある人の「これが理解できない人は感性をもっと磨いてください」みたいな感想読んで、正直イラッとしたんだよね。
なんだ、「わかる人にだけわかればいい映画」か?鼻持ちならない言い方しやがって、と。
だけど観終わったあとは、あまりに的外れな批判が多いことにその人が思わずそういわずにいられなかった気持ちがちょっとわかりました。
いや、感性がどうのこうのはどうだっていいんだが、ものすごくかまえて観に行ったせいか、僕には意外なほどわかりやすい映画だったんですよ。
基本的にはモノローグでぜんぶ説明してくれちゃってるわけだし。
そして、たしかに登場人物の顔のアップが極端に多いために画的なダイナミックさに欠ける、と感じる人もいるだろうけど、この映画ではイップ・マンやルオメイ、一線天<カミソリ>、ルオメイの父ゴン・パオセンなど、すべての登場人物たちの「顔」こそが見どころであり、俳優たちの顔がじつにみごとに捉えられていたと思います。
あの顔こそが、言葉では説明できない映画ならではの表現となっていた。
僕は個人的にチャン・ツィイーの顔を観に行ったようなものなので、うまいことハマれたのかもしれない。
この映画でのツィイーは、僕が好きなあの「にらみ顔」は見せないけれど、イップ・マンとの最後の場面で、それまでのつねにどこか張りつめたまなざしからスッと力が抜けたような表情になって涙を流すその刹那に、僕は彼女に抱きしめたくなるような愛おしさを感じたのでした(なんか、この表現ばっか使ってるけど)。
そう、この人のこういう表情を観たくて俺は劇場に足を運んだんだよ。
…すいませんね、主演のトニー・レオンをほったらかしにしてツィイーちゃんのことばかり書いてしまって。
僕は女性が大好きなおっさんなんでトニー・レオンやチャン・チェンに「うっとり」することはなくて、どうしても女優さんに目がいっちゃうんですが。
イップ・マンの妻役のソン・ヘギョもきれいな女優さんだったなぁ。


今生の別れになるかもしれないと予感していたのか、あるいは夫とルオメイとのあいだにあった「愛の夢」に気づいていたのか、彼女が家族での写真撮影のときに見せた涙が美しかった。
もちろん、トニー・レオンもチャン・チェンも、セクシーな俳優であることは僕にもわかりますよ。


チャン・チェンは僕はエドワード・ヤン監督の『牯嶺街(クーリンチェ)少年殺人事件』ではじめて見たんだけど、そのときは彼はまだ少年だったので、その後『グリーン・デスティニー』で美青年に成長していてちょっとおどろいたんですよね。ウホッ。


トニー・レオンは前述の『恋する惑星』がはじめてでした。
美男子、というわけではないのだけれど、大人の男性の色気ですよね。わかります、ハイ。
さっきも書いたように、この『グランド・マスター』は出演者の「顔」がとてもいいんですよ。
ゴン・パオセン役のワン・チンシアンも、各流派の宗師たちもみんなイイ顔している。

ウォン・カーウァイの作品がどうして女性に人気があるのか。
いつもサングラスかけてて、まるで梶原一騎か黒社会の人みたいな顔したおっさんなのに。

それは、彼が“乙女の心”をもっているから。
きっとそうなんだろうと思う。
おそらく女性がときめく瞬間の気持ちが彼には理解できるのだ。
だからおじさまたちのことだって官能的に写せるんである。
もともと脚本家出身なのに、どちらかといえばストーリーテリングではなく、感覚的に映像をコラージュしていく手法。
アートの匂い。
そこにイラッとするところもあるのだけれど、でもどこかで「いいなぁ~」と思ってる自分もいる。
イップ・マンとルオメイの手合わせには、男女が一対一でおこなうすべての行為がかさなる。
スポーツ、ゲーム、ダンス、そして…。
たがいの息遣いが伝わるほど接近した、顔と顔。
かなわぬ恋。
伝えるつもりのなかった告白。
ルオメイがイップ・マンにつぶやく最後の言葉。
「自分も世間もそれなりに知ったけれど、わたしは人生に負けてしまったのかもしれない」
アヘンの煙のなかで、ルオメイは過ぎ去りしなつかしい日々を回想している。
どこかセルジオ・レオーネの『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』をおもわせる。
そしてもう一つは、「人は完璧ではない。だからこそ進歩があるのだ」ということ。
「武術に流派などない」といっていたイップ・マンの教えは、弟子たちに伝えられた。
そのなかには、生意気そうなひとりの少年の姿もあった。

やがて世界じゅうの人々に記憶されることとなった彼の名は、ブルース・リー。
リーは、すぐれたものは認め、それを自分のなかに取り入れていった人だった。


そこには映画監督ウォン・カーウァイのメッセージも感じられる。
メンツや名声のためではなく、前に進み後ろも振りかえり、そして時がきたら退く。
ルオメイは子を作らず、その技も伝えなかったが、彼女が命を助けたカミソリは八極拳を後進に伝えた。
そして彼女がひそかに愛した男、イップ・マンは伝説になった。
1972年、イップ・マン死去。79歳。
それは弟子ブルース・リーの死のわずか数ヵ月前のことであった。
拳法のために生きるのではない。人として生きるのだ。 ブルース・リー
今回はたまたま僕の琴線に触れる要素がふくまれていただけなのかもしれない。
今後も王家衛が撮る映画をいつも楽しめる自信はない。
でも、彼の作品にはじめて出会って20年近く経ち、ウォン・カーウァイの映画のなかの俳優たちにいまも魅せられている。
いつかまた、その作品に触れる日がくるかもしれません。
関連記事
『欲望の翼』『いますぐ抱きしめたい』
『恋する惑星』『天使の涙』
『ブエノスアイレス』
『花様年華』『2046』
『ラスト、コーション』
『ドラゴン怒りの鉄拳』
『ドラゴンへの道』
グランド・マスター [DVD]/トニー・レオン,チャン・ツィイー,チャン・チェン

¥3,465
Amazon.co.jp
恋する惑星 [DVD]/トニー・レオン,フェイ・ウォン,金城武

¥3,990
Amazon.co.jp
楽園の瑕 [DVD]/レスリー・チャン,ウォン・カーウァイ,トニー・レオン

¥3,990
Amazon.co.jp
花様年華 【2枚組】 [DVD]/トニー・レオン,マギー・チャン,レベッカ・パン
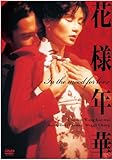
¥3,990
Amazon.co.jp
イップ・マン 葉問 [DVD]/ドニー・イェン,サモ・ハン・キンポー,ホァン・シャオミン

¥3,990
Amazon.co.jp