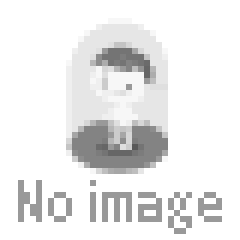南海タイムス(7月28日)によれば、クロアシアホウドリの2羽の巣立ちが確認されたそうだ。実に5シーズンぶりの朗報である。
これにより「クロアシアホウドリ最北限の繁殖地」となった。
懸念材料はカラスとドブネズミが多数いることだそうだ。また、繁殖地に不用意に人が立ち入ることも問題となる。今後も繁殖地として
栄えていくために難題を解決し環境整備を整えていく必要がある。
日本の鳥類学の第一人者・樋口広芳氏の話の要約、「今回の巣立ちはとても大きいニュースです。近い将来アホウドリが繁殖を始めるケースはよくある。島民、行政共にこのことを重要な出来事として認識しどう見守っていくかを考えること。このままうまくいけば、船で30分でいける小島は”鳥の島”として世界から注目を集めることになる。重要な観光資源です・・・・」
というわけで、八丈小島がまた脚光を浴びる日もそう遠くないとおもわれる。観光地として人が多くくれば、当然小島の昔に興味を持つに違いない。