子供たちの未来に希望を与えたい教育再生を願う本ブログを閲覧いただき、ありがとうございます。
2月27日、日本の教育正常化をめざす一般社団法人・全国教育問題協議会(中尾建三理事長)は第三回役員会を東京都千代田区永田町で開き、これまでの活動報告や今後の方針などについて来賓や顧問の方々の意見を取り入れながら多方面に活発な意見交換を行いました。
来賓として上野通子(うえのみちこ)参議院議員(自民党文部科学部会副部会長)や宮崎貞行議員立法支援センター代表、全教協顧問の小林正氏(教育評論家、元参議院議員)、杉原誠四郎・武蔵野女子大学元教授(新しい歴史教科書をつくる会前会長)、友好団体である全日本教職員連盟の岩野伸哉委員長(日本教育文化研究所長)が今後の日本の教育のあり方について、それぞれの立場から報告されました。
とくに深刻な教科書会社の不正や教科書検定のあり方の問題点を改善するために必要な教科書法案(教科用図書基本法)の制定は重要で、立法化に向けてしっかりとした準備をしていく国民的な議論へ展開できるようにしていくように決議。
歴史教育で聖徳太子の名前をあえて消していこうとする亡国左翼史観、日教組の動きに対しては警鐘を鳴らす必要があることを共通認識しました。詳細については追って紹介します。以下、会議の写真をアップします。
【できるだけ早期に教科書法案を提案する理由】
一般社団法人「全国教育問題協議会」は平成29年2月27日の第三回役員会でできるだけ早急に教科書法案の制定が必要であることを決議しました。全国教育問題協議会が教科書検定のさまざまな問題点を改革、刷新させるために教科書法案を立法化推進が必要不可欠であるとの理由は以下の通りです。
■教科書行政法の一本化
平成18年12月改正教育基本法が公布・施行されたが、旧来の教育基本法が制定されて今日まで部分改正を繰り返してきた教科書行政法を一まとめに一本化する必要があります。
■総合的な教科書行政に必要な教科書法案が廃案になったままの現状刷新
「教科書発行に関する臨時措置法」は戦後間もない昭和23年、経済の混乱、教科書用紙の不足という困窮事態に対処するための臨時措置として定められた法律で、当時と現状は大きく違うのに変わっていない。昭和31年、総合的な教科書行政のための「教科書法案」成立が図られましたが、参議院で廃案となり、現状に至っていますので、総合的な法案を立法化する必要不可欠な時期になっています。
■教科書検定規則の新たな明文化は教科書の調査・審議の透明性を確保するために必要かつ重要
教科書検定制度は本来、教科書が学習指導要領に準拠して作成されているかどうかを基準として進められてきました。昭和38年、「義務教育諸学校の教科書図書の無償措置に関する法律」が成立し、教科書の無償給付や給与措置が取られ、あわせて教科書の採択、発行が法文化されました。また、昭和33年、従来の試案だった学習指導要領が基準となって、文部大臣の公示、官報に告示されるようになり、法的拘束力を持つようになりました。教科書検定規則はこれまで省令に委ねられてきましたが、法律事項に格上げ、明文化することで検定基準とともに、教科書の調査・審議の透明性を確保する上できわめて重要な核心部分となります。
■教育委員会の職務権限と教科書採択制度の間にある矛盾解消
平成23年、中学校教科書採択をめぐっては「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が定める教育委員会の職務権限と「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」の広域採択制度との間に深刻かつ重大な矛盾を来しています。これらの事態を解決・解消し、「弥縫(びほう=失敗や欠点を一時的にとりつくろうだけの状態)的だ」と指摘・批判されている教科書行政を総合的な教科書法案として抜本的に改正・整備することが必要不可欠であり、急務です。
以上が一般社団法人・全国教育問題協議会が提案する教科書法案の策定理由です。
平成29年2月27日 一般社団法人 全国教育問題協議会 第三回役員会
☆ ~ ★ ~ ☆ ~ ★ ~ ☆ ~ ★ ~ ☆ ~ ★
【学習指導要領のパブリックコメントを送ろう!】
2月14日、文部科学省は小中学校の学習指導要領の原案を発表し、3月15日までの期間、「意見公募(パブリックコメント)」(←こちらをクリック!!)を実施します。3月末には大臣告示がなされ、小中学校の具体的な教科書編集作業が開始されます。
学習指導要領は法的な拘束力を持ち、教科書や授業内容を決める重要な指針ですので、非常に大切です。
「意見公募(パブリックコメント)」は、政府に国民の声を届ける大切な機会ですので、これからの教科書や授業内容の改善に向けて、皆様の意見を文科省にどしどし届けましょう。
次期学習指導要領では、小学校から自衛隊の災害派遣の活動を教え、領土教育、防災教育を充実させ、伝統文化の教育に力を注ぐことになりました。誇りある国づくりのための教育改革に向け、意見を出していきましょう。
【意見の送付先】
■郵送 〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2 文部科学省初等中等教育局教育課程宛て
■FAX 03-6734-4900 ※ 電話での意見提出は受け付けていません。
■パブリックコメント意見提出フォーム(←こちらをクリック)
【ご意見提出の要項】
◆意見には「件名」をつけること。件名は「小学校学習指導要領案について」、「中学校学習指導要領案について」などをつけるようにして下さい。
◆氏名、性別、年齢、職業、住所、電話番号、意見をご記入下さい。
◆締め切りは3月15日必着です。
◆インターネットの電子政府の総合窓口(e-Gov )からも意見提出できます。パブリックコメント意見提出フォーム(←こちらをクリック)
【学習指導要領の深刻な問題点と改善すべきポイント】
新学習指導要領案(歴史・公民)は教育基本法を遵守したものになっていません。意見公募(パブリックコメント)を出して日本の教育を根本から良くしていくようにしたい気持ちがある方々は、ぜひ、改善に向けて文科省を厳しく指導して日本の教育が良くなる大きな枠組みとなりますように願います。
2月16日に公表された新しい中学校学習指導要領改定案(歴史的分野・公民的分野)について3月15日までパブリックコメントが求められています。
■歴史的分野では、古代史においてこれまで「大和朝廷」と表記されていたところが「大和政権(大和朝廷)」となり、聖徳太子の正規の呼称「厩戸王(うまやどのおう)」とするよう変えられました。
■公民的分野では、家族の規定が欠如し、また、教育基本法で2度にわたって強調している「公共の精神」についての規定がありません。
教育基本法をないがしろにしたもので、教育基本法の精神に基づいて改善に向けて厳しいご意見を一人ひとりの国民の声として発信していきましょう。
(1)歴史的分野で「大和朝廷」を「大和政権(大和朝廷)」に変更し、聖徳太子の正規の呼称を「厩戸王(うまやどのおう)」にすることについて
歴史的分野でこれまで「大和朝廷による統一」と表記してあるところを「大和政権(大和朝廷)の成立」と変更しています。古代に誕生した初めての統一王朝である大和朝廷が今日まで続き、その下にある今日の日本を顧みた時、歴史教育としてこのような突き放した表記は行うべきでありません。
また、これまで「聖徳太子」と表記してところを「厩戸王(うまやどのおう)」を正規の呼称にするように変更しています。聖徳太子は冠位十二階や十七条憲法を定め、中国大陸との外交では「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す」と、わが国の誇るべき外交を行いました。
その顕著な業績に基づいて、後世「聖徳太子」と呼称し、国民にその業績を教えてきました。これは歴史学会ではすでに完全に否定されている「聖徳太子虚構説」(聖徳太子という人物は実在しなかったという説)の影響に基づくものと思われます。この虚構説の影響で、近年、中学校の歴史教科書では、呼称も「厩戸王」とし、聖徳太子の業績を低く扱う傾向が顕著に出てきていて、今回の学習指導要領の規定の変更は、その傾向を追認しようとするものと言えます。
しかし、もし、聖徳太子の呼称を「厩戸王」とするならば、他の人物名もすべて実名にすべきです。他の場合は、贈り名で呼称するよう指導しながら、聖徳太子のみ実名で記述せよというのは聖徳太子の存在と業績を否定しようとする試みにほかなりません。聖徳太子の時代、「聖徳」という美称をもって称えられる人物とその業績があったことは確かなことであり、このことを否定すれば、学習指導要領に定める歴史教育の目標である「わが国の歴史に対する愛情を深め」という文言に反し、国を愛することを定めた教育基本法に反することになります。
「大和朝廷」の表記や「聖徳太子」の呼称というこの度の変更は、日本の歴史のアイデンティティを壊そうとする意図が込められていると想定せざるを得ません。そうした意図を持ったとも言える歴史学の一部の傾向を取り入れたのかもしれませんが、日本のアイデンティティの形成のために行う歴史教育は、そうした歴史学の傾向とは無関係でなければなりません。
(2)公民的分野で「家族」と「公共の精神」に関する規定が欠如することについて現行憲法のもと、国民主権を担う公民として、持続可能な社会の形成者として「家族」と「公共の精神」に関する規定は学習指導要領の公民的分野の規定として必要不可欠
家族については、戦後、長く学習指導要領で規定されていましたが、平成20年の改定でなくなりました。健全な社会を築くためには、家族は社会の基礎単位として社会の中での位置づけを学ぶ必要があります。地蔵可能な社会を支え、今日、問題となっている少子化対策に資するためにも公民的分野で家族のことを学ぶことは欠かせません。
「公共の精神」は教育基本法において前文と第2条において2度も規定されている極めて重要な目標事項です。教育基本法が改正された直後の平成20年の学習指導要領改訂でも、この項目は公民的分野の規定として出てきませんでしたが、今回の改訂案でも欠如したままです。教育基本法が強調している「公共の精神」が最も密接に関わるはずの公民的分野で、この目標事項が規定されないのは、教育基本法を意図的にないがしろにしていると言わざるを得ません。
中学校社会科歴史的分野および公民的分野において、歴史教育の課題および公民教育の課題に悖(もと)り、教育基本法を守っていないところがありますので、教育を正常化し、未来の子どもたちのために歴史や公共の精神を養う教育の充実のために、皆様一人ひとりの声をパブリックコメントで発信して日本の教育を改善していきましょう。
文科省では3月15日までパブリックコメントを受け付けています。皆様の熱い教育への思いが具体的な行動で示されれば、是正は可能です。文部科学省も是正に向けて大きな一歩を踏み出していくことでしょう。
■パブリックコメント意見提出フォーム(←こちらをクリック)
文部科学省は2月14日、小中学校の次期学習指導要領の改定案を公表しました。
現行指導要領から授業時間数や内容の削減はせず、小学校高学年で英語を教科化。
小中を通じて言語能力の育成や読解力の強化を図り、幼稚園教育要領の改定案も示しまた。
人工知能(AI)の飛躍的な進展を念頭に、AIにはできない課題発見や正解のない問題を議論し折り合いをつける姿勢などを育むことが主軸となっています。
次期指導要領では、「生きる力」を育むため、「何を学ぶか」が中心だった指導要領の性格を大きく変え、「どのように学ぶか」「何ができるようになるか」を明記。学習内容と狙いを明確にしました。
現行指導要領の内容を維持した上、小学校での初の英語教科化や領土学習の拡充し、小中を通じた教科横断型での読解力の強化などを図るとしています。
改定の目玉となる小学校高学年での英語教科化では、国語教育との連携で日本語の特徴や良さに気付かせることを盛り込んでいます。
グローバル化した社会では、自国の歴史や伝統文化への理解が一層必要となるため、年中行事や和食・和服、和楽器などに関する指導を行うよう求め、幼稚園の学習指導要領では、文化や伝統に親しむ例として、唱歌やわらべ歌と並び「国歌」を示しました。
また、利害が衝突する世界で日本の正当な主張ができる人材を育むため、竹島(島根県隠岐の島町)と尖閣諸島(沖縄県石垣市)を「我が国の固有の領土」と初めて明記したことが当然なこととはいえ、画期的です。
現代社会の課題解決に向けては、主体的な学級活動や児童会・生徒会活動を通じた主権者教育、東京五輪・パラリンピックに関連したフェアプレー精神の理解なども盛り込みました。
★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
一般社団法人・全国教育問題協議会は平成28年10月25日、東京の自民党本部で同党の政務調査会長、組織運動本部長、団体総局長の各長に教育問題に関する要望書を提出しました。
要望書の内容は以下の通りです。
教育問題に関する要望書
自由民主党政務調査会長、組織運動本部長、団体総局長様
平成28年10月21日 一般社団法人 全国教育問題協議会 理事長 中尾建三
私たち全教協は1977年(昭和52年)結成以来、約40年間、日本の教育正常化を願う全国の民間人が結集し、活動してきました。安倍内閣が教育こそ国づくりの原点として教育の再生をめざし、取り組んでおりますが、この機にあたり、本会として下記の通り、要望をまとめました。
記
1.文教予算に関する要望
(1)既に中教審答申、教育再生実行会議第八次提言などでわが国の公財政支出に占める教育費の割合が3.5%とOECD加盟国中、最低であり、少なくとも各国平均の水準とすべきであるとの指摘がなされていますが、改善の兆しはありません。国の将来にとって教育財政の拡充強化は財政健全化とは矛盾しないとの立場から平均値である4.5から5.0%の目標の達成にご尽力いただきたい。
(2)OECD国際指導環境調査(TALIS)=2013(中学校のみ参加)によれば、一学級当たり参加国平均24人に対し、日本31人、教員の一週間の仕事時間は参加国平均33.8時間に対し、日本53.9時間と長時間労働が際立っています。その理由の一因として、学校運営業務の時間が参加国平均のほぼ2倍となっていること、一般事務に携わる時間も同様に傾向にある。このことから、教員が本来の業務である授業に専念できる体制の整備が求められます。この計画が進行しており、注目しています。
なお、平成29年度概算要求で、定数改善については平成37年度までの10年間で約3万人の定数改善を目指すとしていますが、児童生徒の自然減による教職員の定数減も同時に進行している現状から、標準法の抜本的改善の好機でもあり、30人学級実現に踏み出していただきたい。
(3)標準法の運用上の措置として、「総額裁量制」が導入されて以降、各道府県段階で「非正規教員」の割合が増加傾向にあります。安倍内閣は「働き方改革」として、長時間労働と「非正規」を死語にすると宣言しています。今や、教育現場では、この二つが同時進行しています。特に私学においては「非正規」の増加率が顕著となっています。
学校基本調査によれば、「防止法」制定以降もいじめとそれに起因する自殺も後を絶ちません。平成27年度のいじめ件数は約20万件に達し、不登校も15万件を超えています。暴力行為も5万5千件と過去最高を記録しています。
こうした学校の実態を直視し、学校に必要なあらゆる職種の担い手を配置することをためらわず実現していただきたい。
(4)学ぼうとする意欲のある全ての青少年に学ぶ機会を提供することは、より良き民主国家を形成するための国家の責務です。経済的な理由で進行の道が閉ざされることのないよう教育を受ける権利の保障の観点からも重要な課題です。いま、一方で「子供の貧困」が社会問題化しています。親の貧困が子供に受け継がれ、階層化していく、健全な社会とは言えず、教育にとっても由々しきことです。
平成29年度文科省概算要求では、大学生らを対象とした「給付型奨学金」については、具体的な制度内容が固まっていないため、「事項要求」に止まっています。
この問題は国政選挙においても争点となった事項です。私たち全教協としては、幼児教育の無償化、義務教育の完全無償化(私学を含む)とともに、返済を不要とする奨学金制度の創設を要望します。
2、教育政策に関する要望
(1)義務教育費を現行の三分の一国庫負担から全額国庫負担に制度改正し、都道府県の財政力格差が教育の質的格差とならないよう、国が義務教育に関し最終的な責任を負う体制を整えていただきたい。
(2)文科省は、教科書会社による教科書採択に関する不公正な行為が幅広く行われていたことを受けて、省令改正を行いました。これによって、教育委員会の判断で不正が発覚した場合、小・中学校の教科書の採択替えを認める制度としました。これで果たして独禁法が定める不公正取引の抑止力となり得るでしょうか。教科書汚職は歴史的に存在しました。この際、弥縫的な些末な対象ではなく、無償措置法とも一体化した新たな教科書法を制定すべきではないでしょうか。ご検討をいただきたい。
(3)本年6月以降、選挙権年齢が18歳に引き下げられ、7月執行の参議院選挙で行使されました。民法改正論議は後追いとなり、権利行使が先行しました。このことの是非とは別に現行法制は、青少年、つまり成人に達しない者について従来保護の対象としてきました。
今後、法改正が行われれば18歳未満の青少年が対象となる「青少年健全育成基本法」の制定が求められます。18歳以上が有権者となれば、なお一層、18歳未満の青少年が健全に育つことが必要になります。
そのための条件整備が基本法制定です。積極的に取り組んでいただきたい。
(4)憲法改正に関しては、臨時国会段階から憲法審議会において熟議を重ね、成案を得る努力がなされることを立法府に期待します。
当会としては次世代のためにわが国の独立と平和が保たれる保障として、第9条の改正はもとより現憲法に欠落している家族の価値・伝統文化の継承など、国のアイデンティティにかかわる条項の新設がなされることを期待しております。そのためにも、人間形成の土台となる、倫理・道徳を育む人格教育を推進していく事が最重要と思われます。
★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
「青少年健全育成基本法」を制定しよう!
【日本の現状 家庭崩壊の危機】
 ■離婚件数 26万2000組(厚生労働省2005年「人口動態統計」)
■離婚件数 26万2000組(厚生労働省2005年「人口動態統計」)
■母子家庭 122万5400世帯 28%増(5年前調査との比較)
■母子家庭のうち、未婚の出産 24万6900世帯(厚生労働省「平成15年全国母子世帯等調査結果報告」)
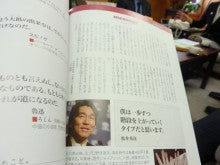 ■児童虐待相談件数 3万4451件(厚生労働省2006年「全国の児童相談所が処理した児童虐待に関連する相談件数」)
■児童虐待相談件数 3万4451件(厚生労働省2006年「全国の児童相談所が処理した児童虐待に関連する相談件数」)
■高い日本の売買春経験者(厚生労働省平成12年3月発表)
米国0.3% 英国0.6% フランス1.1% 日本13.6%
【少子化時代で非行に走る子どもたち】
平成24年刑法犯少年 6万5448人
●人口比 9.1(成人の4.3倍)
●焦点の割合 22.8%
●凶悪犯 836人(警察庁「平成24年中における少年補導及び保護の概要」参考)
■8日に1人-殺人犯少年(46人) 1日に2人-強盗犯少年(592人) 5日に1人-放火犯少年(76人) 3日に1人-強姦犯少年(122人)
【猟奇的少年殺人の背景】
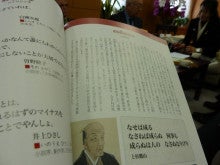 ◆「ゲームの世界のように、人を無機質に考えるような感覚だったのだろう」(佐々木光郎・静岡英和学院大学教授)
◆「ゲームの世界のように、人を無機質に考えるような感覚だったのだろう」(佐々木光郎・静岡英和学院大学教授)
◆「メディアやネットが発達し、事件の被害者数や具体的な手口の情報をすぐに知ることができ、犯罪へのハードルが低くなっている」(犯罪精神病理学が専門の影山任佐・東京工業大学教授)
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
 ◆一般社団法人・全国教育問題協議会 (全教協)は昭和52年に結成され、37年以上、要望活動、提言活動、研究活動、情報宣伝活動をしている「美しい日本人の心を育てる教育」を推進する民間人による全国組織です。
◆一般社団法人・全国教育問題協議会 (全教協)は昭和52年に結成され、37年以上、要望活動、提言活動、研究活動、情報宣伝活動をしている「美しい日本人の心を育てる教育」を推進する民間人による全国組織です。
とくに自民党の教育公約について「青少年健全育成基本法」の制定実現を核に要望しました。以下が要望内容の要旨です。
【教育問題についての要望書】
■教員の政治的中立の徹底をはかり、教員の過剰な政治活動に罰則規定を設ける
■教育長を教育委員会の責任者とし、教育委員会制度を抜本改革する
■教科書検定基準を抜本改善し、近隣諸国条項を見直す
■道徳教育の徹底を図り、道徳教育の教科化を実現する
【文教予算ならびに税制改正に関する要望書】
 ■教育への支出を未来への先行投資として文教関連予算を確保する
■教育への支出を未来への先行投資として文教関連予算を確保する
■義務教育費の全額国庫負担制度の実現
■児童・成都の学級定数の改善と教職員定数の改善
■いじめ防止対策法に関する財政措置を講じる
■新しい教科書発刊の際、見本本の配布費用は国庫負担にする
■教育・文科・スポーツ介護などのボランティア活動に対する寄付行為に対し、税控除の対象とする
■教員(公務員)への締結権を与えたり、人事院を廃止することに反対する
日本の教育再生を目指す一般社団法人・全国教育問題協議会(全教協) の活動に参加したい一般の方々、法人の方々は随時入会可能です。入会したい方はお申し込み下さい(←ここをクリック)

















