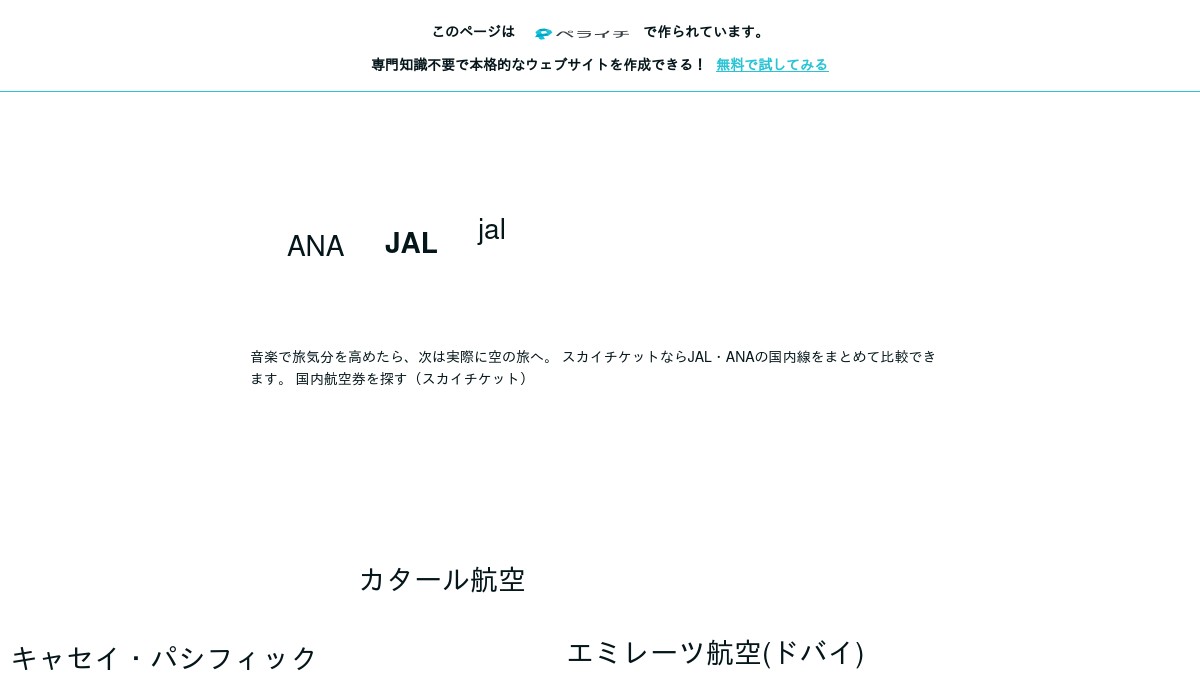なぜサウンドが仕事を彩るのか
目の前のタスクに没頭したいときも、少し気分をリセットしたいときも、音楽は最高の相棒です。 適切なBGMは思考の雑音を取り除き、視界をクリアにするフィルターとして機能します。 絵画に色が必要なように、仕事時間にも“音のタッチ”を加えてみませんか?
1. 集中を刻むインストゥルメンタル
インストゥルメンタルは歌や言葉に邪魔されず、リズムだけで脳を前進させる魔法のトラックたち。 BPMは60~80を目安に、一定のテンポが集中を後押し。
おすすめトラック
-
Casiopea「Asayake」ヒュージョンのカシオペアは知らないという人も、そのサウンドは、CMなどで、必ず、必ずと言っても良いほど、聞いたことがあるはずだ。日本では、カシオペアと、Tスクエアが二大巨頭。あの2チームは奇跡の競演もしている。あとゲームミュージックも人気ある。コナミの矩形波クラブとか。それから飛行機の搭乗音楽もすばらしい。だいたいその国を代表するミュージシャンが作曲してる。日本だと、JALはジブリの久石譲、ANAはクライズラ―カンパニーの葉加瀬太郎のアナザースカイが有名。⇒
-
Nujabes「Luv(sic) Pt.3 feat. Shing02」
-
Johann Sebastian Bach「Goldberg Variations: Aria」
-
Hiromi Uehara「Place to Be」
2. 休憩に染み渡るアンビエント&ピアノ
作業後のひと息には、ゆったりとした環境音やピアノソロを。 心拍数を緩やかに下げ、深呼吸を促す“休憩用プレイリスト”を用意しましょう。
おすすめトラック
-
Brian Eno「Music for Airports 1/1」
-
Ludovico Einaudi「Nuvole Bianche」
-
Ólafur Arnalds「Saman」
-
森のさざめき(Noisli, Rainy Mood)
3. 切り替えを演出するジャズバラード
次のセッションへのスイッチには、ジャズの温かいリフレインが最適。 リズムが穏やかでありながら、新たな気分を呼び込んでくれます。
おすすめトラック
-
Chet Baker「My Funny Valentine」
-
Bill Evans「Peace Piece」
-
Miles Davis「So What」
-
Diana Krall「The Look of Love」
4. 気分転換のエレクトロニカ&ダウンテンポ
ルーチンの合間にエレクトロニカを挟むと、刺激的なリフレッシュが可能に。 ダウンテンポなら眠気もなく、脳がシャキッと目を覚まします。
おすすめトラック
-
Tycho「Awake」
-
Bonobo「Kiara」
-
Thievery Corporation「Lebanese Blonde」
-
Emancipator「Minor Cause」
5. 音量と空間をデザインする
BGMは「背景として感じられる音量」が鉄則。 ヘッドホンなら内側の没入を、スピーカーなら周囲との一体感を演出できます。 照明やデスクの整理とセットで五感を整え、スイッチを即オンに。
6. ルーティン化がもたらす“音の記憶”
毎朝のスタート曲、昼休み前の切り替え曲、終業前のまとめ曲を決めると、 曲そのものが行動のトリガーになります。タイマー連動アプリを使えば自動化も簡単。
7. プレイリストのメンテナンス術
用途別にフォルダを分けて、「集中」「休憩」「切り替え」それぞれを即再生。 定期的に新曲を追加して鮮度をキープし、飽きずに続けられるリストを維持しましょう。
8. チームでシンクロするサウンド活用
オンライン会議前に同じプレイリストを流すだけで、一体感がグッと高まります。 ブレスト中はアンビエント、実装中はLo-fiヒップホップなど、シーンに合わせて共有を。
9. 無音の価値も忘れずに
疲労が強いときや深く考えたいときは、あえて“沈黙タイム”を設ける。 静寂は脳をリセットする最高のツールです。
仕事に彩りを添えるBGMは、自分自身のパフォーマンスを引き出す最高のキャンバス。 音の一滴が、日々の集中とリフレッシュを描き出し、あなたの仕事時間を豊かにしてくれるでしょう。 今日からワークスペースに“音のアート”を取り入れて、心地よい時間をデザインしてください。
投資って、こんなにわかりやすい
https://www.ragnet.co.jp/japanese-fusion-band-songs?disp=more
おすすめヒュージョンバンドまとめ。この記事書いた人,ものすごい知識量だ