先日ブログ記事にコメントがついているのに気がつきました。
そのコメントには、「更新しないと殺します」という脅迫文でした。
実際にはそんな物騒なものではないのですが、
ブログを更新するのにはもってこいの動機でした。
結構アルバムには捨て曲や、解説するほどのものでもない曲が多く、
面倒になって書くのを中断してしまうことが多いのです。
しかし、坂本龍一なら違います。
完成度も高く、何よりも愛着があります。
更新のための景気づけですかね。
音楽図鑑-2015 Edition-(紙ジャケット仕様)/坂本龍一
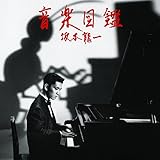
¥4,320
坂本龍一は巨大な蟻だった・・・?
坂本龍一 / 音楽図鑑
Illustrated Musical Encyclopedia
1984年作
Y.M.O.を解散ならぬ散開をして、YMOの呪縛を逃れた坂本龍一。
「ユキヒロ君も頑張っているよね。細野は死ね」
高橋さんと細野さんが82年から発足していた\ENレコードにも、
細野が嫌いという理由(注:根拠は筆者の想像)で参加せず。
代わりにMIDIレコード、そしてスクールというレーベルを創設。
同時に導入したのが、サンプラーでした。
前々からLMD-649やイミュレーターといったサンプラーを使っていましたが、
今回はフェアライトCMI。
LMDのような自作サンプラーやイミュレーターのような廉価(といっても300万)
なんかとは比べ物にならないほどの高価なもので、
これ一台だけで音楽を作ることができるほどの高性能なものでした。
本作は坂本龍一のフェアライト・アルバム第一弾です。
しかしレコーディングは82年から行われています
フェアライトを導入する以前から行われていたのです。
それで発売が84年ですから、異常なまでに長いです。
一曲につき何ヴァージョンも作ったりと気がふれたかのような偏執ぶり。
こういう長いレコーディングが失敗したパターンが
ビーチ・ボーイズの「スマイル」だったりするのですが、
教授は違いました。やりますねぇ。
曲・解説
※あまり本気に読まないでください。
1.Tibetan Dance
たとえば「ラスト・エンペラー」という曲があります。(いきなりの話脱線)
この曲を作った男は日本人初のアカデミー賞を受賞することになります。
その男こそSEKAI NO SAKAMOTOなのですが、このセカサカはかつてこんな曲も書いています。
最近では「チベットを守れ!」的な意味でこの曲を演奏をされていますが、
当時はそういう意図はなかったと思われます。
曲調を聴く限りでは、普通に「チャイニーズ・ダンス」でもまあ良い感じです。
しかし安易に「チャイナ」とかをつけると、日本と中国の違いも分からない
海外ミュージシャンみたくなってしまいます。
それだけ「チャイナ」というのは使い古された単語と言えます。
それよりかは聡明な感じのするチベタンの方が良いに決まっています。
実際そんなに中華てもチベタンでもないですよね?
演奏陣を見ると、細野晴臣、高橋幸宏、大村憲司、浜口茂外也、井上ケン一
といった名前が連なっており、モロY.M.O.関係です。
ムーンライダーズの武川さん(やたら大きい人)もいますし。
武川さんって恰好良いですよね。長身ですし。
ムーンライダーズのメンバーって顔は「別に……」って人が多いですけど、
かしぶち哲郎さんと武川さんは別格だと思っています。恰好良いです。
バンドでヴァイオリンを担当するという珍しい肩書ですし、
そればかりかギター、キーボード、トランペット、ボーカル・・・いやすごい。
「くじら」という愛称もまた良いんですよ。
彼が80年代に出した二枚のソロアルバムも、個人的にはお気に入りですよ!
さて、次の曲は「30」という曲です。
2.Etude
嘘です。「30」はムーンライダーズの曲です。
テクノ・クラシック・アホアホマンと色々なことに挑戦する教授ですが、
今回はジャズです。タイトルの通り「練習」で、
「俺にとってビル・エヴァンスはゴミ」という意図はサラサラないはずです。
どこかでこの「音楽図鑑」というアルバムが、ジャズ評論家に酷評されていた
という記述を見たことがあります。
ジャズっぽい曲がこれだけで、しかもそのタイトルが「練習」というアルバムを
酷評するというのは畑違いにもほどがあります。
しかし「ジャズ」という観点からすれば、他の曲はジャズ要素がないので、
駄作というのも確かに間違いではないでしょう。
これは「ただちに影響はない」と同義です。
私はフクシマを応援します。たかが電気ですよ!
3.Paradise Lost
頽廃的で美しい、そんな素晴らしい曲です。
2曲目までがアカデミックな作品だっただけに、これには驚かされました。
チベタンやエチュードにはY.M.O.三人が参加しているのですが、
これには細野さんも高橋さんも居ないというのもあるでしょう。
その代わり山下達郎がいます。「その代わり」で片づけられる人間じゃないだろ。
「夏だ!海だ!タツロー!だ」という合言葉がありますが、
これはちっとも夏じゃないですよね。
坂本龍一と山下達郎には関係があったというのが、あまりしっくりきません。
二人の関わりは少なくとも1976年の「ナイアガラ・トライアングル」まで
辿ることができるほど、ちょっとやそっとのものではないのですが・・・。
クレジットを見るとタツローはなんとボーカルを担当しているそうです。
最初あの声が教授の音楽に合うのかと想い聴いたのですが、
彼の声はまったく聞こえません。「ああ、ついに耳までおかしくなったか」と
絶望しかけましたが、これヴォコーダーに通して歌っているんですね。
(2016年5月29日追記)ところが、このヴォコーダーは山下氏によるものではなかったそうです。
一体どういうことなんだ!?タツローをそんな風に扱っていいと思っているのかよ!?
4.Self Portrait
「曲の良さ」においてこの曲は、本作はおろか
教授が今までに作った曲の中でも上位に挙がるものでしょう。
ここでも高橋さんのドラムが冴えています。でもリンドラムも重ねられているようです。
いつも気になるのが、この曲の演奏陣。
何度見ても「Ryuichi Sakamoto」の文字がありません。
曲を作ったのは紛れもなく彼ですが、一体演奏においては何をしたのでしょう?
ピアノ演奏すらもサンプリングしてしまったのでしょうか?
またそれ以上に謎なのが、これまた山下達郎。
彼はギターの他にボイス・サンプルなるものも担当しています。
しかしどこをどう聴いてもそれらしいものがありませんでした。
クレジットしてあるからにはどこかで使われているんだよな・・・
と思ってウィキペディアを見たら、彼のボイスサンプルは使われていない!?
ふざけるな!散々騙しやがって!!
5.旅の極北
ここからがB面です。A面はまだまだY.M.O.が残っているのですが、
ここからはガラリと変わりました。ここからがフェアライトの本領発揮です。
まずドラムの音が重くなっています。
ドラムだけでなく、クラップやメロディなど緊張感が走る曲です。
これが極北の厳しさというものなのでしょう。行くならやっぱり夏ですよ。
しかし極北なのですから、夏でも大差ないんですよね。これは旅する方が悪い。
前に9月頃に青森に行ったことがあるんですが、あれは本当に9月だったんでしょうか?
寒い。あんなのおかしいよ。皆さんも風邪ひかないように。
6.M.A.Y. In The Backyard
フェアライトありきの曲。実験的なようで、親しみもある。
さすがにオーケストラヒットに親しみはなさそうですが。
M.A.Y.ですからてっきりメイと読みたくなりますが、それだと教授はキレるそうです。
器が小さい典型例に思われるかもしれません。
しかし、このアルバムには他に「N.J.P.」という単語がつく曲があります。
これをどう読みましょうか。ンジェピー?ああ、それはキレますよ。
実はセカイノサカモトの当時の自宅の裏庭に居た野良猫についての曲で、
M=モドキ、A=アシュラ、Y=ヤナヤツという意味が隠されていたのです。
一方で、「世界の終わり」はSEKAI NO OWARI表記にした結果、
「NO WAR」と「INORI」という単語を発見したようです。???
セカオワさんもなかなかですが、セカサカさんの猫に対する命名センスもかなりのものです。
7.羽の林で
そして、ここにきて突然のボーカル路線に。嫌だ!下手!変態!
でも本気で歌っている曲じゃないので、普通に聴けますね。
大体ヴォコーダーに重ねられて歌っているので、全然破壊力はありません。
一番彼のボーカルですごいのは「SAYONARA」と思いましたが、
よく考えたら「王立宇宙軍軍歌」なるものがありました。
本作の中では一番普通の曲のように受け取りましたが、
それでもその辺のエレポップとは一線を画していてさすがです。
8.森の人
これもボーカル路線です。
これもヴォコーダーによる必死のフォローもあり、ちゃんと歌えています。
聴いているだけで森の中にいるような感覚です。
鬱蒼とした感じがあります。歌詞には深いことが書かれているようですが、
あんまり解釈とかしない人間なんで、考えたこともありません。
9.A Tribute To N.J.P.
トリビュート・トゥ・
これもジャズと言えるのではないですか?ジャズ曲はエチュードだけではなかった。
ウィキペディアによると「ジャズからは遠い」だそうです。さよか、すんません。
3/4拍子らしいですね。そういうのを意識して聴こうとすると気が狂いそうになります。
今まで考えたこともなかったですけど、これ全然テクノじゃないですね。
B面はこれで終わりです。しかし終わりません。
10.Replica
ここからはボーナスシングルになります。二枚組ってことですね。
これがまた結構長いんですね。とはいえ5分半くらいなんですけど。
ただただ繰り返しです。躍動感なんてものはありません。
盛り上がりそうでそうならないというのは、テクノポリスに通ずるものがあります。
テクノポリスとは違って、この曲は本格的なミニマルですが。
11.マ・メール・ロワ
ボーナスシングルは、あまり人々が親しみを持たないような曲が収録されています。
ボーナスだからこそのものでしょう。とは言え、完成度は高いです。
日本の音楽は西洋の真似ごととはよく言われますが、
だからといって日本の昔ながらの音楽をやっても、ポップじゃないです。
琴を弾いてJ-POPと言い張る方がどうかしていますよ。
教授はここで、あえて日本系統の音楽に挑戦するのです。
子供の声はひばり児童合唱団。子供の声といえば「ひばり」というくらい常連です。
12.きみについて
音楽図鑑は後に何度かCDとして再発されるのですが、
あるとき「音楽図鑑完全盤」というタイトルになりました。
そしてこの「きみについて」という曲が収録されることによって、
「音楽図鑑完璧盤」というタイトルにさらに変わりました。
キーボードで打つだけでもうんざりするほどの漢字の連なりですね。
これを十回書けと言われたら発狂しそうですよ。
せめて「完全盤」にしてくれよ。「璧」はきついよ「璧」は。
そんな疲れた心を癒してくれるのが「きみについて」
教授本人が「恥ずかしい」とコメントする、歌詞は糸井重里によるもの。
ムーンライダーズの名作「マニア・マニエラ」という
ヨーロッパな風格ある曲が並ぶ中、突然「花咲く乙女より穴を掘れ」という
土民のような歌詞を提供したのも彼です。
(元々そういうコンセプトだったのかもしれませんが)
曲についてですが・・・間奏が非常に長いですね。
このまま歌がなくなればいいのに。歌詞は聴いているこっちも恥ずかしいですね。
街中で脱衣するのと同じくらいかもしれません。
坂本龍一の史実に基づくなら、「きみ」は矢野顕子になりますし……。
13.Tibetan Dance (Version)
「Version」だなんて書いていますが、ようするにリミックスです。
教授本人によるものだそうですが、実際そんなに上手いとは言えません。
かといって、90年代に連発されたY.M.O.のリミックスアルバムよりかは……。
なんというか愛着があり、好感が持てます。
こんなトラックもあるのだと思わされますね。
その点ジ・オーブは「東風」のリミックスだというのにオリジナルの音ばかり使って…‥。
あれは再生コンサートの前座が失敗したから、その腹いせにも聞こえますが。
いまさらですが、話脱線しすぎじゃないですかね。