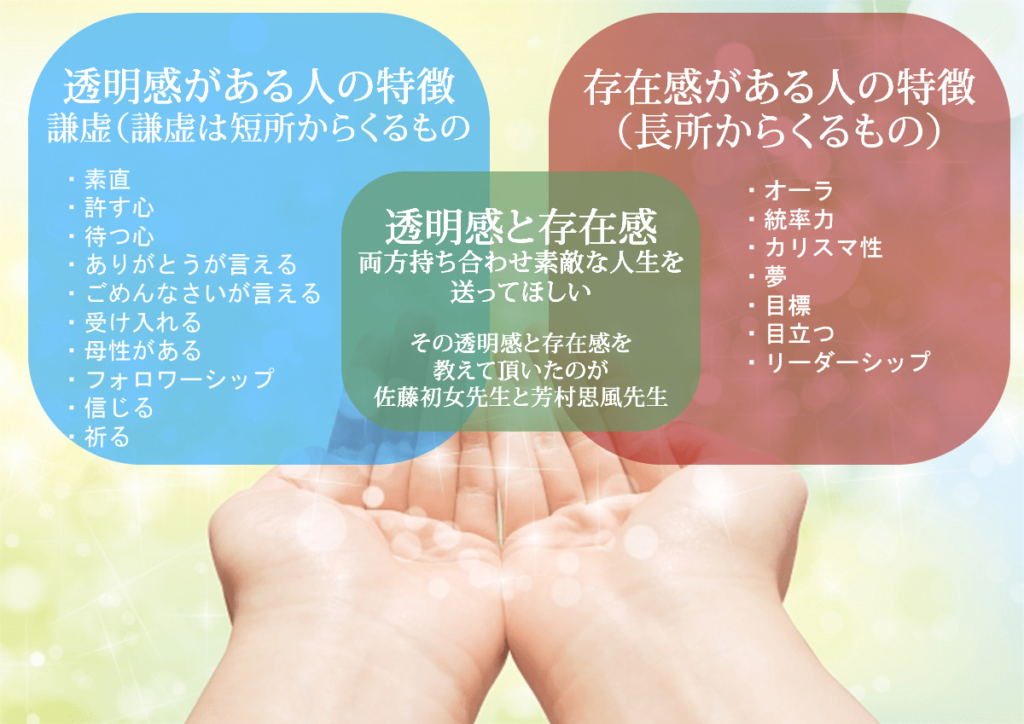東京思風塾次回8月1日(土)13:00〜でZOOM開催となります。
テーマは「人倫の崩壊の原因~愛が文化になっていない~」
先日、思風先生と関ジャニ∞メンバーの一人である大倉忠義さんが
「人生で最も影響を受けた本」として「人間の格」を紹介頂きました。

https://www.chichi.co.jp/web/yoshimura_20200522/
https://www.excite.co.jp/news/article/Wezzy_78109/?p=2
以下記事の内容から
大倉は『人間の格』を挙げ、<自分がどういう心のもちようで人生を過ごしていくと、良き人間になっていくというかさ>と、本の内容を紹介した。すると村上信五も芳村思風氏のファンだと言い出した。村上は<思風先生な。思風先生ええよな!><思風先生はこれもおすすめですよ>と、芳村思風氏と行徳哲男氏の共著『いまこそ、感性は力』(致知出版社)をカメラの前に掲げ、<これはずいぶん前のやつですけどね。哲学ってそんなに難しくないよとかっていう(本)>と紹介したのだった。
これを受けて関ジャニ∞ファンが芳村思風氏の著作に興味を示したのだろう。版元へ注文が殺到したようだ。書籍が手元に届いたというファンたちは、SNSに画像をUP。ここまでなら関ジャニ∞とファンの良い話で終わるが、前述した編集部メッセージが波紋を読ぶこととなった。
わざわざ<注文をくださったのは、これまで哲学や人生論の本とはおよそ縁のなさそうな若い女性たちでした>
関ジャニ∞というアイドルのファンで「若い」「女性」たちが、<哲学や人生論の本とはおよそ縁のなさそうな>存在だという決めつけは、当の女性たちへの侮辱にも等しく、知性を軽んじている。
何となく、ぼんやりと意識していたこと(常識)は本当にそうなのかと疑わないと!と改めておもいます。
女性でも年齢が若くてもきっかけがあれば哲学を好きになる。
むしろ、わかい世代が興味を持っても親世代が知らない、興味がないとちょっと微妙だなと。
一番いいのは、思風先生の普段の姿に触れるのがいいと思っていて
ものすごく謙虚な人柄と自分が知ってる範囲ではここ8年9年の間
人の悪口や不平不満は一度も聞いたことがなく、自分の都合で講演を休んだことも1度もなく、そして講義の中で資料を使ったことがなく(全て聞かれたことや話す内容が頭に染みついているということ)、詳しく言えないですがお金の使い方が綺麗で義理人情に溢れていて。
いわゆる言行一致を日々行われています。
それも、40年近く、80歳を手前にして。
学ぶとしたら、学問の前に同じ様にこれから40年気持ちを維持し続けながら活動していくおじいちゃんになる覚悟かなと思わせてくれます。
前回開催
テーマ「人倫の崩壊の原因~愛の理性化~」
思風先生からはこれからの時代を考えるにあたって、人倫の崩壊は民主主義社会が創り出したものという事で、民主主義社会の次に来る新しい時代を我々は考えていくべき時代に来ていると解説頂きました。
本日のテーマ「人倫の崩壊の原因~愛の理性化~」において、
人倫の崩壊というのをもたらした根本・原因は、民主主義社会の構造にあるんだということを、感性論哲学では言っている
民主主義は自由と平等を権利と考え、自由と平等こそ、人間にもって生まれた人権だという発想で、社会の法律や制度が作られてきたが、ほとんどの人は、自由と平等が大事ということを語るが、本当に自由と平等は人間にとって、人間の基本的人権、人間に生まれながらに与えられた権利と言えるのかどうか?
権利には義務があるが、義務で相手を責める。現実は義務を責める道具として使っている場合が多い。その権利を主張するということに、人間関係が破壊される原因があり、不完全な人間が心安らかに安心していける社会は、お互いに協力し合い、助け合い、許し合って生きること。感性論哲学ではそれを互敬主義社会と言っています。
権利を主張し、義務を責める道具として使った世界に愛が存在せず、愛が理性化され、愛の魂が抜かれた状態になると
自分と同じ考え方、自分と異なるひと、考え方が許せなくなってくる。
そこに対立の原因である権利の主張が生じ、対立が生じ、お互いが自由に言い争っている、暴動が起こる。
権利を主張する、自由を求めていくこと自体が時代の限界がある。
その相手との対立を解消しお互いを認め合い、愛を求める為にも民主主義からの脱却を考えるべき時代に来ているのが今の時代。
自分しか愛せない=偽物の愛。他者を愛することが愛の原理
考え方が違っても仕事・家庭が一緒にやっていける、理屈を超えた愛ある関係を作っていく
多くの人にまずは、この気づきを伝えて、考え方が違ってもやっていけることが人類の進化
確かに仰る通りだなと聞きながら、相手との接し方において常に愛を持って接していたとしても
相手が受け取る体制や状況になければ、心がつらくなってしまうという事も多いと思い、まだ自分の様に仕事、私生活で外の人と会う機会が多いのはまだいいのですが、主婦の方や例えば地方で農業されてる方など、年間でお会いする人がかなり限定されるケースも多く、家族や知人に対して対立を解消しようと思って、愛で受け入れ続けるその気力、モチベーションも必要になるな!と感じます。
なので、相手を受け入れるというのは、視点を変えると自分の能力を高めないといけないかな。。と
そこで参考になったのがこちら
相手と違う時、ずらして質問する!
自分と違う人がいる場合、相手に興味を持つためにインタビュアーになる。
思風先生からは、
「目を磨き、目を鍛え、目を育てる」
異なる価値観や考え方を持っている人と接する際に、対立が起きた瞬間に、相手をにらみつけるのではなく、「何を学び取ったらいいんだろう?」という視点を持つ。
相手を敵だと思っている目と、相手から学ぼうという目では、目の色が違い、相手の反応を見ながら、感じ取って、自分が相手に言った言葉を言い直したり、自分の相手に対する違和感を取り除き、相手にちゃんと聞いてもらえるような言い方に変えていく。
そんな、自分の人間性を作っていくことが大切
逆に嫌な目つきをしてしまう時は心の反応。
・ちょっとした目で子どもの人生をダメにしたり、希望を与えたり…目だけで出来てしまう(目ほど恐ろしいものはない)