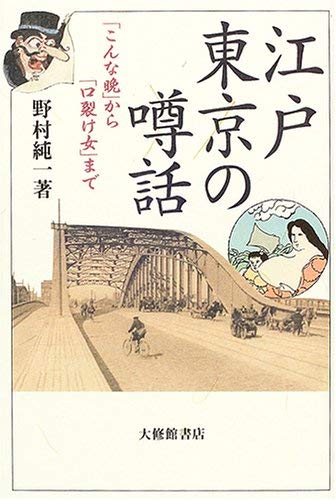「働かなくても暮らせる世界があったら」と思ったことはありませんか
現代に生きる私たちも、日々の仕事や責任に追われる中で、そうした空想にふと心を寄せる瞬間があるのではないでしょうか
実はこうした夢を本気で思い描き、ときには信じられていた時代がありました
中世からルネサンス期にかけて、ヨーロッパでは「クッカーニャ(Cuccagna)」と呼ばれる架空の楽園が語り継がれてきました
それは単なる夢物語ではなく、飢えや貧困、不平等に苦しんでいた人々が思い描いた、希望のよりどころでした
同時に、当時の厳しい社会への不満や風刺が込められた、象徴的な理想郷でもあったのです
しかし、この理想郷が現実の祭りとして叶えられた時、人間の欲望と残虐性をあぶり出す舞台へと変わってしまったのです
過酷な現実が生んだ「夢の世界」
「クッカーニャ(Cuccagna)」は、中世ヨーロッパで語られた理想郷「コッカイン(Cockaigne)」のイタリア語形です
詩や民話のなかでは、「空からパンや肉が降ってくる国」や「怠け者が至福を味わう場所」として描かれました
14世紀の詩には「ミルクと蜂蜜の川が流れる世界」といった幻想的な描写も登場し、こうした異世界のイメージは、人々の想像力を大いにかき立てました
この理想郷のイメージは、やがて現実の祭りや風習にも影響を及ぼしていきます
イタリア各地で行われた「クッカーニャ祭」では、食べ物で飾られた塔や城が建てられ、群衆がそれをよじ登って奪い合うという儀式が行われました
これらの催しは、貴族社会における権威の誇示であると同時に、民衆が理想郷を疑似的に体験する場でもあったのです
当時のヨーロッパは、飢饉がたびたび起こり、農民たちは封建領主による重税に苦しめられていました
さらに疫病や戦争、自然災害が絶えず人々の暮らしを脅かし、明日食べるものさえ手に入るかどうかわからない日々が続いていたのです
そうした厳しい日常のなかで語られたクッカーニャは、現実とは真逆の世界でした
クッカーニャ祭は「空想だけでは癒せない欲望や飢えを、せめて祭りの間だけでも味わいたい」という切実な願いのあらわれだったのです
祭りによるカタルシス
物語の中だけでなく、現実の祭りとして具現化されたクッカーニャの中で、とりわけ有名なのが「クッカーニャの木」と呼ばれる競技です
これは、長い棒の先にハムやチーズなどのごちそうを吊るし、表面を滑りやすくしたうえで、人々がそれを奪い合うようにして登るというものでした
こうした競技は、単なる娯楽にとどまるものではありませんでした
滑る棒を登って食べ物にたどり着くという構図は、当時の社会における階級上昇や報酬の獲得を象徴していたとも解釈できます
祭りの中で上下関係や制約が一時的に逆転し、庶民が主役となる空間が生まれたのです
さらに、このような祭りは権力者によって、民衆の不満を和らげる手段としても活用されました
年に一度でも「夢のような世界」を提供することで、人々の心を慰め、社会の不満を発散させる役割を果たしていたのです
こうした構造は、現代のエンターテインメントや祝祭文化とも共通点があるといえるでしょう
宮廷や都市行事における華麗な儀式
イタリア各地では、祝祭や宗教行事に合わせて、食べ物で作られた巨大な構造物が作られました
とくにナポリでは、王族や都市の上流階級が自らの富と権威を見せつけるようにして、壮大な祭りを催していました
たとえば1722年、神聖ローマ帝国エリーザベト・クリスティーネ皇后のための祝祭の際に設営されたクッカーニャでは、パン、果実、チーズ、家禽などが壁に貼り付けられ、神像の立つ巨大な土台に据えられました
1768年のフェルディナンド4世とオーストリアのマリア・カロリーナ王女の結婚祝賀では、王宮前に城塞形式のクッカーニャが設けられました
そこでは、貧民や民衆が食料を奪い合いながら競い合い、その騒ぎを上流階級が野蛮な娯楽として楽しんでいたと伝えられています
貴族が庶民を嘲笑う「地獄絵図」
しかし、このような華やかさの裏には、少なからず暴力や悲劇が伴いました
クッカーニャのためにイノシシ狩りや牛狩りが行われ、生きたままの家畜が差し出されることもあったのです
たとえば、1617年にナポリのメルカート広場で催されたクッカーニャでは、王から庶民へ豪華な食料が下賜されました
その中には生きたままの豚も含まれており、それを奪い合う群衆によって豚が引き裂かれるという凄惨な光景が広がりました
貴族たちは、その様子を愉快な見世物として眺めていたと伝えられています
さらに、豚だけでなく、アヒルや鶏、七面鳥なども生きたまま柱に釘で打ちつけられ、命を奪われながら見世物として消費されていきました
こうした残酷なエンターテイメントの犠牲になったのは、動物だけではありません
食料を奪い合う混乱のなかでは、ナイフを手にする者も現れ、争いが流血沙汰に発展することもありました
押し合う群衆の中では将棋倒しや事故が相次ぎ、死者が出ることも珍しくなかったのです
庶民は乱闘しながら食糧を奪い合い、貴族たちはその様子を見ては喜ぶという、さながら地獄絵図のような光景が繰り広げられたのでした
1764年、ナポリを襲った大飢饉の際には、クッカーニャの開放を待ちきれない群衆たちが、合図の前に突入するという事件も起きています
こうした悲惨な出来事が繰り返されるなかで、クッカーニャには徐々に厳しい制限が設けられるようになり、18世紀後半には公共行事としてのクッカーニャは廃れていきました
厳しい暮らしに追われていた庶民が、束の間の楽園を味わうことができたクッカーニャは、同時に暴力と混乱に満ちた過激なエンターテインメントでもあったと言えるでしょう
現在でもイタリアの一部地域では「クッカーニャの木」といった形で祭りの伝統が受け継がれていますが、幸いにも当時のような残虐性はもはや見られません
しかし「クッカーニャ」という概念はイタリア語の枠を超え、詩や幻想文学、地域の遊戯文化の中に今なお生き続けているのです
参考:
『Piero Camporesi, Il paese della cuccagna』
『思わず絶望する!? 知れば知るほど怖い西洋史の裏側』他
文 / 草の実堂編集部
(この記事は草の実堂の記事で作りました)
「働かなくても暮らせる世界があったら」と思ったことはありませんか
現代に生きる私たちも、日々の仕事や責任に追われる中で、そうした空想にふと心を寄せる瞬間があるのではないでしょうか
実はこうした夢を本気で思い描き、ときには信じられていた時代がありました
中世からルネサンス期にかけて、ヨーロッパでは「クッカーニャ(Cuccagna)」と呼ばれる架空の楽園が語り継がれてきました
それは単なる夢物語ではなく、飢えや貧困、不平等に苦しんでいた人々が思い描いた、希望のよりどころでした
同時に、当時の厳しい社会への不満や風刺が込められた、象徴的な理想郷でもあったのです
しかし、この理想郷が現実の祭りとして叶えられた時、人間の欲望と残虐性をあぶり出す舞台へと変わってしまったのです
過酷な現実が生んだ「夢の世界」
「クッカーニャ(Cuccagna)」は、中世ヨーロッパで語られた理想郷「コッカイン(Cockaigne)」のイタリア語形です
詩や民話のなかでは、「空からパンや肉が降ってくる国」や「怠け者が至福を味わう場所」として描かれました
14世紀の詩には「ミルクと蜂蜜の川が流れる世界」といった幻想的な描写も登場し、こうした異世界のイメージは、人々の想像力を大いにかき立てました
この理想郷のイメージは、やがて現実の祭りや風習にも影響を及ぼしていきます
イタリア各地で行われた「クッカーニャ祭」では、食べ物で飾られた塔や城が建てられ、群衆がそれをよじ登って奪い合うという儀式が行われました
これらの催しは、貴族社会における権威の誇示であると同時に、民衆が理想郷を疑似的に体験する場でもあったのです
当時のヨーロッパは、飢饉がたびたび起こり、農民たちは封建領主による重税に苦しめられていました
さらに疫病や戦争、自然災害が絶えず人々の暮らしを脅かし、明日食べるものさえ手に入るかどうかわからない日々が続いていたのです
そうした厳しい日常のなかで語られたクッカーニャは、現実とは真逆の世界でした
クッカーニャ祭は「空想だけでは癒せない欲望や飢えを、せめて祭りの間だけでも味わいたい」という切実な願いのあらわれだったのです
『西洋史で最も醜い祭り?』貴族が庶民を見世物として笑った「クッカーニャ」・・・
貧民や民衆が食料を奪い合いながら競い合い、その騒ぎを上流階級が野蛮な娯楽として楽しんでいたと伝えられています
貴族が庶民を嘲笑う「地獄絵図」
しかし、このような華やかさの裏には、少なからず暴力や悲劇が伴いました
クッカーニャのためにイノシシ狩りや牛狩りが行われ、生きたままの家畜が差し出されることもあったのです
たとえば、1617年にナポリのメルカート広場で催されたクッカーニャでは、王から庶民へ豪華な食料が下賜されました
その中には生きたままの豚も含まれており、それを奪い合う群衆によって豚が引き裂かれるという凄惨な光景が広がりました
貴族たちは、その様子を愉快な見世物として眺めていたと伝えられています
さらに、豚だけでなく、アヒルや鶏、七面鳥なども生きたまま柱に釘で打ちつけられ、命を奪われながら見世物として消費されていきました
こうした残酷なエンターテイメントの犠牲になったのは、動物だけではありません
食料を奪い合う混乱のなかでは、ナイフを手にする者も現れ、争いが流血沙汰に発展することもありました
押し合う群衆の中では将棋倒しや事故が相次ぎ、死者が出ることも珍しくなかったのです
庶民は乱闘しながら食糧を奪い合い、貴族たちはその様子を見ては喜ぶという、さながら地獄絵図のような光景が繰り広げられたのでした
1764年、ナポリを襲った大飢饉の際には、クッカーニャの開放を待ちきれない群衆たちが、合図の前に突入するという事件も起きています
こうした悲惨な出来事が繰り返されるなかで、クッカーニャには徐々に厳しい制限が設けられるようになり、18世紀後半には公共行事としてのクッカーニャは廃れていきました
厳しい暮らしに追われていた庶民が、束の間の楽園を味わうことができたクッカーニャは、同時に暴力と混乱に満ちた過激なエンターテインメントでもあったと言えるでしょう
現在でもイタリアの一部地域では「クッカーニャの木」といった形で祭りの伝統が受け継がれていますが、幸いにも当時のような残虐性はもはや見られません
しかし「クッカーニャ」という概念はイタリア語の枠を超え、詩や幻想文学、地域の遊戯文化の中に今なお生き続けているのです
とんでもなかった! あなたが知らない西洋がここにある
丁寧な解説とわかりやすい映像で大人気のYoutubeチャンネルが書籍化!
知られざるヨーロッパの真実をユーモアたっぷりにお届けします
あの有名な王族、貴族の教科書には載っていないウラの顔、実在したトンでも職業、庶民たちのおもしろブームなど、世界史が好きな人も、苦手な人も楽しめる1冊です