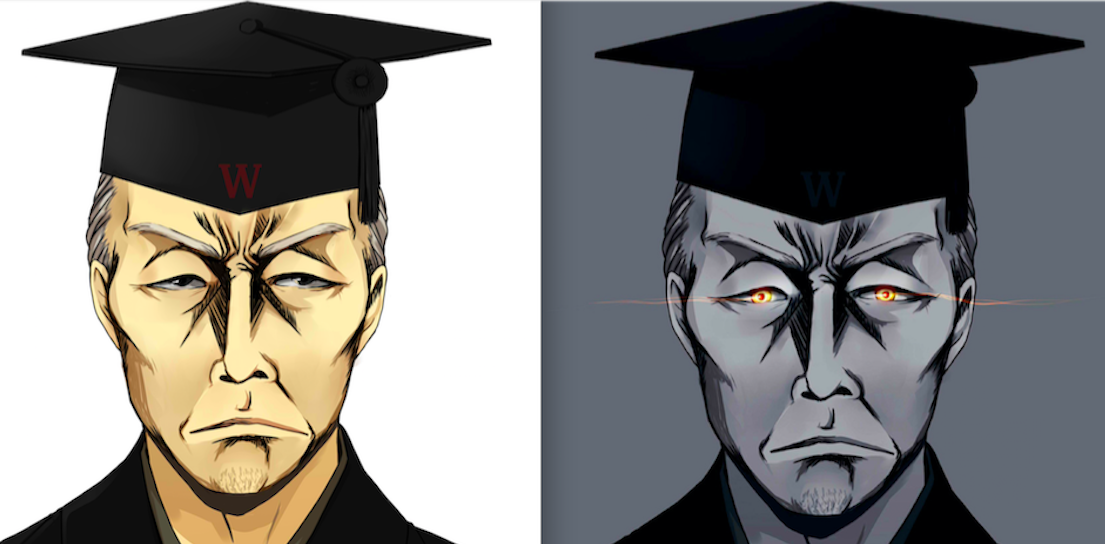この記事は受講生各位に励んでいただいている
『ポラリス レベル2』に関する記事です。
授業では受験学年の5月6月の第4回で指示を出しております。
また、各位の勉強報告の「戦術フィードバック」にて指示を出されている子もいると思います。
その使い方についてです。
①{ペースについて}
以下のどちらかで。
・1週間に2題。
・10日に3題。
これで十分です。この本は本当にむこう10年は出ないように思われる良書なので丁寧に正確に消化させていきます。
②やる順番
レッスン2から始めます。
2⇒3⇒4⇒5⇒6⇒9⇒11⇒12
まずこの順番で。
ちょっと長さに負荷が高い「LESSON1・7・8・10」の4つは後回し。
最後に7⇒8⇒10⇒1の順でやってあげてください。
③やり方
・まず自分の力で「演習時間の目安」以内でガチンコ勝負。
↓
・マルバツをつけてマーク式問題は自己訂正の後、解説熟読。
詳しくはこちらの記事
https://ameblo.jp/wasegogo/entry-12374150001.html
記述問題は解説をしっかり読んでそのうえで解答のポイントをチェック
自分の解答と模範解答の差を要チェック。特に以下が大事。
「なんでこの差が出ちゃったかな?」
「何に気づいたらこれは埋められてたかな?」
「振り返ってみてそれは現実的or無理っぽいか?」
↓
翌々日にもう1回、読み直し&解きなおしの解法再現復習。
あえて翌日は解きなおしということに関してはオフです。
人の脳の少し忘れたころにやると定着しやすいという性質を逆手にとって翌日はあえてのオフ。
でも音読だけはやりなさい。
④音読について
(1)自分の声だけでの「生音読」4回
(2)CDを使いながら目線は文章を追う「CD音読」4回
(3)シャドウイング4回(文章は見ながらで構いません)
以上計12回
::::::
さらに授業では補講も行っています。
補講では
・全体の論理構成
・文章タイプ別の読み方のコツ
・ポイントになる精読
・早稲田っぽい問題「ワセモン」を2題ほどとりあげてさらに掘り下げて解説。
ここまで1冊の問題集を味わい尽くして完成度を高めます。
総復習について
最後まで終えたらとどめの総復習です。
1日1題か、出来が良かった回であれば1日2題までならやってしまって構いません。
(1)
まずは本文を読み切ってください。
あれだけ音読したんだから速読の訓練だと思って早く正確に読み切る。
(2)
間違えた問題、△だった問題を解きなおす。
マーク式の問題に関してはできて当たり前。答えを覚えていても構わないので、プロセスも思い出してあげる。
どこで何に気づいて、その拾ったヒントをどう判断にして選択の決断を下すのか、このプロセスを。
記述問題は、初めての時よりも確実にいい答案を作ること。
これにつきます。 少しでもマルに近いいい答案を作る。これの積み重ねです。記述ができるようになっていくっていうのは、ある意味、どこか僕の授業づくりにも似ているような気がします。 少しでもいいモノを作ろうとする創作活動的な。それがひいてはマルにつながるからですね。
(3)
解説をチェック。ここまででこの1大問は完璧にしたい。
この解説チェックはスタンスとしては「だよね!」「ああ、やっぱりか」ってな具合で、自分でできたけど一応確認くらいのスタンスがちょうどいいです。逆に言えばそれくらいで再解答のパフォーマンスが出来てくれというメッセージです。 だって毎日のリバウンドとか翌々日の復習とかあれだけやらせたんだから。 ちゃんと丁寧にできてたらやれますよ。
(4)
仕上げに、生音読・音声音読・シャドウイング
この3タイプの音読を1回ずつ計3回。
ここまでやってその長文の復習はおしまいです。次の長文の復習へ。