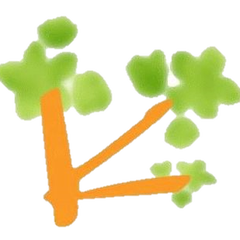過去に「PowerPoint スライドショーを記録」記事で、「記録」を使ったときに表示される「テレプロンプター」ビューという表示モードを少しだけご紹介しました。
従来、プレゼン時のサポート機能として「発表者ツール」を使うことが多いと思いますが、この「テレプロンプター」も使いやすいので、改めてご紹介します。
PowerPointで [スライドショー]-[設定]-[録画]-[先頭から]をクリック、あるいは [記録]-[録画]-[先頭から]をクリックすると「テレプロンプター」ビューになります。(下図)

さらに、素早くこの表示モードを起動できるように、パワポの「標準」モード画面の右上アプリバーの [共有] ボタンの隣にある [録画] ボタンが用意されています。
これをクリックしてもこの「テレプロンプター」ビューになります。
[録画] ボタンで起動されることからお分かりのように、この表示モードはプレゼンのビデオ録画のためにありますが、今回は録画せずに「テレプロンプター」ビューにおける発表者サポート機能をご紹介します。
(1) ノート領域
「テレプロンプター」ビューで最初に気付くのは、「ノート」に記載した内容が画面上部に大きく表示されることです。
「発表者ビュー」における「ノート」領域よりも大きいので、小型のノートPCなど狭い画面でも容易に読み取れると思います。
また、画面上部に表示されるので、視線をPCの上部に向けたまま読めるので、参加者から見ても自然なカメラ視線のまま表示されます。
なお、カメラを有効にすれば、投影されるスライドの右下に丸く囲まれた領域に発表者の顔が映し出され、参加者は表情と共にプレゼンを聞くことができます。
「ノート」領域の文字は、その左下にあるテキストの拡大・縮小ボタンでそのサイズを変更できます。(下図)

上図は [テキストの拡大] ボタンを押し、テキストを拡大して表示させたときのもので、さらに下方にノートがあるときは、右側にスクロールバーが現れます。
これを操作して、下方のノートも読むことができます。
また、上部にある [マイク] ボタンの右隣にある [自動スクロールの有効化] ボタンをクリックすると、ノートのテキストを自動スクロールさせることができます。
ノートの右側に「スクロール速度」と書かれたダイアログが現れ、その左端にある再生ボタンをクリックすると、ノートに記載されたテキストが自動スクロールされます。
そのダイアログのスライダを左右に動かせば、スクロール速度が変わります。
スクロールを一時停止させるには、ダイアログの左端の一時停止ボタンをクリックし、再びスクロールさせるには、改めて再生ボタンをクリックします。
そして、画面のほぼ中央に表示される水平線をドラッグすると、ノート領域とスライド領域の割り当てサイズを変更することができます。
使いやすいサイズにしてください。
(2) スライド領域
「テレプロンプター」ビューの下半分であるスライド領域は、現在投影され参加者が見ているスライドが表示されています。
この画面上でクリックすれば、次のスライドまたは次のアニメーションとなります。
この画面の左下にはスライド(ページ)を 1ページずつ次へ/前へ送る操作ボタンがあり、現在のページが全体のどのあたりかもここで確認できます。
画面下部中央には、4つのアイコンとカラーパレットが並んでいます。
アイコンは、左から順に
- レーザーポインター
- 消しゴム
- ペン
- 蛍光ペン
です。
操作は、「発表者ツール」での操作と同様なので、省略します。
画面右下にある人型アイコンは [カメラモードの選択] です。(下図)

これをクリックすると、上図のように「背景を表示する」「背景をぼかす」のいずれかを選択できます。
さらに右隣には [ビューの選択] ボタンがあり、下図のように「テレプロンプター」「発表者ビュー」「スライド表示」のいずれかが選択できます。

「発表者ビュー」を選択すると、下図のような表示モードとなります。

スライドショーを開始して使用する「発表ツール」に操作は似ていますが、上記 [自動スクロールの有効化] ボタンは使えません。
また、スライド一覧表示やスライドの拡大表示などの機能もありません。
「スライド表示」を選択すると、下図のような表示モードとなります。

先の「発表者ビュー」から「次のスライド」「ノート」が非表示となり、スライド領域だけとなります。
(3) ご注意
上述したように、これらの表示モードはプレゼンのビデオ録画のためにあります。
そのため、特に「テレプロンプター」モードでプレゼンするとき、スライド一覧表示やスライドの拡大表示などの機能は使えません。
これらの機能を使ってプレゼンする場合は「発表者ツール」を使いましょう。