今回紹介させて頂きます帯は、江戸時代後期の 「 麻の葉つなぎ花の丸文様打掛 」 を
モチーフに制作しました。
麻ノ葉文様の名称は、形が大麻の葉に似ていることにちなんだものです。
麻の葉は丈夫で成長が早い事で、古来より吉祥文様として着物や長襦袢また織物の
文様として用いられました。
本来は正六角形を基礎とした文様ですが、そのイメージが残る範囲で柔らかく崩す
ことで洒落感を出しています。

≪ 疋田麻ノ葉文 ≫ ひったあさのはもん

疋田は “ 本疋田独特の立体感 ” と “ 躍動感 ” を表現するために “ 織物組織 ” と
“ 技術 ” を駆使しています

技法としては < 有職唐織 > ( ゆうそくからおり )を用いています。
< 有職唐織 > ( ゆうそくからおり )という弊社独自の技法は、 弊社独自の
≪ 有職錦 ≫( ゆうそくにしき ) をベースにした技法です。
西陣織を代表する織物組織には、畦( 綴 )・綾( 錦 )・朱子( 緞子 )の三大組織が
あります。各組織にはそれぞれ特徴があります。
【 綴 】 は、緯( 横糸 )をつめる緯組織なので生地がしまり力強い生地になります。
しかし、「 つや 」 がなく、地風はやや硬くなります。
【 緞子 】 は、細い経糸( 縦糸 )を数多く使用し経を多く出す経組織の為に「 絹本来
のつや 」 は出ますが、生地が重くなります。
【 錦 】 は、それらの中間組織である為、使い勝手がよく、一般的に用いられやすい
のですが特徴がありません。
そこで弊社では、緞子地に匹敵する細かく数多い経糸 ( たていと ) に、綴 ( つづれ )
以上に極細の緯糸( よこいと )を使用して織る事で、生地の組織率を高め生糸のつやを
残しつつ、軽くしなやかでこしのある生地としました。
このように各組織の基本をふまえ、それらの長所を重ねる為には、素材の良さが大切で
製織技術も重要となってきます。それらを統合したものが弊社技法 < 有職錦 > です。

その【 生地 】をベースにして、≪ 疋田麻ノ葉文 ≫ のようなボリューム感を表現する為に
土台となる生地を通常の倍の組織にして“ 箔 ” を用いなくても品格のある生地に仕上げる
とともに柄を表現する緯(横糸)も異なった色を倍越することで立体感をだしています。
それが弊社独自の < 有職唐織 > ( ゆうそくからおり )という技法です。

【 参考本 】



【 色無地 】【 小紋 】【 織の着物 】 にも合せて頂けます

難しい説明になってしまいすみません。“ 帯の写真 ”だけでもお楽しみ頂けたら嬉しいです。
最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。
≪ お礼 ≫
2月10日(水)~23日(火)まで銀座三越にて開催されていました【 西陣織アンソロジー 】の
イベントへ、沢山の方が足をお運びくださりありがとうございました。
また、ブログをご覧くださっている皆様にも沢山お声をかけて頂き嬉しかったです。
ありがとうございました。
2箇所のランキングに参加しています
2箇所共クリックしてくださると嬉しいです
過去の日記は【 和装小物・バック umegakiorimono オンラインショップ 】をご覧頂けると
嬉しいです http://umegakiorimono-online.jp/hpgen/HPB/categories/7431.html
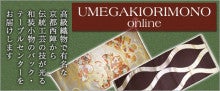
 梅垣織物 公式 Facebook
梅垣織物 公式 Facebook