正徳の治でアホウな金融引締め等をやったことによってデフレ不況を引き起こした新井白石は、暴れん坊将軍で有名な徳川吉宗に罷免されました。
しかし、徳川吉宗も当初は金融政策に興味を示さず、緊縮財政に勤しんでいたため、一向に経済はよくなりませんでした。
そこで出てきたのが、大岡越前こと、大岡忠相です。彼が元文の改鋳というリフレ政策を行ったのです。
---引用ここから---
第六章 栄達の裏
現行の貨幣の含有品位は、純度を百とすれば、金は六十七、銀が八十で、銀の品位が高くできている。
このため、自然、銀高、金安に傾くのであった。
(略)
「ここが、肝心要であったのでござる。それゆえ、貨幣の全面改鋳をおこない、金貨と銀貨の品位を同率にするか、金貨をやや高めにすれば、上方商人の暗躍があったとしても、自ずと、金銀相場は正常に働き、多少の金高、銀安にて安定し、江戸の物価にとって、好都合の結果をもたらすのでござる」(p287)
享保二十一年は四月二十八日に改元され、元文元年となる。
その五月、貨幣改鋳が、勘定奉行細田時以と町奉行大岡忠相に下命された。町奉行が貨幣改鋳の担当奉行を兼ねるのは、異例中の異例であった。
貨幣の量を増やすために、当然、品位は下がる。金貨と銀貨の品位比率は、忠相としては、一割くらいの差をつけたかった。だが、御側役加納久通の意向が強く働き、金貨が六十、銀貨が五十八という僅差に落ち着いたのである。(p289)
---引用ここまで---
ソース:
大岡越前守忠相 (講談社文庫)/講談社
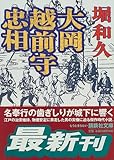
¥670
Amazon.co.jp
改鋳というと、普通は小判(金貨)の改鋳を思い浮かべると思いますが、この元文の改鋳のポイントは、銀貨の含有量を減らしたところです。
当時、生産の中心は上方(関西)で、実際は上方が物価を決めていました。上方が主に使っていたのが銀貨です。この銀貨の価値が上がりすぎることが当時のデフレ不況の一番の原因だったため、大岡忠相らは、金貨と同時に銀貨の改鋳も行い、貨幣の流通量を増やし、デフレ脱却に成功したのです。
含有量を3割弱ほど減らして銀貨の量を増やした訳です。(もちろん小判も)
現代とはちょっと異なりますが、通貨が不足している時(デフレ)にその量を増やしたという意味では全く同じです。
現代のアベノミクスにも通じるものがありますね。
つづく(?)
↓↓↓拡散のためクリックお願いします!!
社会・経済ニュース ブログランキングへ
読者登録もお願いします。