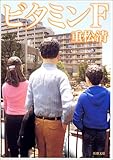- ふり返るなドクター―研修医純情物語 (幻冬舎文庫)/川渕 圭一

- ¥680
- Amazon.co.jp
なぜか発言は英語オンリーの会議。
脱サラし37歳で医者になった佑太は、そんな大学病院の現状に驚く。
曲がったことの大嫌いな医師・瀬戸だけが彼の味方だった。
ある日、教授が医療過誤を起こし…。
組織に立ち向かう二人の医師の葛藤と友情を描いた、
リアルで痛快な医療小説。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
前作の「先生と呼ばないで」と同様、中年研修医が主人公。
別人ではあるけど、似た設定なのは主人公=作者だからだろう。
研修医の生活を描いた前作に似た部分も多いが、主人公の悪友の
医師である瀬戸の存在が前作と違った展開を見せてくれている。
瀬戸はベテランの優秀な医師であるが、とにかく報われない。
教授との関係が元に、振り回される数年間。
上司と反りが合わないという話はよくあるが、一般的な会社組織で
あれば、それだけで瀬戸程の苦難がもたらされる事は無いように思う。
組織では、属するメンバーを適切に配置して、効率良く業務を遂行する
必要がある。
上司の個人的な感情は、それらに優先されるべきものではない。
多少上司とぶつかり合っていても、結果を残していればそれを組織は
評価するものだ。
しかし、大学病院という組織の中では教授は絶対的な存在であって、
その意に沿わない様な人物に対しては、瀬戸のようなひどい扱いが
待っているというお話。
この辺り、政治的な医療ドラマそのままのイメージ。
現実に、このような感じなんだろうなと思ってしまう。
というストレスの溜まる展開ではあったけれども、最後に教諭が
権威を失うというある意味痛快な展開が待っていた…と思いきや
まさかの夢オチ…。
夢オチなんてめったに見ないから、新鮮だったけど拍子抜け。
大学病院を退いた主人公は作家を目指す。
そして自分や瀬戸をモデルとしたお話を書く事に。
まさにメタ展開。
作者も2作目だけに、色々な試みをしてるんだなぁ。
こういう展開も、ニヤリと出来るので悪くないなと思う。
前作は主人公一人だった日常パートも、彼女や瀬戸の存在が
ある事でバリエーション豊かに。
合コンの話などで親近感。
しっかし、お医者さんってやっぱりモテるんだろうなぁ。
収入、世間的な地位、優秀な頭脳、これだけ揃ってればなぁ。
とは言っても人命を扱うような大変なお仕事。
それほど羨ましいとは思えない…。
最後は非常にすっきりとした展開。
主人公自身が目指していた明るい話となっている。
第3作の「五郎とゴロー」にも期待。