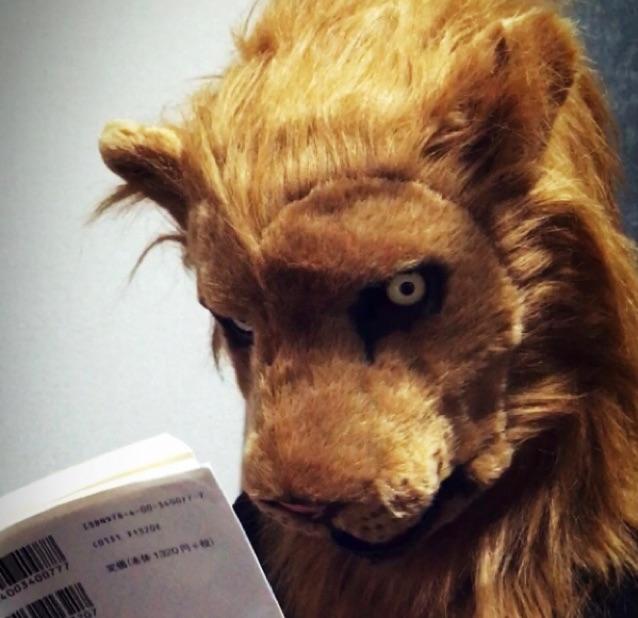2020年は『SDGs入門』から『粘膜蜥蜴』まで、電子書籍や書評を書いていないものも含めて、全部で25冊、本を読んだ。
冊数としては、去年は15冊ということで、おそらく人生最低記録だったので、いちおう回復した。その以前が27冊とかだったから、まあ取り戻したといっていいかもしれない。しかし最低記録に達する以前からひどい読書状況だったので、昨年対比ばかり見てても売れ方みえてこないのと同じく、安心してもいられない。ふつうにやってせめて週1冊、50か60くらいは読んでいたい。それでも最低ラインだろう。書評ブロガーで書店員なのだからせめて・・・。
月ごとに見てみると、3月を除いては、どの月も1~3冊読んでいる感じで、まあまあバランスがとれている(3月に読了がなかったのは、おそらく『近代立憲主義と他者』を読んでいたからである)。いつも前年に読みきれなかったのが流れてくる年初めと、今年中に読み終えようとして年末には数が増えがちなのだが、そういうことも特にない。まあ、もとの数が少ないのでこれも意味のない分析だが。
2019年がひどかったのは、ひとことでいえば病んでいたからである。前にいた会社は、販売会社が深く関与することによって、かなりデータ主義的なところがあって、ぼくはそれを問題だと考えていた。リアル書店はロングテールから書店員の個性が拾い上げるものに表情が浮かび上がるから、金太郎飴みたいにどこでもあるものばかり置いていてもしかたないのである。しかしいまとなっては「数字」がものをいう世界がとても懐かしい。いまは数字さえ誰もろくに読み取ることができないまま、ぬるい仕事を、みずから意味のない負荷をかけてきつくやっているのだ。「横断歩道の白線をふみはずしたら死ぬゲーム」みたいなものである。そういう状況だったから、帰宅しても読書する体力、また気力が残っていなかったのである。だがそれも、「優れた書店員」であろうとすることをやめることで、回復した。努力を重ね、頭角をあらわしていけば、それを望まないひとと衝突するのは当然のことなのである。といっても、じっさいにはそれはかなり流動的で、なにか自己肯定感があがるようなことが起きたとき、たとえば、じぶんで仕入れた洋書がポンポンと売れたり、ずっと売れなかったものをPOPつきで面陳にしたらその日に売れたり、お客さんに誉められたり、そういうことがあると、つい前の、書店員でいるときの気分に戻ってしまう。じっさいには、日常の業務に「なにも期待しない」でいることは、かなり困難なのだ。でも、そうすることができるとわかったことは大きかった。そのおかげで、今年は2年前程度には本が読めたわけである。ぼくにとって読書はなによりも重要なものだ。記憶力がわるいので、読むはしからすべて忘れてしまうが、それでも、ふとしたときに「あれ、これなにかに似てるな?」みたいな思い出しかたをするところをみると、いちおう血肉にはなっているようであり、そして、これまでの書きものはすべて、「読んできたもの」で構築されているのである。なによりも本を読むこと、である。この先ぼくがなんらかの能力をじっさいの仕事できちんと行使することがあるのだとしても、それは経験によるものではない。読書である。
さて、通常であれば、ブログのテーマわけにしたがった分類で見ていくが、冊数的にそうしてもあまり意味がないので、もっと大雑把に見ていくと、小説、フィクションが4冊、詩集が1冊、随筆が5冊、ビジネス書が3冊、法学系の本が2冊、その他批評などが10冊である。
小説は、まず『店長がバカすぎて』がすばらしかった。現存の若い作家、しかも多くのひとが読んでいるような本を読むのはあまりないことなので、その意味でも新鮮な気持ちになれた。今後も直木賞候補や本屋対象候補みたいな分野も、食わず嫌いせずに見ていきたいものだ。
今年の2月には、高校生のころから愛読している偉大な作家、浦賀和宏が亡くなった。
小説4冊のうち1冊は、遺作のひとつ前の作品となる『デルタの悲劇』である。これが、作品内に登場する「浦賀和宏」が死亡する作品であるというのも、なんともひとを食った、浦賀和宏らしい状況である。ぼくが浦賀先生から受け取ったものはもはや測定できるようなものではない。なにしろ思春期の、もっとも本を読んでいた時期に熟読していた作家なのだ。文体や思考法はもちろん、愛好する音楽まで、強い影響を受けてきた。かんたんに乗り越えられるようなものではないし、遺作となった『殺人都市川崎』も、せっかくほしいものリストからいただいたものだが、読めていない。しかし、これからも浦賀和宏批評は続けていくつもりである。中期のシリーズで読んでいないものがまだけっこうあるので、そういうのを読んでいきつつ、例の「どんでん返し」が再読にあたってはどういうふうに働きうるのかという視点を、いまは考えている。浦賀先生の作品は、ミステリだが、いちど読んで、いちど驚いて終わりというものではない。「驚き」にかんしてはそこで終わりかもしれないが、その先が必ずある。その鉱脈を批評的に探っていきたいと、人生の半分を浦賀和宏で構成してきた読者として考えている。
随筆に含めた金田淳子によるバキBL、『「グラップラー刃牙」はBLではないかと1日30時間300日考えた乙女の記録ッッ』も、1月に読んだものでありながらまだ印象が鮮やかだ。もちろん、読みつつ爆笑してしまうような本ではあるのだが、イロモノではない。読み方の手続きの本である。
今年のもっとも大きな収穫としては、たった3冊ではあるが、ビジネス書を読めたということがある。『SDGs入門』、『企業不祥事を防ぐ』、それから、記事にはしていないが、電子書籍で『小さな会社が大きく伸びる55の最強ビジネスモデル』である。とりわけ『企業不祥事を防ぐ』はためになるうえにふつうにおもしろく、おすすめだが、ともあれいろいろこれまでの視点ががらりと変わっていくような感覚もあった。というのは、特に前の店で働いていたようなころには、ビジネス書とか自己啓発書というのを、ちょっとバカにしていたわけである。いまでも、「なぜ××なのか?」という文体・タイトルで、本来××に入る命題は当たり前ではないのに、さも自明のように書かれているものには警戒しているが、それでも、だいぶガードがゆるくなったとおもう。なぜなら、毎日いじって展開しているからである。そうすると、自然にさまざまなことに関心が生じ、またくわしくなってくる。以前のぼくなら、SDGsと聴いても、「ああ・・・なんか、環境問題のやつでしょ?」くらいの感じだったろう。まあいま「SDGsとはなにか」と問われてもそう応えるだろうという気はするが、ここでいっているのは関心の問題だ。要するに、タイトルにSDGsと書いてある本とESGと書いてある本を併売できるようになるためには、その認識の段階ではいけないわけなのである。だから自然と、経営やビジネスモデルにも関心が向いてくる。ほんらいはそれが実生活に関係しているのが望ましいが、ぼくにはそれは二の次というか、どうでもいい。おもしろくて、世界の死角がまたひとつ失せていく感覚が、ぼくの知的関心が求めるものである。その意味でぼくは筋金いりのディレッタントである。これはビジネス書に限ったはなしではなく、たとえばもともと憲法の勉強をしていたようなところで法律の本を触るようになったから、自然と民法、刑法などにも興味がわいてくるのである。ぼくは書店員で、いちばん最初に新刊を触るので当たり前だが、実はこれは利用者の立場であってもそう変わらないものであって、書店の利点はこういうところにあるのだ。
その法学関係の本は、江藤祥平『近代立憲主義と他者』と、非常に網羅的な『法と心理学への招待』である。『近代立憲主義と他者』は非常に興味深い内容ながら難解であり、読むのに苦労したが、これほど鍛えられる読書もなかった。法学に関してはひとつレベルがあがったような感じさえしたものである。『法と心理学への招待』もまた、あらゆる方面からの法学、また心理学の基礎知識が手に入り、たいへん勉強になった。ぼくのばあい、好きなものから適当に読んで言っているから、基礎的なぶぶんがぜんぜんできていない。ピアノもそうだったけど、すぐ先にすすみたがる人間で、基礎練習みたいなことはかったるくてなまけてしまうのである。だから、ある段階でつまずく。おもえばぼくは数学もそうだった。ぼくは大学は数学科にすすんだのだが、それは数学がなにもしなくても高得点がとれるからである。事実、大学に入って半年くらいは、ぜんぜん講義にでなくてもひとりだけ満点がとれたりした。しかし、すぐについていけなくなってしまったのである。当たり前である。なんでもそうなのだ。こういうところで、この本はすばらしい相棒になってくれた。いまでもすぐ手に取れるところにおいてあり、とりわけ『九条の大罪』の感想を書くときにお世話になっている。また、本書の書き手のひとりでもあった廣井先生の「司法臨床」という、法と心理学の交差点という概念にもひかれ、『司法臨床入門』を手にすることにもなった。こうしてぼくの関心は広く浅く、枝分かれしていくのである。
さて、去年くらいから基本テーマになっているフェミニズムにかんしては、いちおう勉強をすすめたが、おもったようにははかどらなかった。ひとまずは『ジェンダー論をつかむ』と『ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた』を通じて、去年から引き続き、基礎的な知識を身につけていくことはできたかもしれない。だがここでいっているのは、『82年生まれ、キム・ジヨン』が示した語り口の問題である。何度も書いていることなのでさすがにしつこいかもしれないが、あの小説は設定としてはキム・ジヨン氏を診断した医師のカルテという設定になっている。ここで「カルテ」とは、リアリズム勃興のときに、ゾラが至高の文体を実現したものである。ひとことでいえば、「科学」が、わたしたちに究極の客観を授けたのだ。だから、カルテのような、症状を人間から分離して無機質に記載したようなものが(それが作品としてどうであるかということとはまた別に)究極の客観であると考えられたのだ。この意味で、キム・ジヨン氏の半生を書き写したカルテは「客観」であり、見えにくかった女性差別を浮き彫りにしたはずである。ところが、最終部分、この医師においても、ごく素朴なものではあれ、しかしそのぶん典型的な女性差別があらわれるのである。客観であるはずの、女性差別を無機質に記載するはずのカルテが、女性差別を含むのである。これを非対称性の問題に回収してよいものだろうか。わたしたちは、ほんとうに「女性差別」を語ることができているのだろうか。
こういう疑問がこの2、3年くらいあって、ぼくが参考になるのではと考えてきたのが、魯迅とプラトンである。というのも、魯迅の代表作「狂人日記」は、『82年生まれ、キム・ジヨン』とほぼ同じ構成だからだ。そういうわけで、岩波文庫の『阿Q正伝・狂人日記』を読み直した。「狂人」は、周囲から狂っているとおもわれているが、その日記のなかで中国の人肉食を告発する。だが、じつは、彼自身が、どうやら人肉をすでに食べていたらしいということが発覚する、というはなしなのだ。人肉を食べているかもしれない状況で、彼はどうやってそれを告発できるのだろう。魯迅は『吶喊』の「自序」のなかで、わたしたちを外部から規定する逃れがたいシステムを「鉄の部屋」に形容しながら、ひとまずの告発、「吶喊」ののちに、未来へ託すというヴィジョンを諦念のなかに示している。魯迅が少年時代を懐かしむ作品を書くのは、それがまだシステムにとらわれる以前の空間だったからだ。そこにしか希望はないのだろうか?こういうことを研究するつもりでいたのだが、うまく進まなかった。プラトンにかんしては、「対話」がどのようにして可能か、ということのヒントになるかもしれないと考えた。プラトンの描くソクラテスは基本的に論破してまわっているひとだ。そうすると、論敵となる相手は、けっきょくソクラテスのひとりごと、モノローグに回収されてしまうことになるだろう。とするとこれは対話といえるだろうかと、こういうことを、逆説的に学べるかもしれないとおもったのだ。が、けっきょくなにも読めなかった。これは引き続き来年の課題である。
誰も気にしていないとおもうが、今年のベスト本はというと、フィクションは『店長がバカすぎて』、それ以外では『近代立憲主義と他者』ということにする。まあ、目標達成という意味ではけっこうダメな点も目立つけど、こうしてみると案外いろいろなものを読んだなという感じもするので、よしとしよう。来年もがんばるぞ。
管理人ほしいものリスト↓
https://www.amazon.jp/hz/wishlist/ls/1TR1AJMVHZPJY?ref_=wl_share
note(有料記事)↓
連絡は以下まで↓ 書きもののお仕事お待ちしてます
↓寄稿しています