- ZERO LANDMINE

- ¥2,605
- Amazon.co.jp
2001年に坂本龍一が、国内有名アーティストはもちろん、世界中の音楽を中心とした表現者の手を借りて制作した、地雷ZEROキャンペーン・ソング。
このシングルという個物がもつ社会的な意味は置いて(といっても無視できるものではないが)、僕は教授がじっさいに世界を旅することで音源を得、協力を集中させることのできた各国のすばらしいミュージシャン(音楽で表現をする者)たちによる音楽の連鎖がほんとうに好きで、何度聴いてもふるえがくる。
基本的には教授の盟友、YMOのメンバーであった細野晴臣がベース、また高橋幸宏とスティーヴ・ジャンセンが贅沢なツインドラムを担当して、禁欲的にビートを保ちつつ、それぞれの国独特の民俗音楽がそのうえを流れていくという筋書きだが、僕がなによりも好きなのはシンプルながら非常にバウンスした教授のピアノと、TAKURO(GLAY)、SUGIZOのギターのからみがかっこいい、短いブリッジだったりする…が、それはやはりこの曲のブリッジにすぎず、また通奏して、非常に高度ながらしかし雑多になりかねない各地のフォーク・ミュージックをタイトに締める、いわばトラックの露出部であって、ここがかっこいいのは当然なのだ。これがだらけていたらおはなしにならないというもので、きっとこの長大な一曲の体感時間はもっと長く、推敲されすぎて新鮮さを失った文章のような、蛇足の連続となってしまうだろう。
といっても、べつにこれが「トラックにすぎない」ということがいいたいんではなくて、各国のサウンドを代表して物語のいちぶに組み込まれるそれぞれの音楽は、もしかしたらそれじたいで聴いてもたいして僕は感動しないかもしれず、たとえばコリア・セクションや、チベット・セクションのお経のところ(そう、お経?さえもサンプリングしてかっこよく仕上げてしまっているのだ!)にすべりこんでくる細野晴臣のベースなどはぞっとするほど精確かつ怜悧であり、延々と続くドラムスの乾いたスネアの音などもこれ以外のサウンドはありえないというもので、やっぱり教授の音楽監督(長期的コンダクター)としてのセンスはすばらしいものがあるとおもう。
モザンビーク・セクションにおける、非常にプリミティヴなかたちのラップもクールすぎる。僕はこのころもっとも坂本龍一に入れあげていた時期であって、TBSのNEWS23で特集が編まれ、長々としたメイキング画像(もちろん作品の主旨としてはこれも重要なのだ)のあとにライブと映像で披露された演奏も、ビデオにも録画して嬉々と観たものだが、当のビデオがどこにいったかもうすでにわからないいまでも、このセクションのボーカルの男のはにかんだ笑顔が忘れられない。
彼らの、人間がシンプルに人間であり続けることに返っていくような熱い咆哮ののち、伶楽舎による刹那の雅楽が導き、いよいよジャパン・セクションというか、日本の名のあるボーカリストたちによる合唱がはじまるのだが…、正直いってこの曲はここから途端にダサくなる。そういうわけで、僕はこっから先をほとんど聴いたことがない。がんばって聴き続けても、どうも耐えられない。理由はよくわからない。「ことば」が出てくることで急にうそくさくなるということかともおもったが、デイヴィッド・シルヴィアンによる原詞は英語なのである(ちなみに邦訳は村上龍が務めている)。ことばが、「意味」がまっすぐに伝わってこないという点では、「世界巡りセクション」においてもボーカル・パートはいくつもあるのだ。
そういうわけでひとことの内に「好き」といえない感じのある音楽なのだが、前半ぶぶんがとにかくすばらしいものであることはまちがいないとおもいます。
- Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2009 Japan

- ¥2,800
- Amazon.co.jp
- out of noise
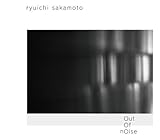
- ¥1,764
- Amazon.co.jp