山本七平『一下級将校の見た帝国陸軍』を読み始めました。
- 一下級将校の見た帝国陸軍 (文春文庫)/山本 七平

- ¥570
- Amazon.co.jp
まだ数ページというところなのだけれども、『「空気」の研究』とはやや異なった文体をみて、僕はなぜか「ブログっぽい」というふうにおもった。そして、このひとが「山本書店店主」という「場所」にこだわったことも含めて、この直観は案外核心をついているのかもしれないというふうに考えた。
- 「空気」の研究 (文春文庫 (306‐3))/山本 七平
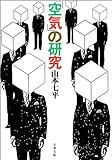
- ¥460
- Amazon.co.jp
日常ブログを扱うことに馴れていないひとには想像もつかないことかもしれないが、ブログの世界には(というかネットの世界には?)、特に書評系のブログ界には、とんでもないひとたちが大勢潜んでいるのである。医者だとかビジネスマンだとかを表の顔としつつ、プロ顔負けの(というか、アマチュアであることを含めて考えればばあいによってはプロ以上の)批評を展開できる教養と思考力をもっているひとが、びっくりするほどたくさんいるのだ。僕もじぶんでブログをやるようになるまではそんなことはまったく知らなかった。「それ」を目標にしている僕などは、なんでこのひとたちはこっちを本業にしないのだろうと訝ってしまうのだ。しかしそれは嫉妬的な感情以外のなにものでもなく、こういったひとたちのふるまいを読み誤っているとしかいいようがないのである。そして、こういったひとたちのふるまいと山本七平のありかたは、もしかすると非常に似た哲学に基づいているのではないかとおもえてくるのです。
サルトルの用語に「アンガジュマン」というものがあります。英語のengageと語源は等しく、「社会参加」とか「政治参加」とかいったことを意味します。
「(略)好むと好まざるとに関わらず、我々が状況の中に捉えられてしまっている(engage)のが私たち人間の根本的なあり方だ。このような事実と同時に、自分の自由を自覚し、投企によって状況のうちに自らを投げかけること(s’engager)。それがアンガジュマンという思想の骨子なのであり、参加することも、しないことも可能であるような、曖昧なものではないことはすでに指摘したとおりだ」
澤田直『新・サルトル講義』P119より
- 新・サルトル講義―未完の思想、実存から倫理へ (平凡社新書)/沢田 直

- ¥798
- Amazon.co.jp
サルトルのいうアンガジュマンの特徴は、たぶんその積極性だ。「投企」という用語はハイデガーが最初のようだけど、これは西研『実存からの冒険』の受け売りだが、サルトルとでは意味がまったく異なっている。「いまある状況」を「被投性」とし、その状況の輪郭の外へと働きかけ、更新していくようなうごきを「投企」とするが、ハイデガーではこのあらわれてくる可能性すらも委ねられたものなのだそうだ。サルトルにおいてこれは主体的であって、積極性を帯びたものだ。
そして、書店主山本七平的書評ブロガーたちのありようというものは、順序としては逆になるのだけど、このアンガジュマンというひとことに集約されるのではないでしょうか。いってみれば、述語的なのです。
山本七平的ブロガーたちにおける「書店主」的な社会的「場所」を、社会の規定する「ジョブ」とすれば、読書と書評による自己の成長と更新は、ある意味でアビリティの獲得であり、レベルアップの手段である。そうなると、そもそもブロガーの書くものがいかに「プロ顔負け」であっても、その文章が個人からあらわれてくる仕方は、プロのそれとは最初から意味を異にしていることになる。とすれば、プロの書くもの(批評)とはいったいなんなんだろうか…。
- 実存からの冒険 (ちくま学芸文庫)/西 研

- ¥882
- Amazon.co.jp