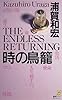- ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー/YMO
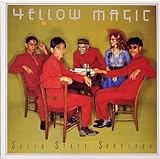
- ¥2,010
- Amazon.co.jp
少し前に坂本龍一について書いてから、じぶんのなかでちょっとしたブームが起きていて、久しぶりにYMOの「ライディーン」を聴いたら、ほとんど瞬間的にこのひとが浮かんできた。
これまで浦賀和宏というひとについて書いたことはほとんどなかった。というのは、なにをどう書けばいいのかわからないからである。どう考えても、あらゆる作家…それは文学者から推理小説家まで含めて、僕の知るすべての物語作家のなかでももっとも天才ということばがふさわしいひとであるにもかかわらず、あるいはそれゆえというべきか、どういうふうに書けばこの感じが伝わるのか皆目見当がつかないのです。いまでもついていません。だから、今回の記事は、島田荘司などのときと同様、通常の書評とは趣向を異にした、きわめて個人的な書き方でやろうとおもいます。
僕というにんげんは、いまさら説明の必要もないとはおもいますが、好きなものごとからは人間存在の根底レベルで影響を受けやすい人間です。僕の語る言葉はすべてどこかで好きな作家が書いた言葉であって、僕の紹介する音楽はどこかの尊敬すべき音楽家のむかし聴いていたものか、あるいはそこから派生して知ったものであり、気に入っている比喩表現やギャグは村上春樹やうすた京介のつかっていたそれの模倣変形であります。もちろんこのようなことはすべてのひとにあてはまるもので、僕らは常に誰かのくちにした言葉を再利用するだけなのだけど、それにしても僕のばあいのそれはうんざりするほどわかりやすく、露骨で、たぶん僕の性格もあるんだろうけど、じぶんでときどきいやになります。
そういうわけで、高校生のときはじめてこのひとの『頭蓋骨の中の楽園』を読んで以来、浦賀和宏が僕の人格形成(これは発達心理学的な意味ではなく、生が終わる瞬間まで行われる成長と同じような意味合い)におよぼした影響というのは、もうはかりしれないのです。たぶん自覚していないだけで、僕の行い…「述語」にとどまらない、根幹的な思想や、思考法などにも、影響はあるのかもしれない。
(ちょっとびっくりなんだけど、このシリーズぜんぜん文庫化されてないんですね)
『頭蓋骨の中の楽園』は、浦賀和宏が最初に書いていた安藤直樹シリーズの三作目ですが、たしか僕は新刊で読んだ気がします。巻末の奥付によると最初の発行は1999年4月5日で、これはちょうど僕が高校生になった時期にあたるので、それで合ってるとおもいます。なんでこんなことにこだわるかというと、僕のピアノ衝動は、この本が先なのか、それともすでにピアノ熱が甚だしかったときにコレを手にしたのか、僕じしんにはとても重要におもえるからです。
『頭蓋骨』を読んですさまじい衝撃を受けたあと、僕はシリーズ第一作…浦賀和宏のデビュー作で、第五回メフィスト賞を獲った『記憶の果て』を手にしました。主人公の安藤くんは卒業間近の高校生であって、ピアノを弾ける彼は、ふとした機会に浅倉幸恵という女の子と出会い、バンド・コンテストで彼女のグループとともに「ライディーン」を演奏することになります。彼が幼いころはじめに習得したピアノ曲は、エリック・サティの「ジムノペディ」でした。そして、僕が坂本龍一の楽譜を手にして、たまたま採譜されていた、「はじめて弾けるようになった曲」も、「ジムノペディ」なのでした…。これは、まあ読んでるかたには「知らねえよ」って感じだろうけど、僕という人間を自己分析するとき、とても重要だとおもえるわけです。そもそも僕は、浦賀和宏に出会う前に坂本龍一を聴いていたのだろうか?いまも使用しているコルグのシンセは高校入学時に購入したものなので、時期的にもほんとに微妙なのです。シンセ購入の動機は、98年モントルー・ジャズ・フェスティバルにおいてハービー・ハンコックとヘッド・ハンターズの『カメレオン』を観たからだということははっきりしているのですが。まあ、こんなことはささいなことだといえばそうですし、そんなことより、いまどんな曲が弾けるのかということのほうが重要だといえばそうなんですが、原理的にオリジナルにたどりつけず、生来的にシミュレーション的であるという人間のありかたが、僕のばあいはほんとに露骨なので、どうしてもこういった作業にこだわってしまうのです。こういった構造主義的な考え方…「オリジナルという幻想」は、表現を志向するひとにはつらい事実だろうけど、それだけに、ぜんたいを把握して受け入れることは、大切だとおもうんだよな~。気にしないにこしたことはないのかもしれないが。
安藤直樹の登場する物語は、僕の知る限りぜんぶで七冊。これらの作品に通底するのは、「すべてはどこかで必ずつながっている」という世界観だ。このことの意味は『頭蓋骨』でほぼ明らかにされるが、その裏表紙の解説において千街昌之というひとは次のように書いている。
「『記憶の果て』の主人公・安藤直樹が、古典的な「名探偵」の役割を演じるこの物語は、にもかかわらずその結末において多くのミステリファンを当惑させるだろう。―――だが私は敢えて、本書を謎解き小説(ミステリ)として読んでみることを勧めたい」
あの結末を看破するのは不可能といってもよいとおもうのだが、言いたいことはよくわかる。哲学のマクロの問いを、ミクロの層からロジカルに、またきわめて物語的に、シミュレーション的に解き明かした小説、とでもいえばいいのだろうか…。だから、この作家について書くということはむずかしいのである。はじめてフロイトやソシュールや、あるいは加藤典洋のような文芸批評を読んだときの知的興奮は、たしかに優れた推理小説において真相が明かされるときの感覚によく似ていた。そういう意味でこのひとの書くものは、たぶん浦賀和宏は嫌がるだろうが(なにかの小説でそんなことをキャラクターにしゃべらせていた)、哲学が世界的なフェイズにおける謎解きであるのと同じ意味合いで、ミステリであるのだ。
物語内にとどまらず、すべての物語間にはつながりがあるので、できたらぜんぶ読んでほしいところですが(というかそうしないことにはこの小説世界のすごさはまったく見えてこない)、まあひとつでも読めば、僕がうるさく言うこともなく、誰もがかってに読みすすめていってしまうことでしょう。ただ単品の衝撃度でいったら、カニバリズムを中心に据えた問題作『記号を喰う魔女』でしょうか(ほんとは、この作家がどの程度の知名度であるのかを知らないので、「問題」となったのかどうかはわからないのだけど)。デビュー作の『記憶の果て』では、前述したように、坂本龍一やサティ、ケージの音楽などが効果的なBGMとして用いられてもいて、若い作家らしいというか、創作衝動的な物語的無駄や冗長性も、いきいきとしていていい。
以下に、上の二作を除いた安藤シリーズを発行順に並べておきます。
透明人間―UBIQUITY (講談社ノベルス)