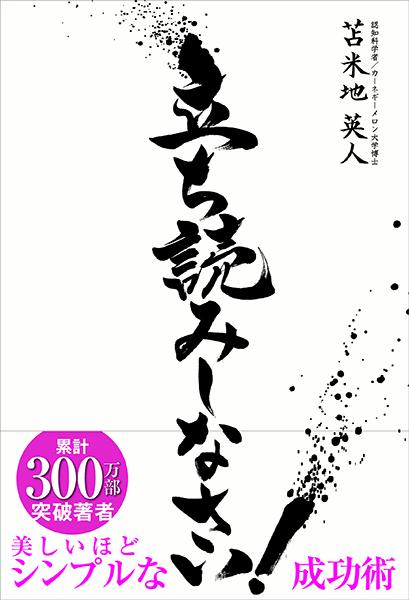(略)自信が先、成功が後
認知科学者・苫米地英人博士の「立ち読みしなさい!」201ページから引用いたしました。
エフィカシーとは、認知科学者・苫米地英人博士のコーチングでは、「自分の能力につける自己評価」を指します。
語義は正確に把握することが大切ですので、博士の初心者向けコーチング本「立ち読みしなさい!」などで体系的に学ぶことが大切です。
筆者は、小学生高学年くらいから「根拠のない自信」が強かったです。
根拠もなく、「エフィカシー」が高かったのです。型破りな自閉症スペクトラム(ASD)・ADHDの児童でした。中学生までは、型破りが許され、生き生きとしていました。
しかし、高校生になると、「年齢通り、普通に成長した人」であることを求められ、エフィカシーを徹底的に下げられました。
(教師の指導通り、「自分の学業成績・内申書で、確実に入れる高校」に入学してしまったのも失敗の原因です)
大学生になると、ますます「年齢通り」であることを求められるため、エフィカシーは地に落ちました。
中学生のときの部活動の先輩に会ったとき、「魅力のない人間になったな」と言われるほどでした。当時は、ASDの概念もほぼ知られておらず、大学で支援するなどありえなかったです。「メンタルヘルス相談室」みたいなものはありましたが、ASDの筆者については理解不能だったでしょう。
しかし今、筆者はエフィカシーを取り戻しつつあります。
これまで自身のエフィカシーが地に落ちていたため、博士のコーチングで重要視される「エフィカシーの大切さ」が腑に落ちなかったのですが、最近のいろいろな体験で、冒頭の引用文の意味が身に染みてきました。「確かにそうかもしれない」と…
具体的には、「根拠のない自信」は浮かんだら大切にしようと思い始めています。
コーチング技術のひとつ「アファメーション」で、「ゴールの臨場感を高める」のも、有効だと思います。
補足
苫米地博士の教材・講座等の説明文を読みますと、よく「技術の悪用を禁止」「技術を学んでも自分を見失わない人が受講したほうがよい」などの趣旨の記載があります。
そのために重要なのが、筆者にとっては「7つの習慣」の学習・実践だと思っています。
「苫米地英人博士のコーチング」と「7つの習慣」の立ち位置は、個人的にはそうなっています。
<参考書>
- 苫米地博士の、初心者向けコーチング本です。おすすめです。
- 「コンフォートゾーンの作り方」の次は、この本です。筆者も学習中です。
<注釈>
当ブログは、「7つの習慣」「苫米地英人博士のコーチング」を活用して、まったく将来の見えない「自閉症スペクトラム(ASD)の方」、「ひきこもり状態の方」、「グレーゾーンの方」、「生きづらい方」などの困りごとを根治させるという「はっきり言ってとんでもない内容」です。
「福祉の支援員さん」など一般の方にも役に立つと確信しています。
ただし、「守秘義務がある内容」は書けませんが…
※文中に出てくる「自閉症スペクトラム(ASD)」等は、「グレーゾーン」も含みます。
※「苫米地英人博士のコーチング」の専門用語は、書籍「立ち読みしなさい!」「コンフォートゾーンの作り方」で学ぶことをおすすめします。