
(No.ym-020)
<次へ← ・ →前へ 最初から>
当ブログのメインコンテンツの4コマ(単位の)マンガです。
昭和20年の広島を舞台にした「ヨシノとミコト編」です。
メイン中のメインのマンガの「カナエとムジャ子」の過去のお話です。
今回は第4幕「動員学徒の放課後」の3回めです。
<ここまでのお話の確認はまとめページが便利です>
第一幕「あの人との出会い」
第二幕「運命へのプロセス」
第三幕「動員学徒の日常」
<なぞの「雑炊食堂」>
ここからは解説メインになります。
ただし、この解説は正しいという保証はありません!!
今回のマンガを導き出した「推測」を記そうというものです。
福屋百貨店の地下食堂へ向かった3人ですが・・・この当時の福屋の地下一階は「雑炊食堂」になっていました。
(なお、一コマ目の雑炊食堂の外観は完全に想像です)
「雑炊食堂」というのは戦時中に独特の存在であったようです。
昭和19年の頃からの資料にその名前を目にします。
そもそも、当時の食料は配給切符制になっており、「外食」も例外ではなく「外食券」を使用する必要がありました。
例外的だったのが「雑炊食堂」で、これは金銭で雑炊を提供してもらうことのできる施設です。
雑炊は一杯20~30銭で提供されたようですが、非常に大雑把に現在の感覚に置き換えると600~900円くらいでしょうか(物価指数をもとに概算)。
これが政府の指示、すなわち「外食に頼らざるをえない者を支援するため」として始まったという解説も見たような気がします。
この点は、あやふやです。あたかも「自然発生的」に現れたような書かれ方をしている資料も多かったです。
運営は公共が行ってた例と個人が商っていた例の両方がありそうです。
福屋百貨店の雑炊食堂は「広島県食料営団」による運営です。
営団とは近衛内閣にて制定された半官半民的な特殊法人です。
(余談ですが、現在の東京メトロの前身である「帝都高速度交通営団」も、この定義の営団です)
「雑炊食堂」は全国の都市部に現れましたが、どこも「人気」でした。
11時頃に開店すると長蛇の列が出来て1時間半くらいで売り切れるというありさま。
ヨシノたちが行った時には閉店しているのも、当時の事情を鑑みれば当然。
人気の理由は美味だったからじゃないのです。
貴重な配給切符を節約しつつカロリーを得る手段だったからです。
出てくる「雑炊」は現代人の感覚から見ればロクなものではなかったといえます。
薄いおかゆにクズ野菜をいれ代用醤油(酷い物は「着色した塩水」と大差ない)にて味付けをした代物であったようです。
<お知らせ>
トリュフ・ラボの作品「カナエとムジャ子」の過去作品をアメブロ系の電子書籍サービス「マンガにしてみた」で公開しています。
全て無料ですし、閲覧だけであればアメーバへの会員登録も要りません。
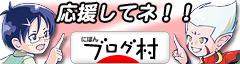
にほんブログ村
ランキングに参加しています、ぜひクリックをお願いします!!

