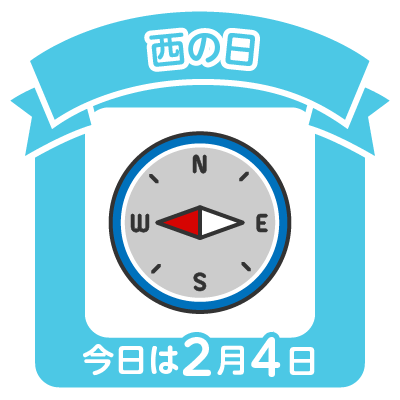梅探る病める心と向き合うて
「方円」2023年4月号円象集掲載。
2023年2月、ADHD・ASDとの診断を受けた頃に詠んだ句。場所は恐らく自宅から車で行ける枚方・山田池公園の梅林か。2月上旬から梅が開きだす。診断を受けて、すっきりした気持ちと不安な気持ちが入り混じったような不思議な感覚。そんな中で梅を見に出かけたが、この時はまだ蕾が多かった。今の自分の気持ちを見透かされたような気がして詠んだ句。
何度か書いたかもしれないが、今お世話になっている「雲の峰」の朝妻力主宰は、季語に対してネガティブな事を書いてしまうのは宜しくないと説く。例えば「立春」という季語に対して、寂れた農村の寂しさを詠むのではなく、春が来たという喜び、明るい気持ちを詠んだ方がいいという。歳時記を見ていると、確かに徹頭徹尾暗い気持ちを詠んだ句は少ない(ないことはないが)。なので、「探梅」に対して「病める心」というのは、ちょっと重苦しいかもしれない。こと句作に関しては思い悩まず、あくまで前向きな気持ちを詠んでいきたいものだ。
↓コチラも併せてご覧ください♪↓
俳句を始めませんか?