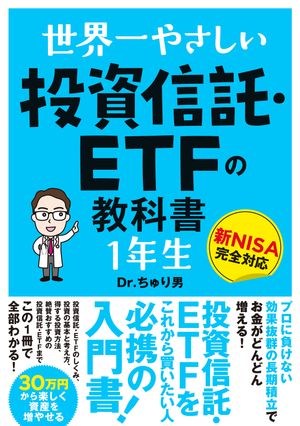MONEY PLUSの記事からです。
前半部分はiDeCoも含めた確定拠出年金に対する課税のあらましについて説明、後半は(昨年示された5年→10年ルールの変更も踏まえた)税負担軽減策を紹介しています。
税の負担を軽減する3つの方法として以下を挙げています。
・退職金を受け取った翌年に受け取る
「利用できる退職所得控除がゼロであったとしても退職所得控除は最低80万円が認められるルールがあるため、その分だけは老齢給付額から差し引くことができます。」
・分割で受け取る
公的年金等控除を利用する方法ですね。
・60歳で受け取らず、引き続き加入する
所得がある場合は、拠出金について所得控除が受けられるメリットを活かすという感じでしょうか。
記事の内容そのものというより、記事を読んでの感想的な話になりますが…
もちろん、税金は払わないものであれば払いたくはないし、少なく抑える方法があるなら実践すべきだと思っています。
一方で、iDeCoについて受取時に税金が発生すること自体が悪いことのような言説も結構見かけます。
ただ、この点については、制度自体がそもそも非課税ではなく課税の繰り延べを前提としているので、条件によっては受取時に課税が発生することはやむを得ないのかなと考えています。
(もちろん、今回改正により期間が長くなってしまう5年ルールをあてにして受取りを計画していた方にとっては「改悪」であることは確かでしょうし、「手のひら返し」「梯子を外した」という批判は妥当だとも思いますが)
それでも、退職所得に関する税制については、現状では勤続年数もしくは拠出期間に応じて受けられる退職所得控除や退職所得控除された後の金額をさらに半分にしたものが課税対象となるなど、現役時代の所得税に比べれば多くの場合は有利であるかなと思います。
さらに拠出期間中、拠出金については全額所得控除となるため、いずれ何らかの税金が発生するとしても多くの場合は税金面で損をするということは無いのかなと思います。
ということで、僕自身はiDeCo推しであるわけです。
少なくともNISA枠を埋め切れる見込みでさらに資金に余裕がある方には、特定口座ではなくiDeCoで運用することをお勧めしたいかなぁ。
ただしこれについては、僕自身の現在の勤務先の退職金の想定額があまり大きくなく、また40代後半からのiDeCoスタートだった(しかも拠出上額が今年からやっと2万円(昨年までは1.2万円/月)になるなど拠出額も少なかった)こともあり、いつから更なる上限の引き上げが実現するのかや今後の運用結果次第ではありますが、退職所得控除の範囲におそらくおさまってしまうであろうという悲しい現実があるから、ということもあるんですけどね。
ただまあ…
iDeCoが、というか本邦の年金制度自体が複雑に過ぎる感じはしますね。(他国の事情はあまり知りませんが)
なんかもうなんというか、もっとシンプルにならんかなぁというのは正直思います。(;^_^A
ランキング参加中です、ポチッとしていただければ密かに喜びます( *´艸`)