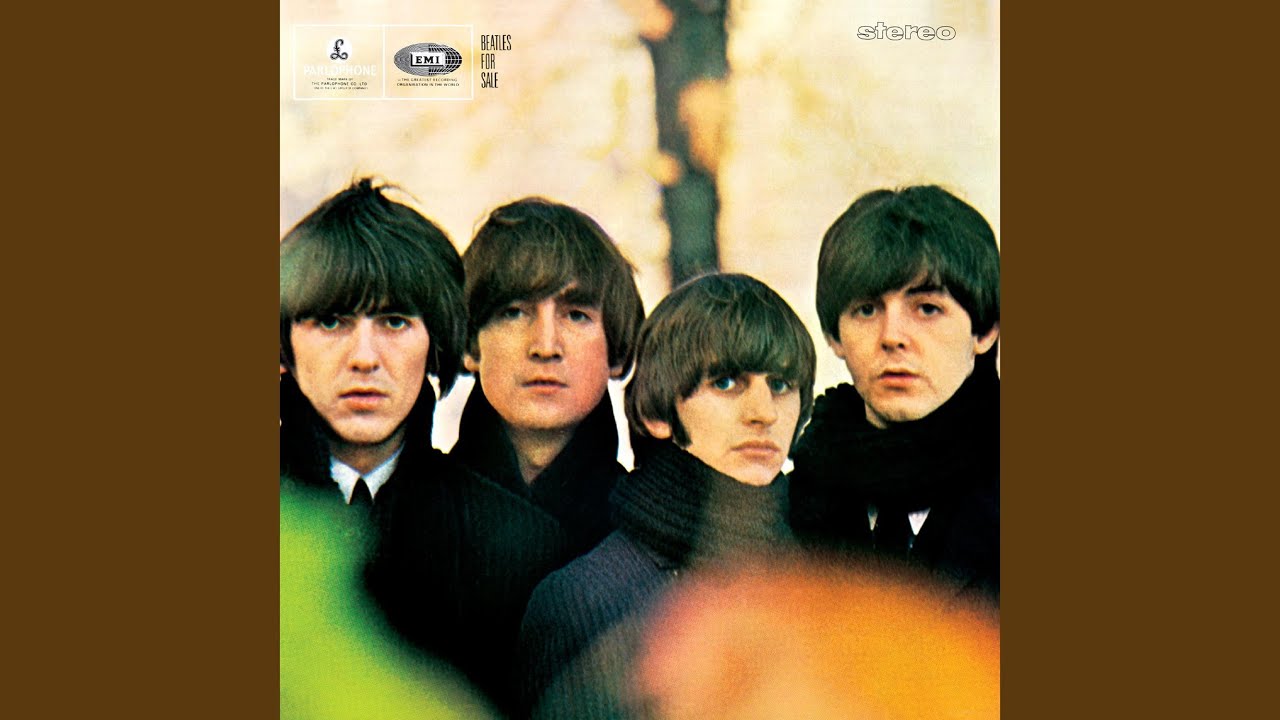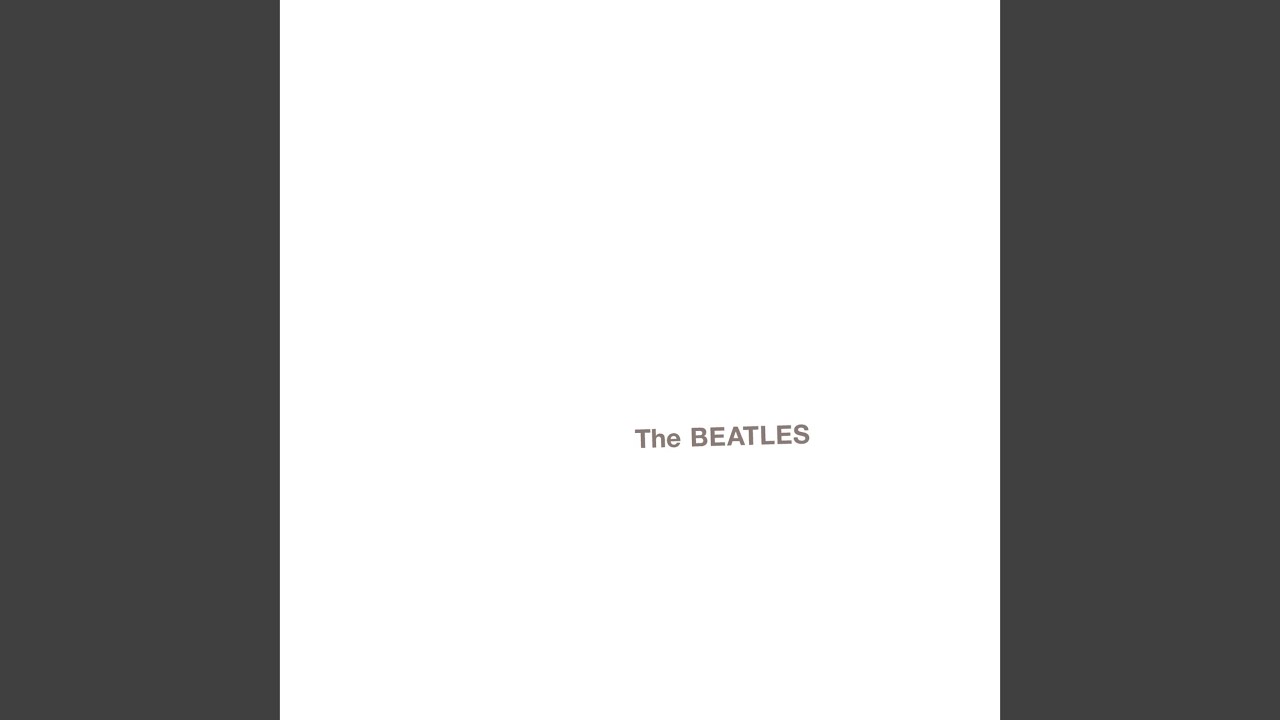●●●●●●●●●●●●●●
★134位
【Love Me Do】
<Single & PAST MASTERS Vol.1>1962.10/5=2:22/2:19=
正真正銘、BEATLESのデビューシングルである。
1958年、不登校生だった当時16才のポールが書いた曲。
ジョンはミドルエイトを書いたが、「“Love Me Do”はポールの曲だ。僕らが本格的な作曲家になる前、ハンブルクの頃から曲を持っていたんだ」と語っている。
しかし、ポールはフィフティフィフティだったと言っており、珍しく意見が食い違っている。
(初期BEATLESは、2才年上で一早く才能を開花させたジョンの方が多作だが、実は、ポールの方が先に作曲していて、ジョンが影響を受けて、やがて共作もするようになるのである)
1962年発表のデビューシングルにて、英17位を記録。翌63年のデビューアルバム 「Please Please Me」 に収録。
64年には米で発売され1位を記録。
シングルVer.は1962年9月3日に録音。このDrはリンゴである。
彼らがレコーディングしたのは、この“Love Me Do”と、カヴァーの“How Do You Do It?”だったが、オリジナルに拘った彼等の意見で、“Love Me Do”がデビューシングルとなる。
しかし、リンゴのDrにも不安があったジョージ・マーティンは、改めて9月11日に“Love Me Do”を再度レコーディングを行った。
この時の録音では、マーティンがセッションドラマーのアンディ・ホワイトを連れてきており、リンゴ・スターはドラムではなくタンバリンでレコーディングに参加することになった。これがアルバムVer.である。
彼等は、この日、“P.S. I Love You”のレコーディングも行っている。
ちなみに、混同を防ぐため、このリンゴの叩いた9月4日バージョンはマスターテープを破棄されてしまいます。
今では「パスト・マスターズ」に収録されていますが、ここで聴くことが出来るのはレコードから拾った音です。
実は、もう1つ、3つ目のVer.があり、1番最初に録音されたのは1962年の6月6日で、EMIの契約の為のオーディションと言われるセッション内である(Drはピート・ベスト)。
更に、当初はジョンがンがメインで歌う予定だったが、ジョージ・マーティンのアイデアで、イントロのジョンが吹くハーモニカのパートが追加されたので、歌い出しと重なる為、ポールが歌うことになった。
ポールの回顧によると「あれはすごく緊張した出来事だったよ!いきなり歌えって言われてさ」だったそう。事実、レコーディングされたものは、ポールの声が少し震えているのが今でも分かる。
リバプールというイギリスの田舎から出て来ての初レコーディングで、ポールはまだ20才であったのだから、当時としたら当然というか、仕方なかったことだろう。
そのジョンが演奏するブルージーかつドライなハーモニカのイントロのリフ、これが実に渋い。
ハーモニカにビブラートをかけている箇所がありますが、ビブラートの周期を意図的に倍に変えていますね。
特に、ビブラートの周期を小節に合わせて三連符的にすることで、ただのビブラートではなくビブラートを活かしたアレンジになっている点がユニークです。
さて、Voですが、ポールの歌にジョンのコーラスが加わり、ツインVoになってくる。
特徴的なコーラスワークですが、Aメロのコーラスのメロディラインは主旋律に対して平行した動きになっていません。
また、コーラスの存在感が主旋律を凌ぐような存在感を持っていて、この曲の大きな特徴1つになっています。
素朴で派手さとは無縁だけれど、噛めば噛むほど味の出る曲である。
●●●●●●●●●●●●●●