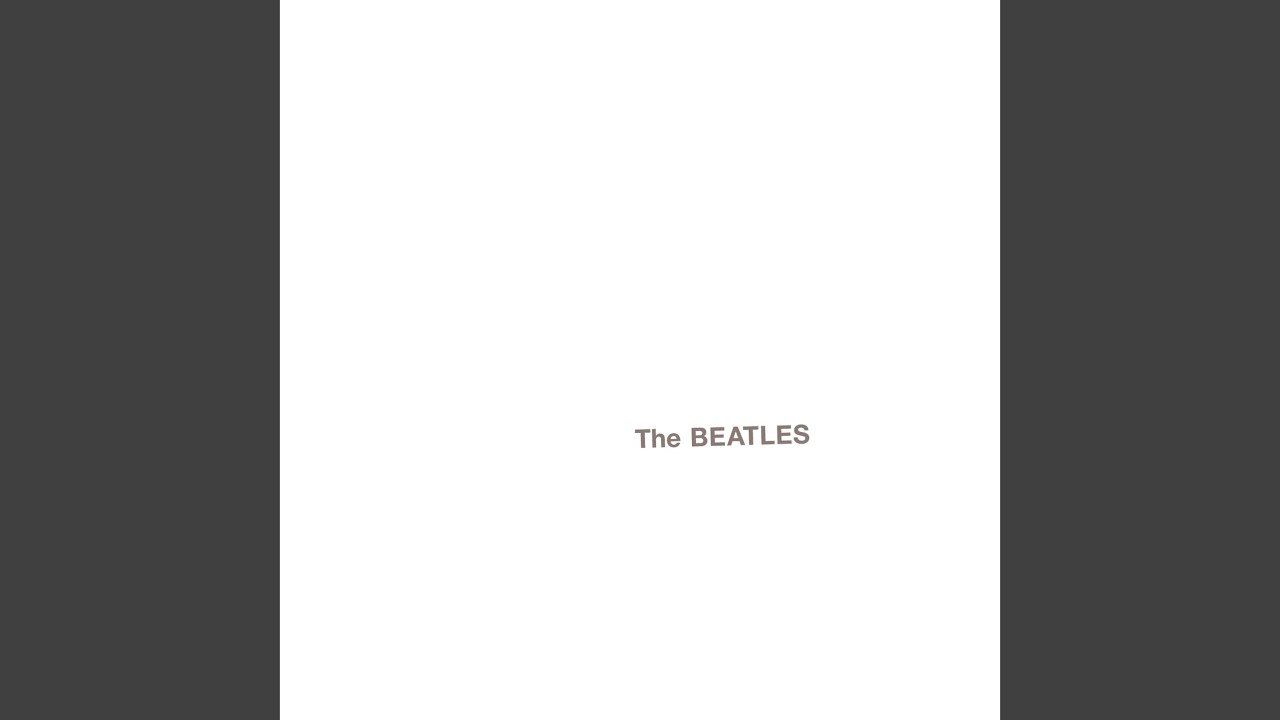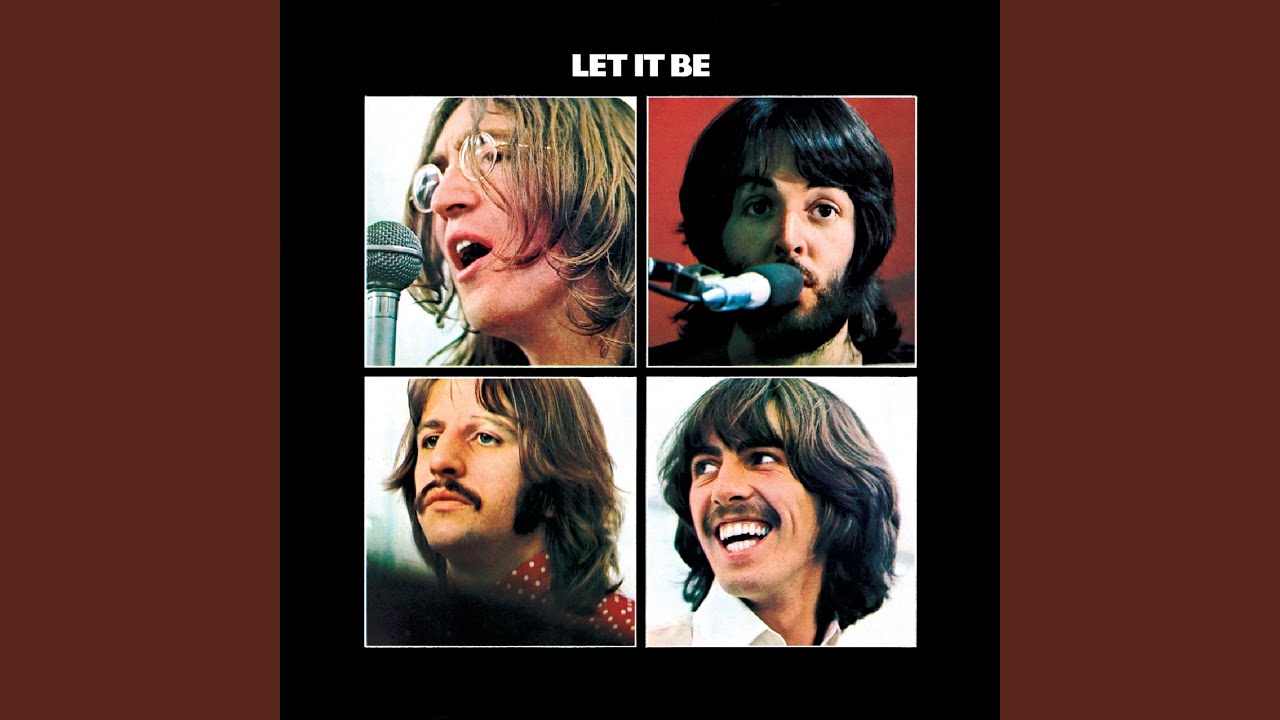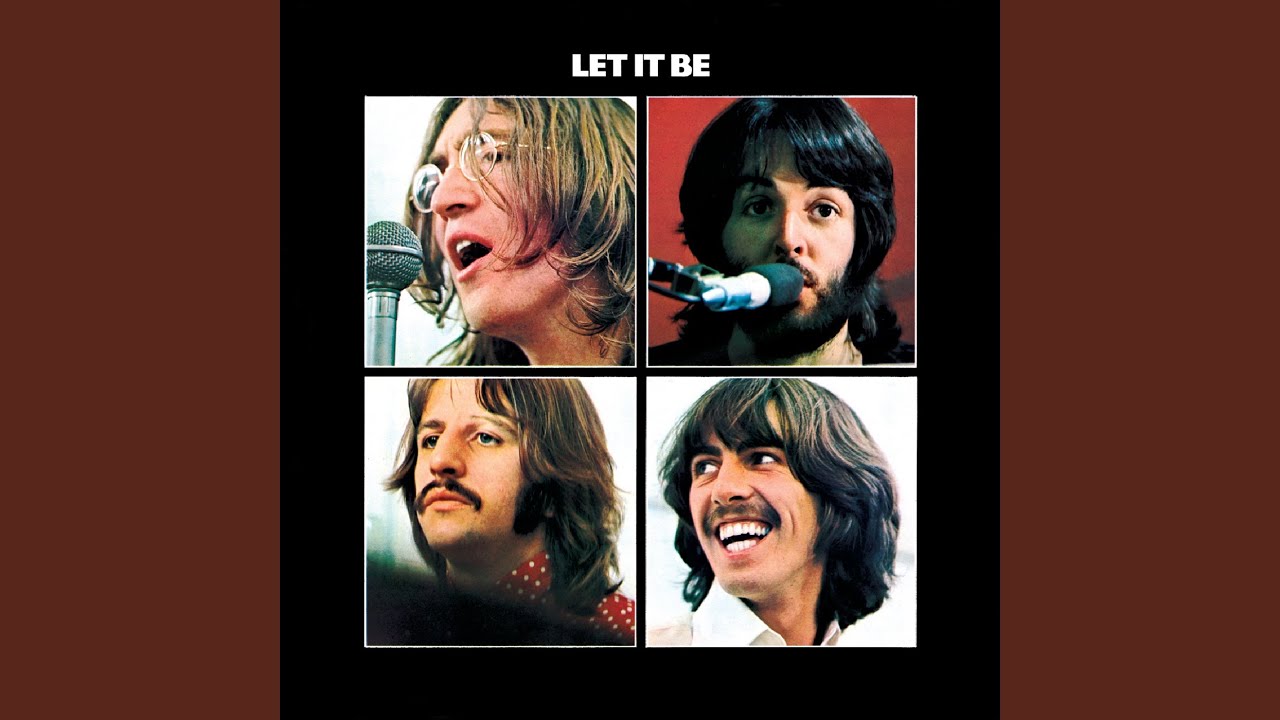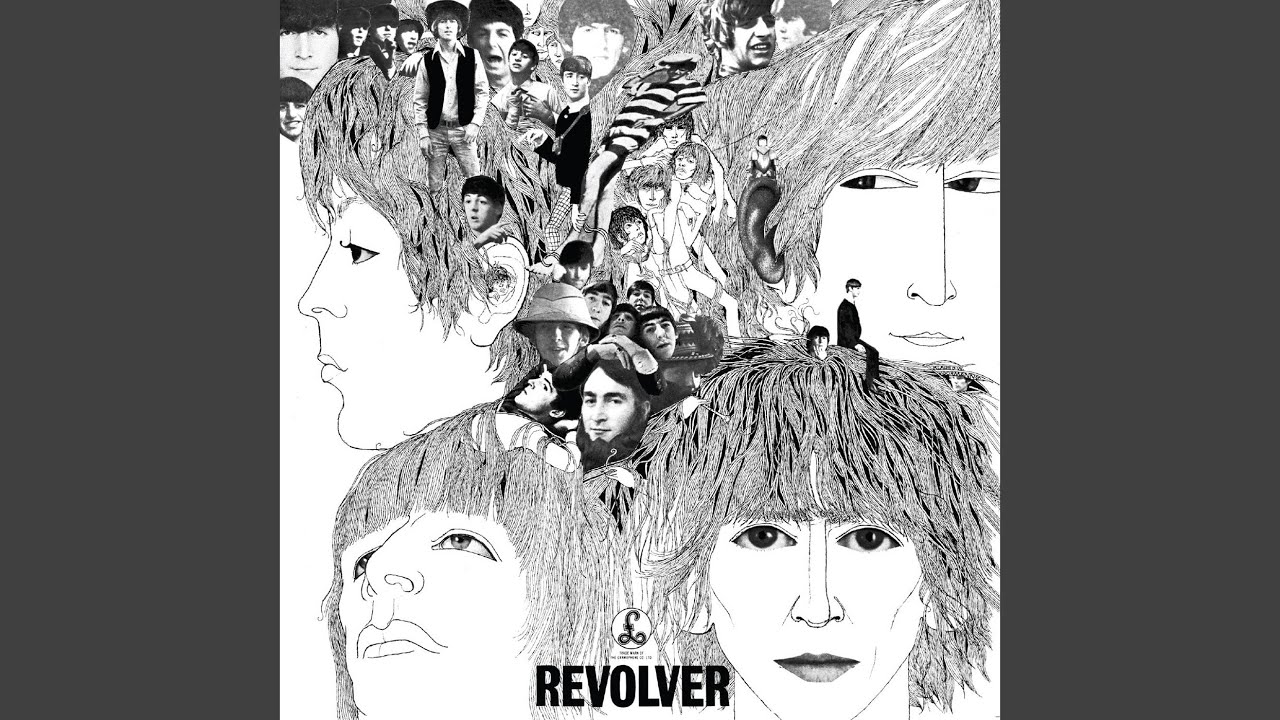●●●●●●●●●●●●●●
★121位
【Do You Want To Know A Secret】
<PLEASE PLEASE ME>1963.3/22=1:56=
デビューアルバム「PLEASE PLEASE ME」に収録された、ジョージVo曲。
ジョージが歌ってはいるけれど、作者はジョンである。
まだ、ジョージのVoの力を認めていなかったジョンは、この狭い音域ならジョージ向きと、自分的には他愛もない曲をジョージに歌わせたのだと思う。
ジョンが言うには、“この曲の自分のボーカルが気に入らなかった。僕はどう歌えばいいか分からなかったんだよ”と言っているが本心であろうか?
しかし、これは、本当に良い曲だと思います。何か、未だに聴いても、夢心地になるというか…。
確かに、中間部は、取って付けたような平凡なパートではあるけれど(このパートは、ポールが作ったような気がする…)。
もちろん、ジョンが歌っていたら、軽くシャウトして、もっと良かったとも思うけれど。
元になっているのは、アニメーション映画「白雪姫」に登場する曲で、ジョンが幼少期に母親のジュリア・レノンに歌ってもらった「I'm Wishing(私の願い)」の影響を受けている。
1963年2月11日に行なわれた10時間に及ぶセッションでレコーディングされたが、録音には6テイクを要した。
ただ、アレンジはシンプルで、簡単なコーラスだけでハモリもなく、演奏も必要以上のことはやっていない。
ポールのベースも半音ズレて間違っている箇所もあるし、ジョージ自体が歌詞を間違えている(“A”を“The”と歌ってしまっている)
しかしながら、アコースティックギター2本の響きは素晴らしく、音も良い。それにリズム感が何ともいえず心地良い。
少し悲しげなイントロから、一転して明るく爽やかな曲調にというのは個人的には大好きな流れで、持っていかれます。
Emから入っての、スパニッシュな雰囲気も大好きだ。
あと、彼等お得意の、そして大好きのクリシェ(半音落ちコード)がすでに、この曲に登場している点も見逃せない。
ポールのベースもランニングしていて、とても効果的だ。
リンゴのスティックを打った音や、Voやコーラスにも、彼等にしては珍しく深いエコーがかかっているのも印象的だ。
アメリカでは、1964年にヴィージェイ・レコードからシングル盤として発売され、Billboard Hot 100で最高位2位を獲得した。
この曲が記念すべきジョージがメインVoを取る、初めてのヒットシングルになったのである。
しかし、ここで歌う「秘密」とは、ブライアン・エプスタインのことだったと知った時の衝撃は…ありましたね。
●●●●●●●●●●●●●●