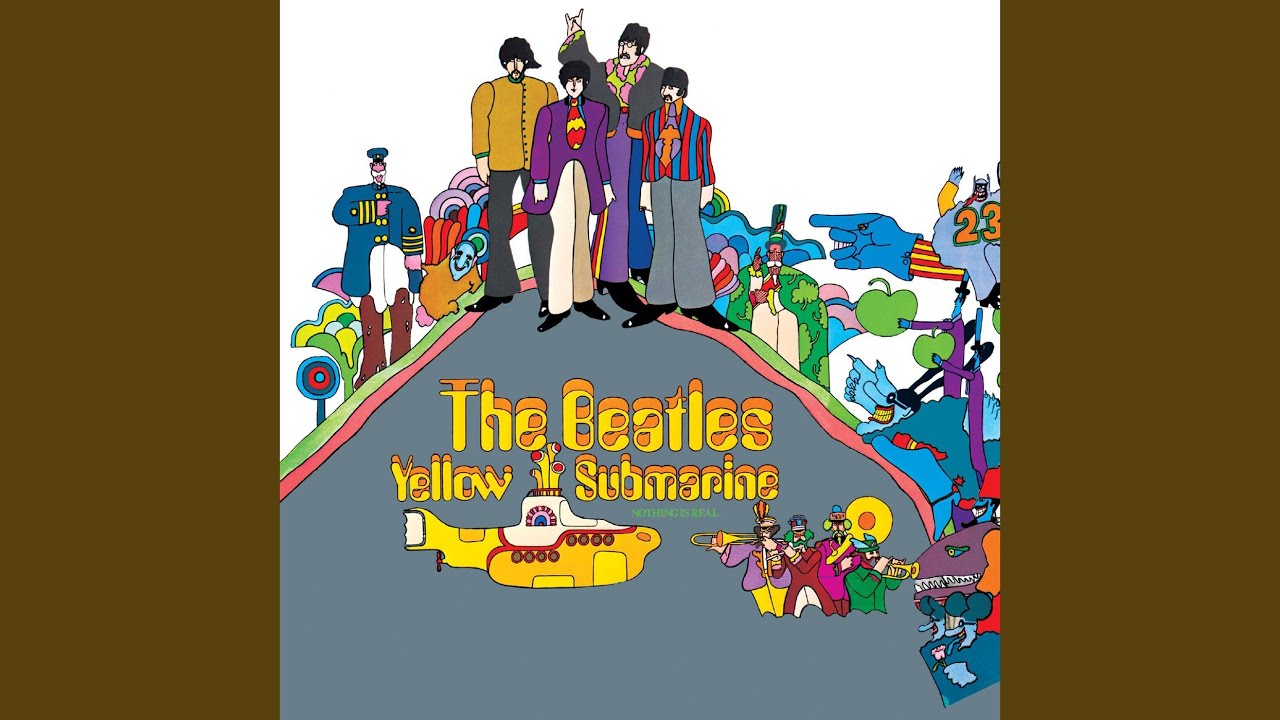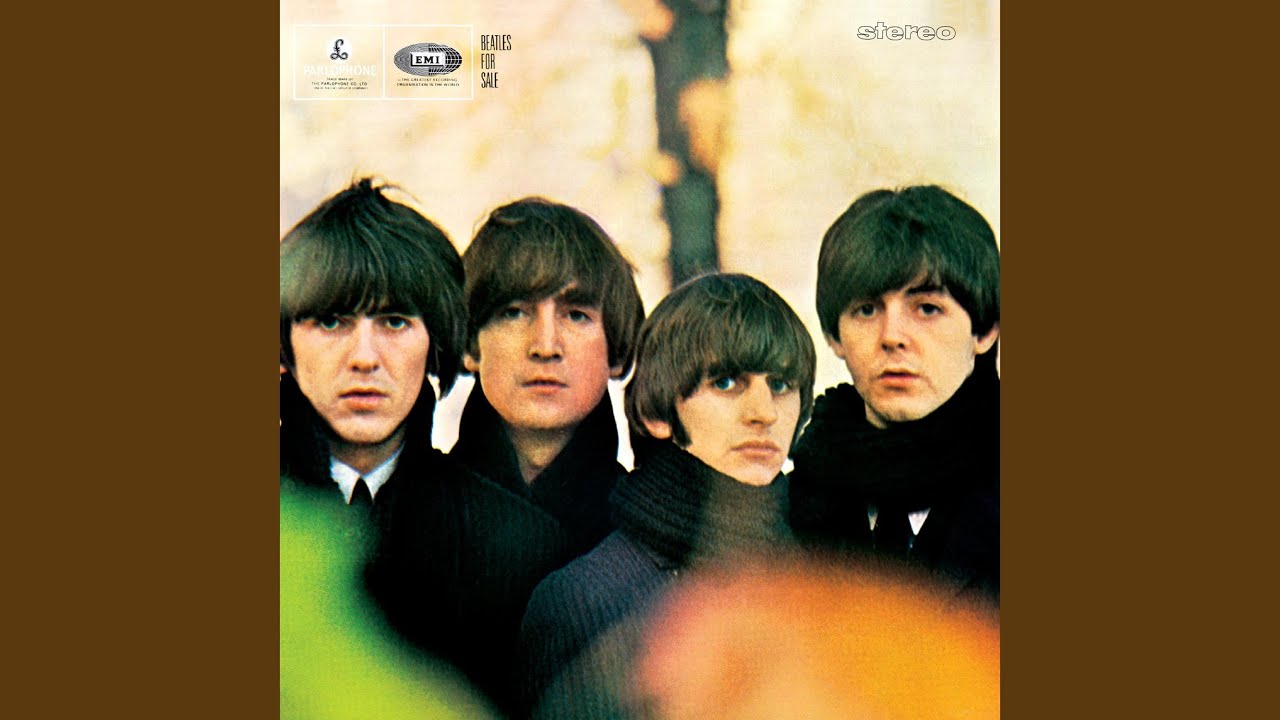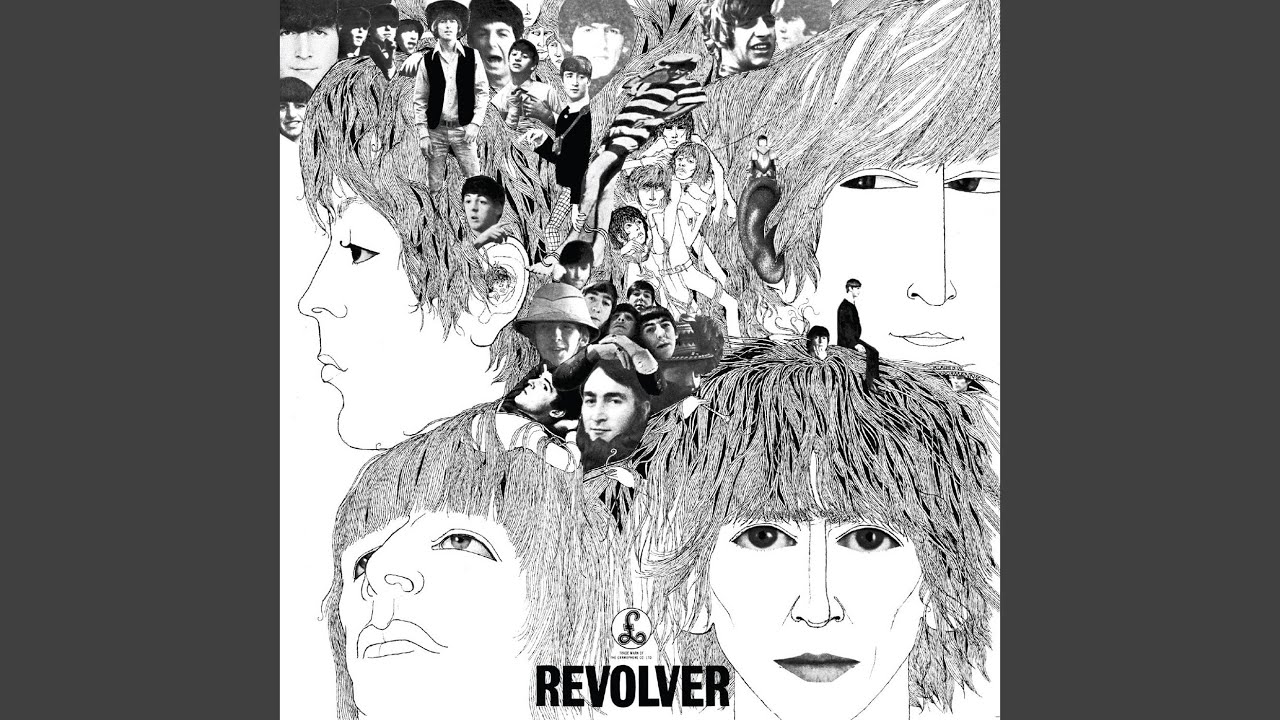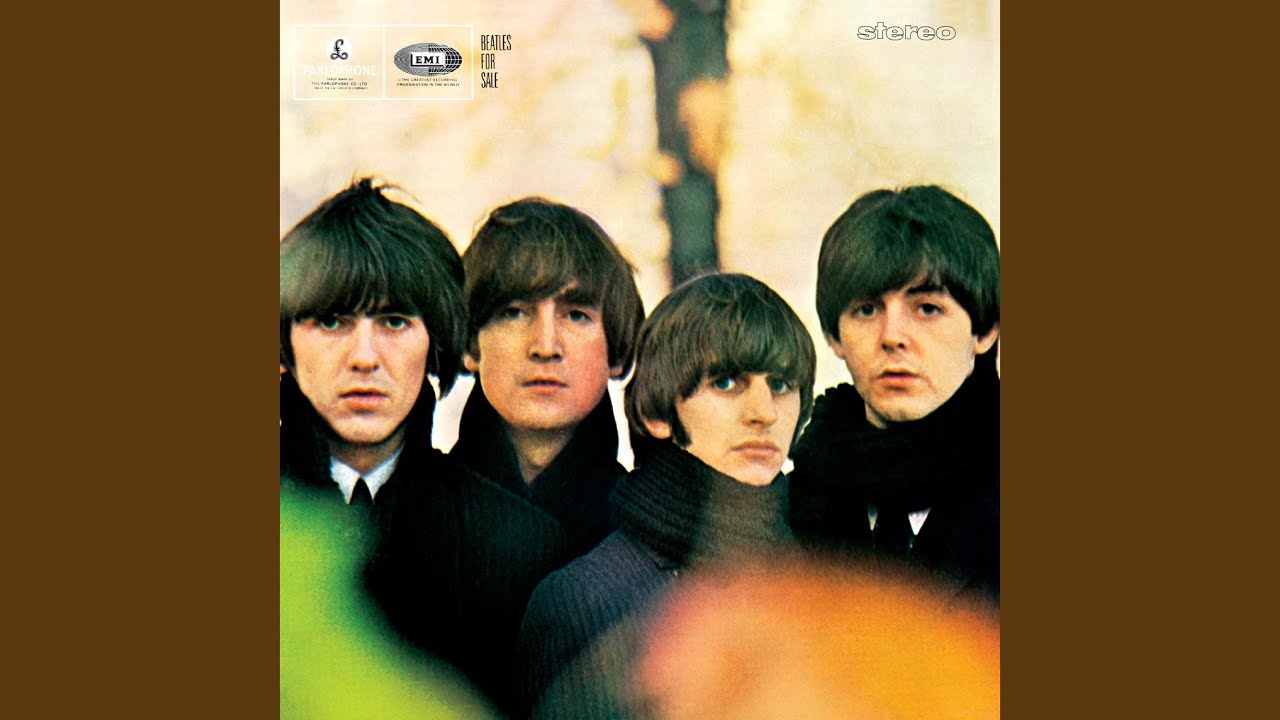★111位
【It's All Too Much】
<YELLOW SUBMARINE>1969.1/17=6:24=
アルバム「Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band」完成直後にジョージが書き上げ、1967年5月にレコーディングされた。
1968年に公開されたアニメーション映画『イエロー・サブマリン』の為にBEATLESが提供した楽曲の1つである。
当初の仮題は「Too Much」。
ジョージは、LSDでの体験を讃える形でこの曲を書いたが、後に超越瞑想で同様の気付きを得たことから、数か月後にヘイト・アシュベリーを訪れた後、LSDを糾弾した。
ビートルズ時代のジョージの曲ではオルガンが使われているのも一つの特徴だと思う。この曲もそうである。
オルガンという楽器そのものが宗教的なイメージを強く持っているからか、ジョージの場合のようにコード弾き的に使う場合、余計にそれが強く感じられるのだ。
ジョージらしい特色と言って良い。
フィードバックを多用するギター、隙間のないオルガン、レガート気味のベース、ラフなシンバルのドラム、多種多様なパーカッション…これらが織りなす重厚なサウンドは他のビートルズの楽曲とは一線を画している。
これは正にREVOLVERの“Tommorow Never Knows”のジョージ版と言えるのかも知れない。
曲の起承転結なしに、アドリブのままレコーディングが進み、最後は混沌としたまま収拾なく続いたものを、後で上手く編集したような印象だ。
名曲中の名曲“Tommorow Never Knows”に及ばないのは、骨格のしっかりとしたものがない部分と、曲の一貫性がないことだろう。
サイケで活力ある曲なのだが、故になのか、それに対するジョージの歌唱力の弱さが浮き彫りになってしまっているのも惜しい。
ただ、個人的にはこの曲への評価は高い。
独特のグルーブ感、サイケの極み、アヴァンギャルドな高揚感は凄い。
不協和音、オフビート…英国アシッドロックの頂点の1つであるとも思う。
一般的にもファン的にも、決して知名度に高い曲ではないが、ミュージシャンからの人気は高く、実は多くのカバーバージョンが存在するのである。
ジョンのシャウトで始まった直後にすぐに入る、強烈なフィードバック。
これはどう見ても聴いてもジミ・ヘンドリックスの影響だ。いや、そのものだ。
つまり、ジミヘンの影響で弾いているというより、ある種のパロディなんだろうと想像する。だって、切り口が彼等にしては余りに捻っていないからだ。
あと、このギターを弾いているのは誰かという問題がある。
ジョージ自身はオルガンを弾いていたので自分ではないと言っている。
ポールはベースで暴れているのでジョンではないかと説と、ジョージ自身がポールだったと思うと発言してるのでポール説がある。
公式には結論は出ていませんが、こう推測します。
バッキングはジョン。曲中のリードはジョージ。頭のジミヘン風はポール。
こう考える方が自然だと解釈します。
●●●●●●●●●●●●●●