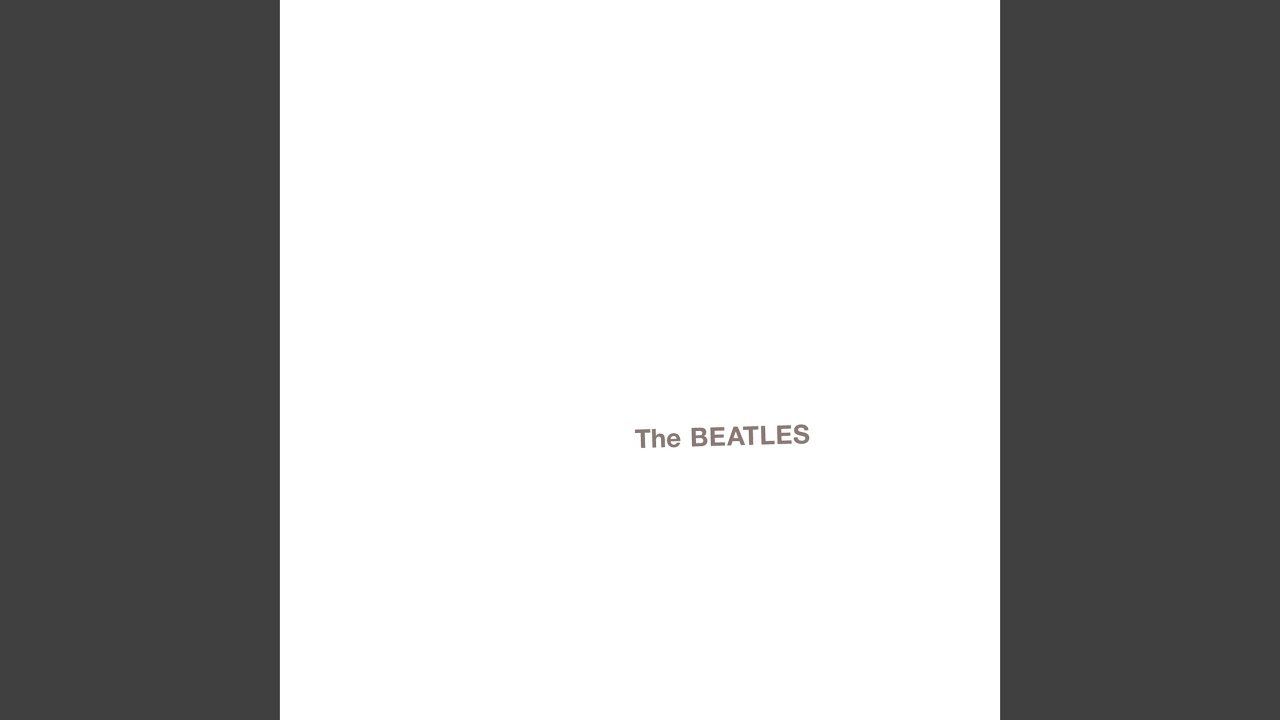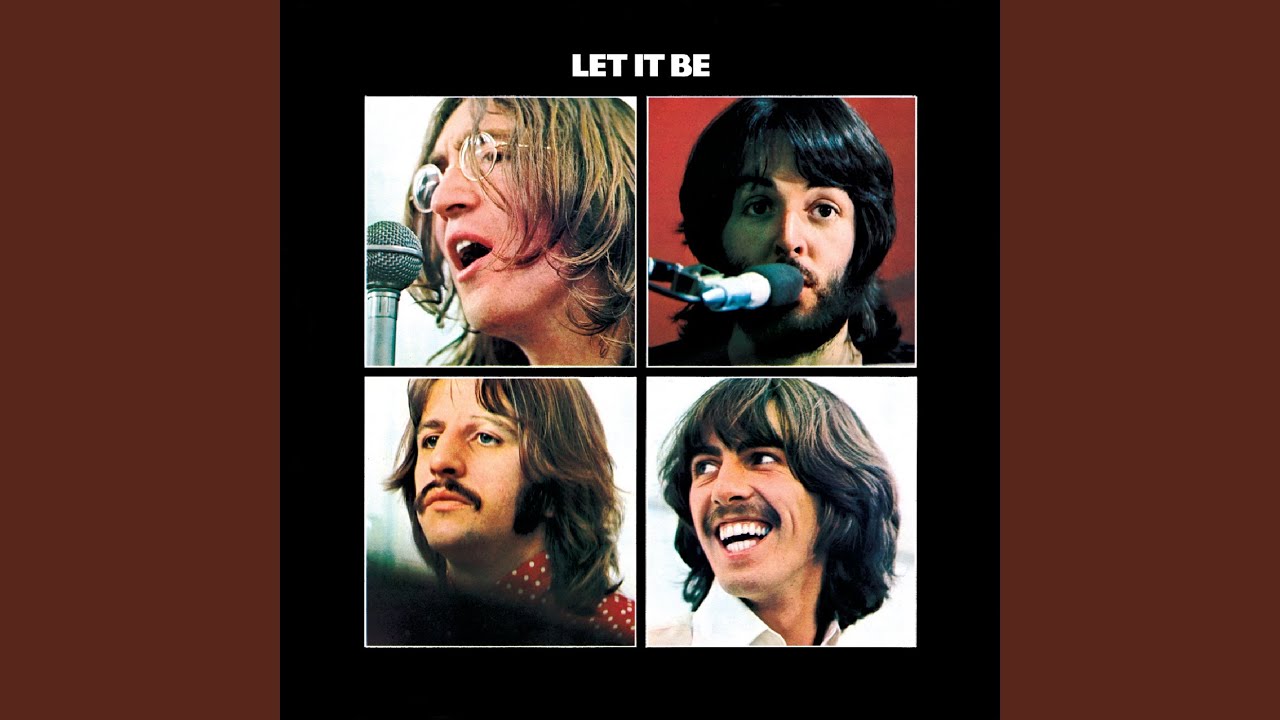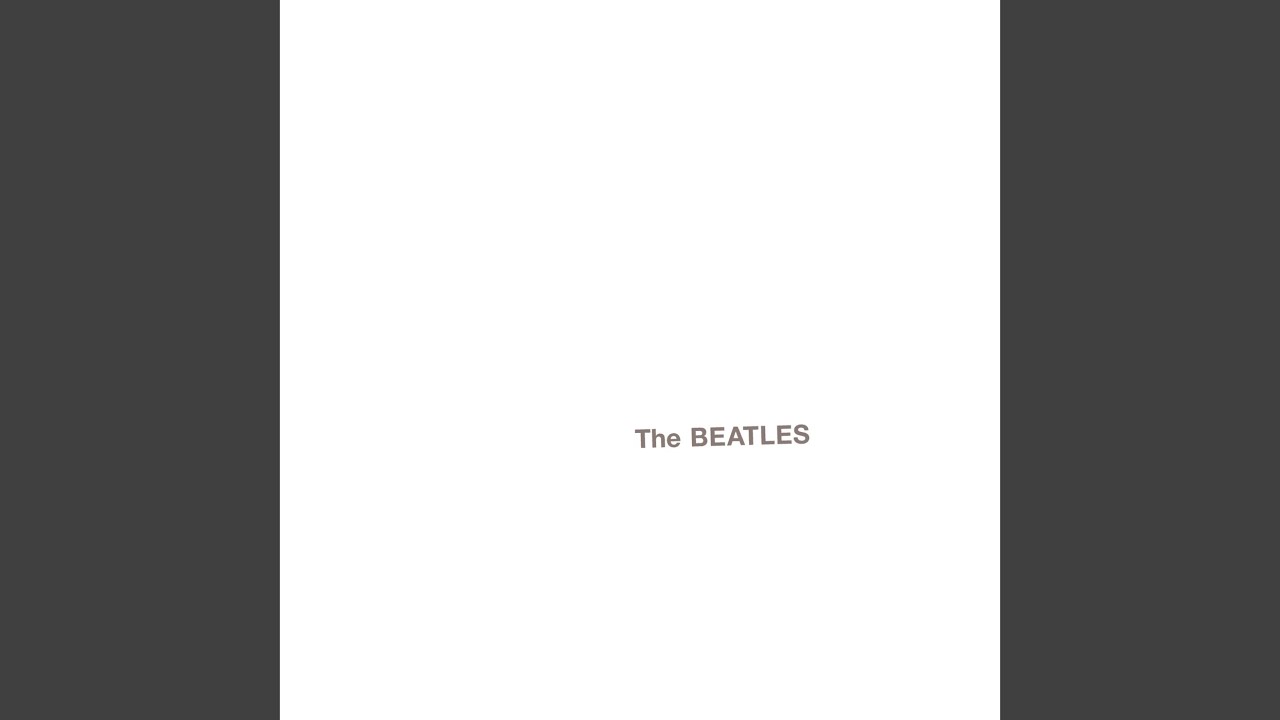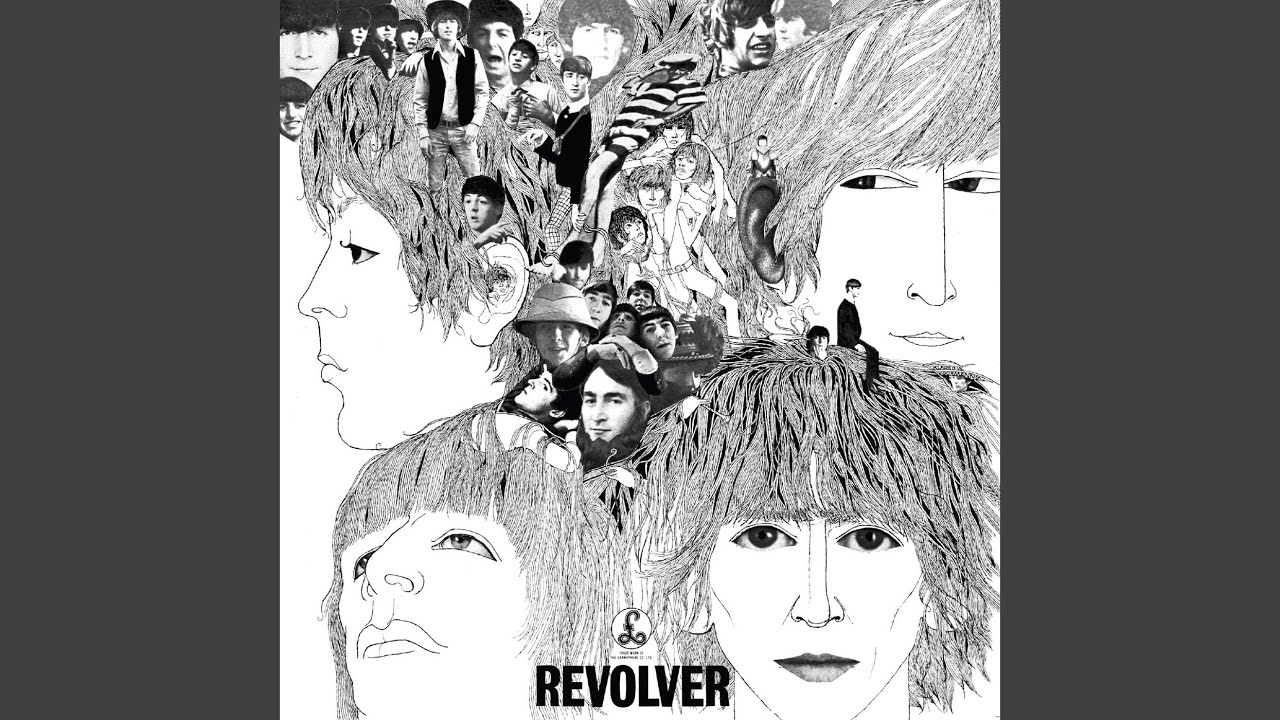★141位
【I'm A Loser】
<BEATLES FOR SALE>1964.12/4=2:30=
アルバム「Beatles For Sale」2曲目で、2曲続けてイントロなしのジョンの渋い声からスタートする楽曲。
しかも、いきなり“僕は負け犬さ”である。
BEATLES…というか、ジョン自身が認めるように、ボブ・ディランの影響を反映した最初の楽曲である。
翌年のフォークロックの流行に向けて、フォークとロックを少しずつ近づけていった流れを作った曲かも知れない。
ただ、楽曲自体は、さほどディランの影響は見受けられない。
内省的な歌詞の最初とも言える曲で、ジョンは、“僕の中の一部は自分が負け犬だと思っている。でも他の一部では、全能の神だと思っているんだ”、と発言があるように、この曲への思い入れが感じられる。
ちなみに、この曲がレコーディングされた1964年8月14日の時には、まだジョンとボブ・ディランは出会っていない。BEATLESとディランが出会うのは、レコーディングから2週間後の8月28日の事である。
録音は、1964年8月14日に行なわれ、同日には“Mr.Monnlight”や“Leave My Kitten Alone”(アウトテイク)」も録音された。
8テイクでレコーディングがは完了した。
(ちなみに、この録音から約2週間後に、ジョンはディランと初対面している)
1回のテイクでVoとリズムギターをレコーディングし、後からハーモニカをオーバーダブしている。
生演奏でジョンは、ハーモニカ・ホルダーを首にかけ、J-160Eを演奏しながら歌ったのだが、この曲を唯一に、それ以降はないので貴重な曲でもあります。
新たなキーボード(後のシンセも)の登場や、メンバー以外の演奏もあったりとしたことが、その理由でしょう。
ジョンは、初の12弦アコースティックギターを弾いている。
コードは、G→Dsus4→Fadd9と進む。つまり、全部、Gの音を押さえている。
ジョージのギターは、テンションコードを上手く使った弾き方だ。何か好きだなぁ、癖になる。
ポールのベースは、4ビートで、ちょっと跳ねるような弾き方をしているのだが、これがなんとも聴いていて心地よい響きである。
ポールは時折、意表を突くような感じで4ビートを奏でるが、この曲もそのセンスの良さがキラリと光っている。
ポールは後年、この曲について、”ジョンは、僕は負け犬だなんて、当時にしては勇気がいるよね“と語っている。
内面を晒すジョン、でも、カッコいい!
●●●●●●●●●●●●●●