学校で劇をする台本は、
言葉選びに慎重になる。
でも、大事なのは、
その言葉をどんな息で伝えたか。
あたたかい息で伝えたら、
言葉が濁った意味を持たないのに。
私は小学校のために、何度か脚本を書いたことがあります。
今も、高槻市の小学校のために、
ミュージカル台本『ピノキオ』を書いているのですが、
学校で上演するためには、
学校の文字コードをパスしなくてはいけません。
それは、学校特有の使ってはいけない言葉、
というものがあるからですが、
最近では、こどもたちが劇のあと、
その言葉で遊ぶ可能性があるからと、
人をからかうようなセリフや、
ちょっと意地悪なセリフは、
往々にしてカットしなくてはならなくなります。
私は、もし、その言葉にこだわりがある場合、
断固、抗議します。
例えば、私は物語の中で、
悪役がきちんと悪役であることを、とても大事にしています。
それは、子どもたちが、悪役を倒す時に、
迷いなく倒す必要があるからです。
そこに、憎めないというよさはあってもいいですが、
いい人かもしれない・・・という、あいまいさを作ると、
こどもが本気で悪を倒せなくなってしまいます。
人の中には、良い部分と悪い部分がある、
だから、それはとても曖昧なものなのだ、
というのは、大人の理屈です。
『さんびきのやぎのがらがらどん』では、
ヤギを食べようとしたトロルが、
最後に大きいヤギに、肉も骨もこっぱみじんにされます。
その言葉を大人が読むと、残酷だとか、
こういう言葉がはやったらいけないとか、
そういう受け止め方になるようです。
でも、子どもからしたらどうでしょう?
行く手を阻む悪い奴を、
大きくなったら自分の手で倒せる、
その良さを全身で感じるにすぎません。
もし、トロルとヤギが仲良くなったら、
(少しオーバーに言えば)こどもは、
悪と手を結ぶ感性を開くことになりかねません。
悪いことは悪い、
そのことを物語を通して学ぶことは大切です。
だから悪役には、悪くなってもらわないといけないのです。
でも、学童に来る子どもが、
劇のセリフを悪用しているのを、
今日耳にして、先生達の気持ちが
少し理解できました。
ナルホド、こういった事態を避けたいわけですね・・・
でも、それは指導した時の
まずさゆえに起きている現象だな…
そのお話しは次回に。
![]() 悪役はきちんと悪役であれ!
悪役はきちんと悪役であれ!![]()
- 三びきのやぎのがらがらどん―ノルウェーの昔話 (世界傑作絵本シリーズ―アメリカの絵本)/著者不明
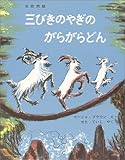
- ¥1,155
- Amazon.co.jp
- 三びきのこぶた―イギリス昔話(こどものとも絵本)/山田 三郎

- ¥840
- Amazon.co.jp
- ちびくろ・さんぼ/ヘレン・バンナーマン
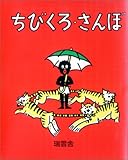
- ¥1,050
- Amazon.co.jp