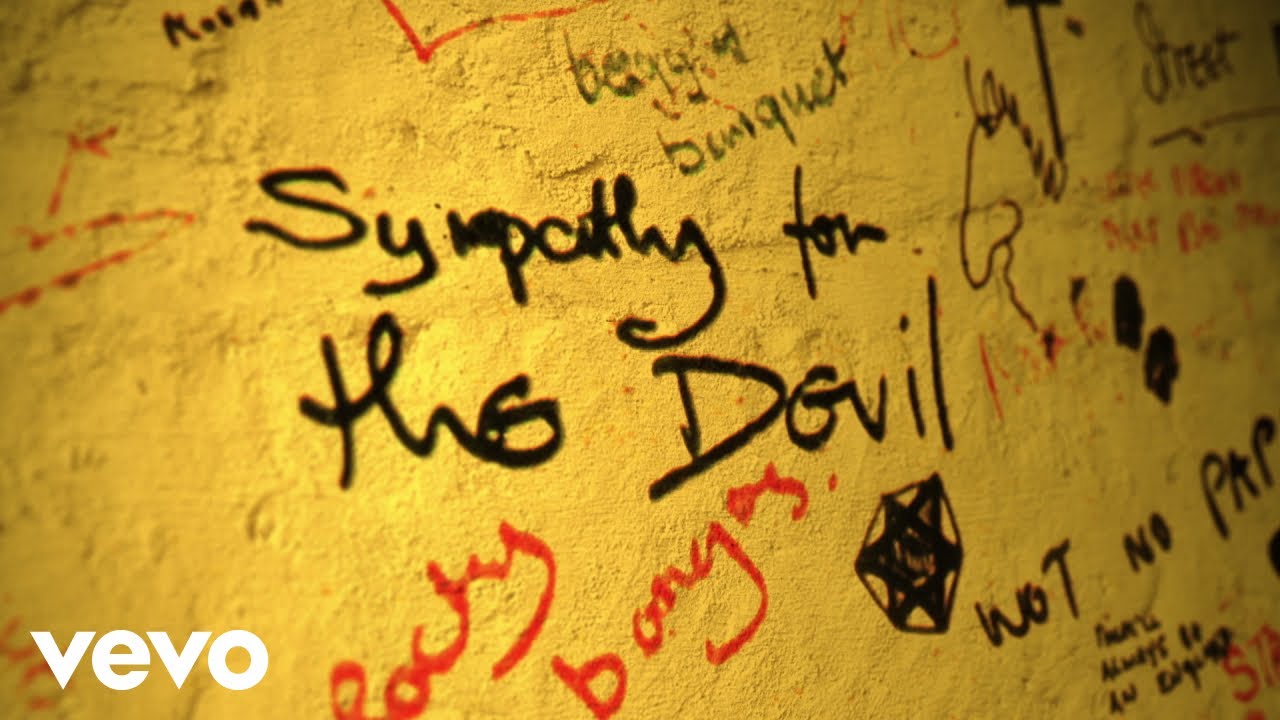Adieu Romantique No.565
『映画と映画音楽について語るときに僕が語ること』
【ヌーヴェル・ヴァーグ編】
僕自身の映画的記憶を呼び覚ますように。断続的に書いているシリーズ記事『映画と映画音楽について語るときに僕が語ること』。その5回目 【ヌーヴェル・ヴァーグ編】。
📖まずは。(いつも都合よく)今、手元にある映画について書かれた一冊の本のことから。今回はヌーヴェル・ヴァーク編ということなので、1964年に単身パリに移住し、ゴダールやトリュフォーが育ったヌーヴェル・ヴァーグの総本山とも言うべき、アンドレ・バザン主宰の批評的映画雑誌「カイエ・デュ・シネマ」に日本人として唯一関わり、翌年(ヌーヴェル・ヴァーグの申し子)ジャン=ピエール・レオ―を介して当時ジャン=リュック・ゴダールが撮影していた『アルファビル』の撮影現場に出入りするようになったという、映画評論家山田宏一の『友よ映画よ わがヌーヴェル・ヴァーグ誌』。そう、僕的には、ヌーヴェル・ヴァーグの聖典であり、映画について書かれたものの中で最も愛すべき本でもあり、この一冊をヌーヴェル・ヴァーグの作品の1本に加えてもいいとさえ思っているほど![]() 。
。
山田宏一には他にも『映画的なあまりに映画的な美女と犯罪』や『ゴダール、わがアンナ・カリーナ時代』、『シネ・ブラボー』3部作(ハワード・ホークスが撮った傑作『リオ・ブラボー』へのリスペクト!)『山田宏一のフランス映画誌』、『山田宏一の日本映画誌』など、いずれも、映画的な、あまりに映画的な数多くの本を書いていて、どの本においてもそのすべてから映画に対する熱烈な「映画愛」を感じ取ることができる。
🎦まずは。ジャン=リュック・ゴダール【Jean-Luc Godard】が1959年に撮った長編デビュー作『勝手にしやがれ』【A Bout De Souffle】から。
過去の映画的文脈から逸脱し、かつて誰も観たことがなかった、まるで感覚だけが疾走し、暴走しているかのような、ワガママで気紛れで、そして自由で。とても魅力的なこの映画は、熱狂と共に迎え入れられ、誕生して間もない『ヌーヴェル・ヴァーグ』【Nouvelle Vague】という言葉と共に世界に衝撃を与えた。
🎬️映画は、主人公のミシェル・ポワカール (ジャン=ポール・ベルモンド)のこんな台詞から始まる。
![]() 「Apres Tout , Je suis Con」【結局、俺ってアホだ】。
「Apres Tout , Je suis Con」【結局、俺ってアホだ】。
🎦ミシェルとパトリシア(ジーン・セバーグ)の、可愛くって、とてもロマンティークなシーンを。
🎬️そして、ラスト・シーンでは。自動車泥棒を繰り返したミシェルと親密な関係にあったパトリシアの密告により警官の凶弾に倒れたミシェルが次のような台詞を吐いて息絶える。
![]() 「c'est vraiment dégueulasse」【ほんと最低だ】。
「c'est vraiment dégueulasse」【ほんと最低だ】。
パトリシアが警官に聞く。
![]() 「Qu’est-ce qu’il a dit ?」【彼は何て言ったの?】。
「Qu’est-ce qu’il a dit ?」【彼は何て言ったの?】。
警官が(ミシェルの言葉の真意を湾曲し適当に)答える。
![]() 「Il a dit : Vous êtes vraiment une dégueulasse」
「Il a dit : Vous êtes vraiment une dégueulasse」
【あなたはほんと最低な女だ、と】。
パトリシアが言う。
![]() 「Qu’est ce que c'est dégueulasse?」
「Qu’est ce que c'est dégueulasse?」
【最低って、何のこと?】。
fin
「最低」な汚い言葉で始まり、「最低」な汚い言葉で終わる最高の映画。その価値や真の意味は、この映画を観たひとりひとりの中にこそ残るべきだと思う。この映画以降、現在に至るまで。フランス映画には結末がなく、よく言えば「考えさせられる」、悪く言えば「よく分からないままに終わる」というイメージが定着するようになったのかも知れない。いずれにしても。「勝手にしやがれ ! !」。
![]() 音楽を担当した、フランスのジャズ・ピアニストであり、コンポーザーであるマーシャル・ソラール【Martial Solal】によるテーマ曲『Duo』。この映画にこの音楽ありき。スタイリッシュで恐ろしくカッコいい。
音楽を担当した、フランスのジャズ・ピアニストであり、コンポーザーであるマーシャル・ソラール【Martial Solal】によるテーマ曲『Duo』。この映画にこの音楽ありき。スタイリッシュで恐ろしくカッコいい。
因みに。山田宏一の『友よ映画よ わがヌーヴェルヴァーグ誌』によると。まだ誰にも知られていなかった頃の映画作家ゴダールは、初めての長編『勝手にしやがれ』を制作するに当たってブリジット・バルドーの『素直な悪女』などを撮り、当時、イケイケ、モテモテの映画作家であったロジェ・ヴァデムを訪ね、「あなたの奥さんアネット・ストロイベルグに、と思う役があるのですが」と説明し、「男は与太者。アメリカ映画のヒーローたちのイメージに取り憑かれている。女には訛りがある。「ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン」を売っている」。本当の恋愛ではなくて、錯覚である。結果はよくない。結局のところ終わりはいい。あるいは終わりは悪い」というマッチ箱に走り書きをしただけの『勝手にしやがれ』のシナリオを渡したものの本人に「ばかにしないで」と一蹴されたというエピソードが書かれている。まさにヌーヴェル・ヴァーグの始まりに相応しい、何て素敵な話だろうか、と思う。
「ヌーヴェル・ヴァーグ」は、文字通り過去の映画に対する批評的精神と「映画愛」から生まれた。「ヌーヴェル・ヴァーグ」の中心にいたのは、もともと「シネフィル」(=映画狂)と呼ばれ、いくつかの映画雑誌に映画批評を寄稿していたゴダールを始め、フランソワ・トリュフォー、クロード・シャブロル、ジャック・リヴェット、エリック・ロメールら。彼らは過去の映画を辛辣に批評し、徹底的に攻撃したけれど、逆に自分たちが認める映画作家やその作品に対しては一貫して擁護し、限りないオマージュを捧げた。
映画に愛を込めて。ヌーヴェル・ヴァーグの作家たちは、映画は映画作家のものであるという前提に立った「作家主義」を標榜し、偉大なる映画作家たちを敬愛した。オーソン・ウェルズ、フリッツ・ラング、F・W・ムルナウ、ジャン・ヴィゴ、ジャン・ルノワール、エルンスト・ルビッチ、ハワード・ホークス、溝口健二、ロベルト・ロッセリーニ、ロベール・ブレッソン、アルフレッド・ヒッチコック……。僕のブログで映画を紹介する時に映画監督(つまり映画作家)の名前を必ず出すのは僕自身もこの「作家主義」を標榜しているからであり(いや、そんな偉そうなものじゃない)、映画は俳優よりも(いやいや、俳優の魅力ももちろん捨てがたいけど)、一般的な評価よりも(それはほとんど気にならない)映画作家で観ることが多いから。
ヌーヴェル・ヴァーグの映画制作は、資金面の問題もあり、カメラをスタジオの外に持ち出し、パリの街角でラウル・クタールやアンリ・ドカエら、後にヌーヴェル・ヴァーグに欠かせないカメラマンたちによって即興的に撮られることが多かったけれど、そのおかげで逆にヌーヴェル・ヴァーグはリアリティや独特のリズムを獲得し、独自の魅力を生み出していく。
そしてヌーヴェル・ヴァーグの音楽のこと。ヌーヴェル・ヴァーグの映画作家たちは自身の映画にクラシック音楽を頻繁に使う。ベートーベン、モーツァルト、ワーグナー、ビバルディなどなど。彼らは映画に対する偏愛だけではなく音楽に対する嗜好も強かった(ついでに言えば女優に対する、つまり女性に対する偏愛も)。既成の音楽だけではなく、オリジナル音楽を時に映画的な感情を喚起するために流したり、時に映画の中で主演女優に歌わせたりしながら♪
🎦1961年の、ゴダール初のカラー作品『女は女である』【Une Femme est Une Femme】は、アメリカのミュージカル映画へのオマージュだった。
![]() 音楽はミシェル・ルグラン【Michel Legrand】。劇中、主役のアンジェラ(アンナ・カリーナ)が歌う『Chanson d'Angela』を。
音楽はミシェル・ルグラン【Michel Legrand】。劇中、主役のアンジェラ(アンナ・カリーナ)が歌う『Chanson d'Angela』を。
🎦ゴダールが撮った(非商業主義的)娯楽大作『軽蔑』【Le Mepris】。真っ白な部屋に真っ赤なソファを配し、当時の大スター、B.Bことブリジット・バルドーが裸で寝そべっているシーンはスタイリッシュの極み。ゴダールにこんな魔法をかけられた「映画」は何て「幸福」なんだろう。
ゴダールの映画は過去から現在まで難解だと言われ続けてきた。僕自身も「あなたはどこまでゴダールの映画を理解してるか」なんて問われてもまったく自信がない。「だから何?」、「So What?」。僕にとってゴダールの映画は(いろんな意味で)文句なくカッコいい。それだけで十分だ。
🎦既にアンナ・カリーナとゴダールの愛は冷めていた、そんな時期に(1965年に)ゴダールは最高傑作『気狂いピエロ』【Pierrot De Fou】を生み出した。ベラスケスで始まり、ランボーで終わる映画。この作品では、世界観が全体的にあっち側の世界に向いており、アンナ・カリーナもまた狂気を孕んだ別次元の存在になっているように見える。山田宏一は『友よ映画よ わがヌーヴェル・ヴァーグ誌』の中で、この映画のアンナ・カリーナについてこんなことを書いている。「マリアンヌ・ルノワールを演じたアンナ・カリーナは、或いはアンナ・カリーナが演じたマリアンヌ・ルノワールは、フェイドアウトのまったくないカットでシーンが閉じられるまぎわに、もう二度と彼女には会えないのではないかと思わせるような、深い、暗い、絶望的な視線をキャメラの方に投げかけるのだった」と。
🎬️『気狂いピエロ』の名場面集。
![]() 音楽はアントワーヌ・デュアメル【Antoine Duhamel】。劇中、マリアンヌ(アンナ・カリーナ)が『私の運命線』【Maligne De Chance】を歌うシーンを。
音楽はアントワーヌ・デュアメル【Antoine Duhamel】。劇中、マリアンヌ(アンナ・カリーナ)が『私の運命線』【Maligne De Chance】を歌うシーンを。
ゴダール以外の。映画的な、あまりに映画的な作品と音楽をいくつか。
🎦フランソワ・トリュフォー【Francois Truffaut】の1961年の傑作『突然炎のごとく』【Jules et Jim】。ジュール(オスカー・ウェルナー)とジム(アンリ・セール)、そしてカトリーヌ(ジャンヌ・モロー)の微妙な三角関係が描かれ、ジャンヌ・モローは「女そのものである女」の性を実に魅力的に演じていく。ちながら。この映画のラストではカトリーヌが盟友ジャック・リヴェットの作品のタイトルを叫ぶシーンがある。「Paris Nous Appartient !」【パリはわれらのもの!】。愛と友情に溢れた、素敵な引用だと思うな。
![]() 映画の中でジャンヌ・モローが『Le Tourbillon』【つむじ風】を歌うシーン。ギターを弾いているのは作曲者のボリス・バシアク。とても親密な、ヌーヴェル・ヴァーグ的なシーンだと思う。
映画の中でジャンヌ・モローが『Le Tourbillon』【つむじ風】を歌うシーン。ギターを弾いているのは作曲者のボリス・バシアク。とても親密な、ヌーヴェル・ヴァーグ的なシーンだと思う。
そして。トリュフォーはその10年後に、この映画の愛の構図を二人の女性とひとりの男性に置き換え、ジャン=ピエール・レオー主演で『恋のエチュード』を撮ることになる。
🎦パリの街角の電話ボックスでジャンヌ・モローの「ジュ・テーム」という台詞から始まる(電話の相手はモーリス・ロネ)ルイ・マル【Lois Mar】が1957年に撮った、ヌーヴェル・ヴァーグの先駆的作品『死刑台のエレベーター』【Ascenseur pour I'echafaud】。
![]() 音楽はジャズの帝王マイルス・デイヴィスが完成したフィルムに即興で合わせる形でトランペットを吹いた。
音楽はジャズの帝王マイルス・デイヴィスが完成したフィルムに即興で合わせる形でトランペットを吹いた。
📷️マイルス・デイヴィスとジャンヌ・モローのオフ・ショット。
ルイ・マルは『鬼火』(1963)でエリック・サティ、『ルシアンの青春』(1974)ではジャンゴ・ラインハルトの音楽を使うなど、特に音楽への拘りが強かった。
🎦ジャック・ドニオル=ヴァルクローズ【Jacques Doniol-Valcroze】が1959年に撮った『唇によだれ』【Leau a la Bouche】の主題歌を書き、歌ったのはセルジュ・ゲンスブール【Serge Gainsborough】だった。
🎦そして最後にもう一度、ゴダールの作品を。最もヌーヴェル・ヴァーグ的ではない俳優アラン・ドロンを主役に抜擢した作品はその名も『ヌーヴェル・ヴァーグ』(1990)。ドイツのジャズ・レーベル「ECM」の音源をレーベルの主宰者のマンフレッド・アイヒャーから提供されたゴダールはその音楽をズタズタに切り刻みながら、俳優たちの言葉もあらゆるノイズも「音響」として編集し、映画における音楽の役割や意味を破壊し、映画における音楽に新しい役割や意味を与えた。