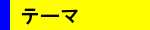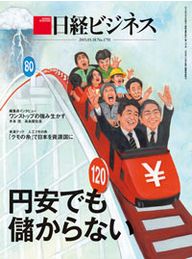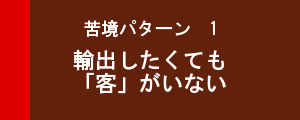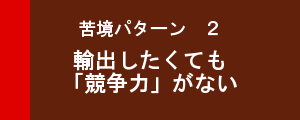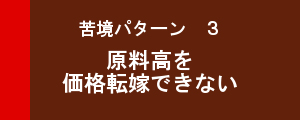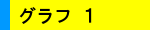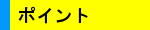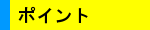『マキアヴェッリ語録』 塩野七生 新潮文庫
平成4年11月25日 発行
目次
第1部 君主編
第2部 国家編
第3部 人間編
マキアヴェッリ(日本ではマキャベリと表現されることが多い)
は『君主論』の著者として知られ、「マキャベリズム」が
人口に膾炙しています。
その思想を端的に表現する言葉は、
「目的は手段を正当化する」
です。
目的のためならどんな手段を講じてもかまわない、と解する
ことが多いですね。
実は、私もこの書を読むまではそのように解釈していました。
言葉を文脈の中で解釈せず、言葉が独り歩きすることの怖さは、
風説の流布でも経験することです。
福島第一原発事故以後、周辺にお住まいの方々は風説の流布
に悩まされ続けています。拡散した誤情報はさらに誤情報を加え、
拡大していきます。容易に訂正されることはありません。
話しを戻しますと、マキアヴェッリの実像はどのようなもので
あったのか、そして「目的は手段を正当化する」と言っている
ことの真意は何だったのか、を知りたいと思いました。
先入観を取り払い、大前研一さんが言う、「オールクリア
(電卓のAC)」にしてマキアヴェッリの説くことに耳を傾ける
ことにしました。
マキアヴェッリは、1469年5月3日にイタリアのフィレンツェで
生まれ、1527年6月21日に没しています。15世紀から16世紀
にかけて活躍した思想家です。500年位前の人です。

塩野七生(しおの・ななみ)さんは、「まえがき」に代えて
「読者に」で次のように記しています。塩野さんが解説
ではなく、また要約でもなく、「抜粋」にした理由を説明
しています。
尚、10ページ以上にわたる説明からポイントとなる言葉を
「抜粋」しました。
(前掲書 「読者に」から PP.3-5、14)
この『マキアヴェッリ語録』は、マキアヴェッリの思想の
要約ではありません。抜粋です。
なぜ、私が、完訳ではなく、かといって要約でもなく、
ましてや解説でもない、抜粋という手段を選んだのかを
御説明したいと思います。
第一の理由は、次のことです。
彼が、作品を遺したということです。
マキアヴェッリにとって、書くということは、生の証[あか]し、
であったのです。
マキアヴェッリは、単なる素材ではない。作品を遺した
思想家です。つまり、彼にとっての「生の証し」は、今日
まで残り、しかもただ残っただけではなく、古典という、
現代でも価値をもちつづけているとされる作品の作者でも
あるのです。生涯を追うだけで済まされては、当の彼自身
からして、釈然としないにちがいありません。
抜粋という方法を選んだのには、「紆曲」どころではない
マキアヴェッリの文体が与えてくれる快感も、味わって
ほしいという私の願いもあるのです。そして、エッセンスの
抜粋ならば、「証例冗漫」とだけは、絶対に言われない
でしょう。
しかし、彼の「生の声」をお聴かせすることに成功した
としても、それだけでは、私の目的は完全に達成された
とはいえないのです。マキアヴェッリ自身、実際に役に立つ
ものを書くのが自分の目的だ、と言っています。
マキアヴェッリの名言をご覧ください。
第1部 君主編
君主にとって、厳重のうえにも厳重に警戒しなければ
ならないことは、軽蔑[けいべつ]されたり見くびられ
たりすることである。
―― 『君主論』 ――
(P.88)
(013-1-0-000-490)
君主にとっての最大の悪徳は、憎しみを買うことと
軽蔑されることである。
それゆえに、もしもこの悪徳さえ避けることができれば、
君主の任務は、相当な程度にまっとうできるであろうし、
他に悪評が立とうと、なんら怖[おそ]れる必要はなく
なる。
古今東西、人間というものは、自分自身のもちものと
名誉さえ奪われなければ、意外と不満なく生きてきた
のである。
一方、軽蔑は、君主の気が変わりやすく、軽薄で、
女性的で、小心者で、決断力に欠ける場合に、
国民の心中に芽生えてくる。
自分の行うことが、偉大であり勇敢であり、
真剣で確固とした意志にもとづいていると見えるよう、
努めねばならないのだ。
―― 『君主論』 ――
(P.89)
(014-1-0-000-491)
人の上に立つ者が尊敬を得るには、どのように行動
したらよいかについての考察だが、なによりもまず
第一に、大事業を行い、前任者とはちがう器である
ということを、人々に示すことであるとわたしは言い
たい。
なぜなら、大事業を行えば、しかもそれが次々と
為されれば、人々は呆気[あっけ]にとられて感嘆
してしまい、他のことに心を使う暇も気も失ってしまう
からである。
第二は、敵に対する態度と味方に対する態度を、
はっきりと分けて示すことである。人の上に立つ者が
この種の明快さを示すとき、人々は彼を尊敬するように
なる。
―― 『君主論』 ――
(P.91)
(015-1-0-000-492)
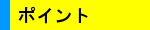
時と場合によって、君主(リーダー)たる者は「はったり」を
かますことも必要である、ということです。
ただただ馬鹿正直に発言し、行動していては軽蔑される
だけだ、とマキアヴェッリは教えている、と解釈しました。
マキアヴェッリは直截的にビシッと言い放つため、
不快感よりもむしろ爽快感を与えてくれます。
曖昧な表現を極力避け、ストレートに話す態度は自信の
現れであり、一面、傲慢のように見えますが、その態度を
貫き通すことができれば、尊敬されるようになる、と言えます。

「自分の行うことが、偉大であり勇敢であり、
真剣で確固とした意志にもとづいていると見えるよう、
努めねばならないのだ。」

「敵に対する態度と味方に対する態度を、
はっきりと分けて示すことである。人の上に立つ者が
この種の明快さを示すとき、人々は彼を尊敬するように
なる」
マキアヴェッリは人間の本質的な側面をえぐり出して、
白日の下に晒す類まれな人物だった、と想像できます。
戦略家であり、優秀な参謀であり、心理学者であり、
歴史学者であり、哲学者と言ってもよいくらいです。
藤巻隆(ふじまき・たかし)オフィシャルブログ-
人気のブログランキング
こちらのブログやサイトもご覧ください!
こんなランキング知りたくないですか?
中高年のためのパソコン入門講座(1)
藤巻隆のアーカイブ
本当に役に立つビジネス書