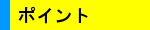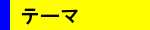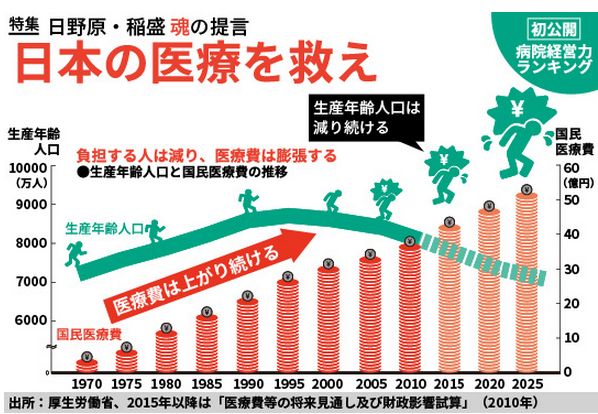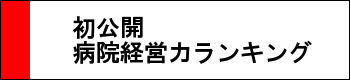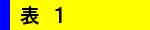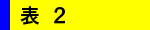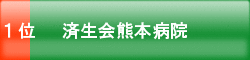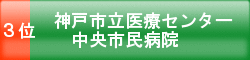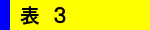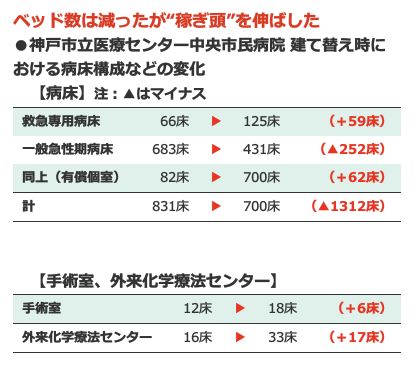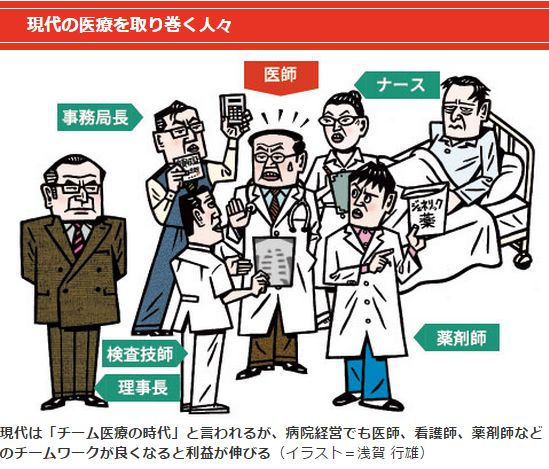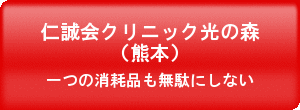その意見を聞かなければ
経営の判断を誤る
野木森 雅郁(のぎもり・まさふみ)氏
[アステラス製薬会長]

旧山之内製薬と旧藤沢薬品工業が合併して
アステラス製薬が誕生して、この4月に10周年
を迎えました。
私が手にしているのは、合併のアドバイザーを
務めた会社から贈られた、「ツームストーン」と
呼ばれる記念品です。
社長に就任したのは、合併から1年余りしかたって
いない2006年6月。
社長になって肝に銘じたのは、自ら心がけ、周囲
にも求めてきた「現場主義」の遂行です。
現場主義といっても、よく言われる3現主義、
すなわち、「現場」に出向いて「現物」に直接触れ、
「現実」をとらえるといったものではありません。
日々訪れる意思決定の局面で、現場を最もよく
知っている人の意見を聞き、それをベースに判断
するというものです。
企業ではポジションが上になるほど、権限が
大きくなり、自分で決められる範囲が広がります。
自己顕示欲の強い人は部下の意見を聞かずに、
自分だけの考えで判断を下そうとしがちです。
それではダメでしょう。
どの会社でも同じだと思いますが、大きな組織には
いろいろな能力を持った人が集まっています。
そうした人を生かさなければならない。
その意味でも、意思決定を求められる時には、
有能で、かつ懸案について実情を最もよく知っている
人の意見を聞く。
その姿勢を社長になってからも続けようと改めて胸に
刻み、実行してきました。
同じような人間ばかりではやれることは限られると。
部下も自分と息が合う人ばかりを選んではいけないんだ
と痛切に思いました。
(2015.06.08 号から)
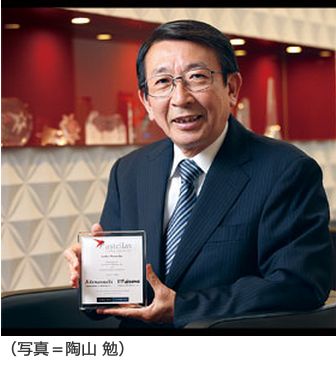
「日経ビジネスDigital」 2015.06.08

キーワードは、 現場の意見 です。
私は、最初、3現主義を思い浮かべていました。
「現場」「現物」「現実」です。
現場に足を運び、現物を見て、現実を確認する、
直視するというものです。
ところが、野木森さんは3現主義のことではない、
ときっぱり発言しました。
「現場主義といっても、よく言われる3現主義、
すなわち、『現場』に出向いて『現物』に直接触れ、
『現実』をとらえるといったものではありません」。
現場をよく知っている人の意見をよく聞くことだ大事
だ、と述べています。
どの会社でも似たようなものでしょうが、本社勤務
の人たち(お偉いさん?)は現場から最も遠い存在
で、現場のことは現場からのレポートを読んで知って
いる程度であるにもかかわらず、すべて把握している
と勘違いしているケースが多々あります。
私は過去、6業種6企業(商社、自動車業界、出版業界、
建設業界、和菓子業界、介護業界)に勤務した経験が
ありますが、どこも同じようなものでした。
職種は経理と営業、在庫管理の3つですが、経理が最も
長く、通算で約26年、営業が6年、在庫管理が1年半です。
本社の人間は自分たちの方が、現場の人間より優秀で
あることを鼻にかけ、威張って見せるだけで、現場のこと
をほとんど理解しようとしませんでした。
ですから、現場の本質的な問題(=全社的な問題)が、
何一つ理解できず、解決できなかったのです。
私は、現場も本社勤務も経験しましたので、両方の立場
の違いと実態が掴めました。残念ながら、十分な成果に
結びつけることはできませんでしたが・・・・・。
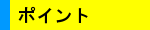
ポイントは、
本部、本社は現場から最も遠いロケーション
です。
この言葉の意味は、物理的にも心理的にも現場から
最も遠い場所に位置している、ということです。
現場責任者は、本社の方を向いて仕事をしている
ケースがあるため(本社勤務を希望しているため?)、
現場の実情を率直に伝えることができていないことが、
ままあります。
本社側の人間は、上から目線で、一方、現場側の人間
は劣等感から面従腹背するか、むやみに反発するか、
のどちらかの態度を示します。
本社の意見をすべて受け入れ、従順な態度を示すだけ
が現場の人間がすることではありません。
現場を知悉するからこそ、現場の意見を率直に述べる
ことができなければ、また本社はそうした雰囲気を醸成
できなければ、真の問題解決には至らないでしょう。
本社は、間接部門ですから、利益にほとんど貢献して
いないことをもっと自覚するべきです。
現場が利益を生み出しているのです。
売上や利益の源泉は現場にあることを、もう一度、
考え直してみる必要があります。
藤巻隆(ふじまき・たかし)オフィシャルブログ-
人気のブログランキング
こちらのブログやサイトもご覧ください!
こんなランキング知りたくないですか?
中高年のためのパソコン入門講座(1)
藤巻隆のアーカイブ
本当に役に立つビジネス書