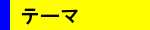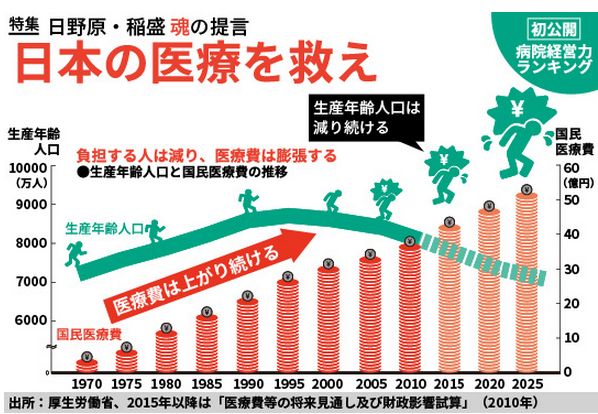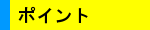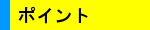大前研一さんは、私にとってメンターでもあり、
グールー(思想的指導者)の存在でもあります。
大前さんの著作を読んでいつも感じるのは、
物事の本質を捉えるずば抜けた能力です。
凡人である私は大前さんの足元にも及びませんが、
不断の努力を怠らず、一歩でも彼に近づきたい、
と思っています。
サラリーマン再起動マニュアル
2008年10月4日 初版第1刷発行 小学館
ISBN978-4-09-379454-1

目次
[イントロダクション]志のあるサラリーマンは、
きつい仕事を厭わない
第1章[現状認識]なぜ今「再起動」が必要か?
第2章[基礎編]「再起動」のための準備運動
第3章[実践編]「中年総合力」を身につける
第4章[事業分析編]“新大陸エクセレントカンパニー”の条件
第5章[メディア編]「ウェブ2.0」時代のシー・チェンジ
[エピローグ]新大陸の“メシの種”はここにある
[エピローグ]新大陸の“メシの種”はここにある
少子高齢化時代のビジネス新大陸では、
企業は「内向き・下向き・後ろ向き」になったら
必ず衰退する。
日本国内にいて少しぐらい商品を改良してみても、
どうにもならない。
既存市場で生き残っていこうと思ったら、
よほどの奇抜な企画力で付加価値の高い商品を
生み出していかねばならない。
換言すれば、少子高齢化時代に対してあなたが、
あるいはあなたの会社が「外向き・上向き・前向き」
にチャレンジするかどうかで自分たちの命運が
決まるのだ。
(今日の名言 48 495)
今国会(当時)で野田首相は、
「社会保障と税の一体改革」を、念仏のごとく
唱えています。
少子高齢化時代になり、さらに2011年3月11日に
発生した東日本大震災及び東電福島第一原子力
発電所事故により、日本国内は企業も個人も
一部を除いて疲弊しています。
こうした状況下で消費税増税が実施されたら、
多くの零細企業とサラリーマンはその衝撃に
耐え切れず、倒れてしまいかねません。
デフレが慢性化し、ギリシャに端を発したEUの
不安定さが円高に拍車をかけています。
株式市場も日経平均が一時的に1万円を回復した
と思ったら、8千円台に下げています。
パナソニックやソニー、シャープなどの家電メーカー
は、韓国のサムスン電子やLG電子の後塵を拝し、
2012年3月期決算で軒並み数千億円の巨額の
赤字を出しています。
薄型テレビの価格下落が急激で、企業業績の足を
引っ張っています。
日本の半導体メーカーのエルピーダメモリは破綻し、
米半導体メーカーに買収される見込みです。
同じくルネサステクノロジも業績悪化のため、
数千人規模の人員削減をつい最近発表しました。
日本には今、逆風が吹き荒れていますが、
大前さんが力説しているように、
「外向き・上向き・前向き」にチャレンジして
頂きたい、と強く願っています。
上記の記事を書いたのは、2012年5月23日のことです。
今から3年前のことです。わずか3年前のことですが、
隔世の感があります。
当時は、デフレ、消費増税、東日本大震災から1年後、
といった負のスパイラルに苛まれていました。
民主党が自民党から政権を奪っても、成果を収める
ことはできませんでした。
その後、自民党が政権を奪還し、自民党と日銀の
共同歩調による円安誘導政策が功を奏し、
自動車メーカーをはじめ輸出産業は好業績を上げ、
日経平均株価は2万円の大台を回復しました。
ですが、庶民の生活は楽になったかといえば、
以前と変わりません。
消費増税が重しになっていることは明らかです。
さらに、非正規雇用者が増加し、収入が減少して
いるため、なかなか消費の増加に結びつきません。
パナソニックは業績が回復しましたが、ソニーは
道半ばです。
一方、シャープは三洋電機と同じ道を辿るのでは
ないかと見られています。つまり、解体される、
というのです。
この3年で、強者と弱者の差が鮮明になったと言え
ます。それは企業にかぎらず、個人においても同様
です。
非正規雇用者の割合が増加したことにより、
賃金格差が拡大したからです。
こんな時代だからこそ、大前さんが言うように、
「外向き・上向き・前向き」にチャレンジして
いきたい、と思います。
決して「内向き・下向き・後向き」になっては
いけません!


非正規社員の現状をグラフ化してみる(2015年)(最新)
Garbage NEWS.com のサイトから (以下同様)


藤巻隆(ふじまき・たかし)オフィシャルブログ-
人気のブログランキング
こちらのブログやサイトもご覧ください!
こんなランキング知りたくないですか?
中高年のためのパソコン入門講座(1)
藤巻隆のアーカイブ
本当に役に立つビジネス書