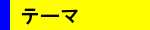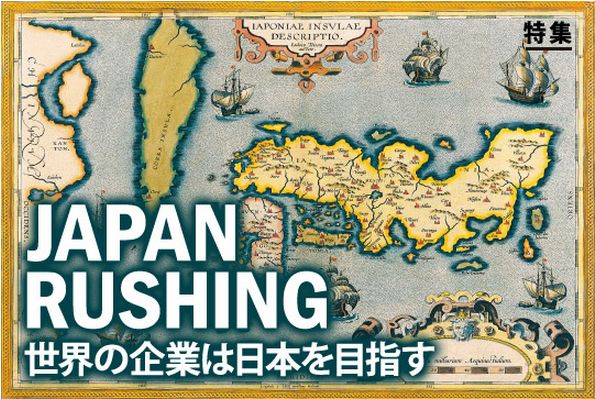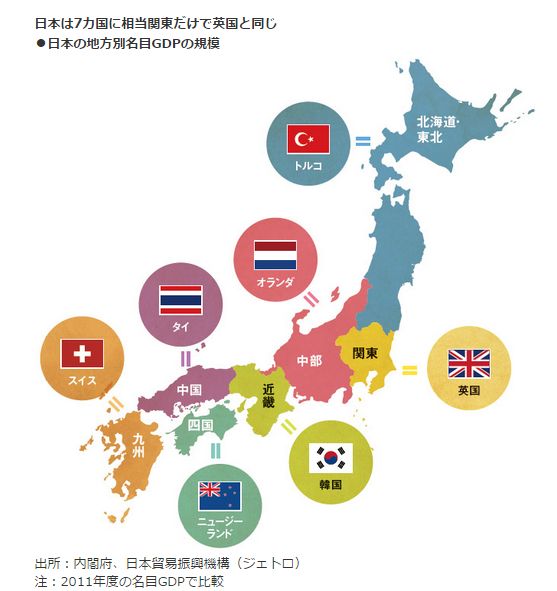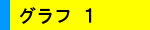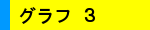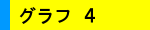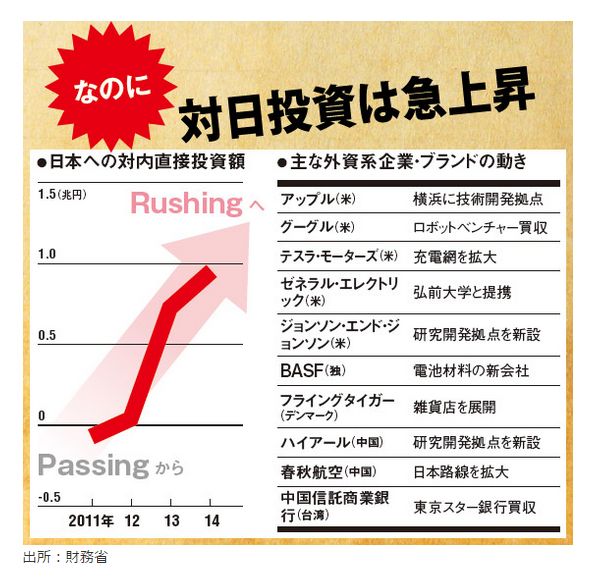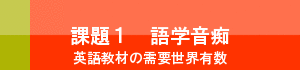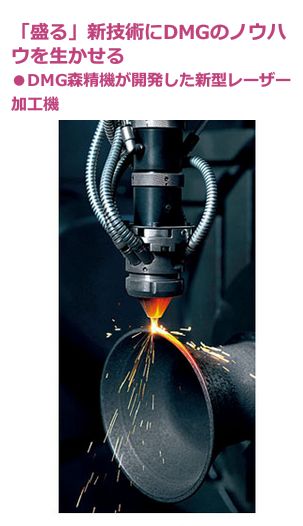大前研一さんは、私にとってメンターでもあり、
グールー(思想的指導者)の存在でもあります。
大前さんの著作を読んでいつも感じるのは、
物事の本質を捉えるずば抜けた能力です。
凡人である私は大前さんの足元にも及びませんが、
不断の努力を怠らず、一歩でも彼に近づきたい、
と思っています。
サラリーマン再起動マニュアル
2008年10月4日 初版第1刷発行 小学館
ISBN978-4-09-379454-1

目次
[イントロダクション]志のあるサラリーマンは、
きつい仕事を厭わない
第1章[現状認識]なぜ今「再起動」が必要か?
第2章[基礎編]「再起動」のための準備運動
第3章[実践編]「中年総合力」を身につける
第4章[事業分析編]“新大陸エクセレントカンパニー”の条件
第5章[メディア編]「ウェブ2.0」時代のシー・チェンジ
[エピローグ]新大陸の“メシの種”はここにある
第5章[メディア編]「ウェブ2.0」時代のシー・チェンジ
現在、ネットの世界は「ロングテール」が常識に
なっている。つまり、ネット配信は、
できるだけ多種多様なコンテンツを大量に揃えて、
ユーザーが自分の好きな番組を好きな時間に視聴
できるようにすることが重要なのである。
番組を選ぶのはNHKではなくユーザーであり、
極端にいえば、大勢の人が見ている人気ドラマや
過去の人気作品ではなく、見ている人の少ない
お宝映像やレアものを充実させるべきなのである。
それこそがブログやSNSなどでユーザーが自由に
情報を発信、交換できるようになったウェブ2・0
時代の発想だろう。
(今日の名言 47 494)
NHKと同様に、ネット配信を行なっている
民放局が数社あります。
新たな収益源として活路を見出しているの
でしょうが、大前さんが指摘しているように
「お宝映像やレアもの」を充実させなければ、
早晩事業が立ちいかなくなる、と考えています。
大前さんは次のような指摘もしています。
<放送メディアが世論の動向を正確に把握でき
なくなったのは、通信メディアを補足していな
かったからである。
言い換えれば、通信メディアが放送メディアを
上回る機動力と影響力を持つようになったから
である>
LINEやTwitter、Facebook、Instagram、Youtube、
あるいはAmeblo などのブログを介して、
即座に情報を発信し、共通する環境が整いました。
個人が情報を発信することができる時代になった
のです。これはとてつもなく大きな変化です。
個人が放送局を持ったようなものです。
内容は玉石混交ですし、不正確な情報や作為的な
誤情報もあるでしょう。
本物と偽物を見分ける「選択眼」を養うことは、
極めて大切なことです。
ですが、テレビ局側の都合で、伝えるべき情報を
故意に伝えなかったり、捏造したり、過剰な演出
(やらせ)が横行している現状を見たり、
政府による報道の自由を規制することが平然と
行われることを考えると、テレビ局側による情報
の一方通行では、テレビ離れの流れを食い止める
ことは困難でしょう。
視聴者に情報の選択権がないことが、致命的です。
今後も通信メディアの動向から目が離せなくなった、
と実感しています。
最近読了した『テレビは余命7年』(指南役 大和書房
2011年9月25日第1刷発行)の中に次のような記述があり
ます。
(前掲書 P.006)
余命7年――。
かつて「護送船団」と呼ばれ、大蔵省の庇護のもと
繁栄を謳歌した銀行業界も、13行あった都市銀行は、
今や4つに集約されている。バブル崩壊の元凶と
なった「不動産取引の総量規制」から、北海道拓殖
銀行の倒産までが、約7年である。
歴史は繰り返す。
僕は今回の「地デジ化」が、かつての不動産総量規制
と同じく、下り坂への1つのシグナルと見ている。
7年後の2018年、テレビ界の威信を失墜させる
大事件が起きると予想する。具体液には、それは僕は
在京のキー局のどこかの破綻[はたん]と見ている。
江戸末期、ペリーの黒船来航から幕府の権威・井伊直弼
大老暗殺までも7年である。
7年とはそういう時間である。
この本の中では、破綻するキー局の名称は示されていませんが、
十分に現実味のある話だと思いました。
藤巻隆(ふじまき・たかし)オフィシャルブログ-
人気のブログランキング
こちらのブログやサイトもご覧ください!
こんなランキング知りたくないですか?
中高年のためのパソコン入門講座(1)
藤巻隆のアーカイブ
本当に役に立つビジネス書