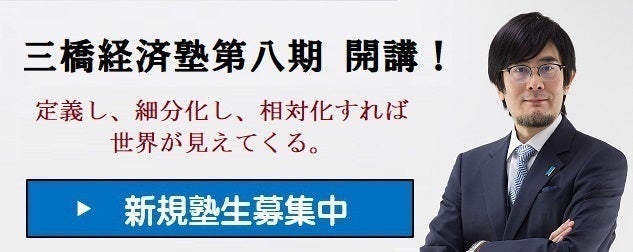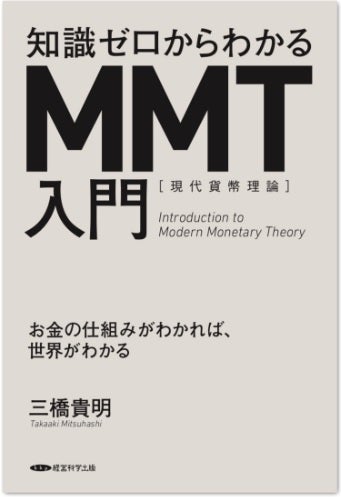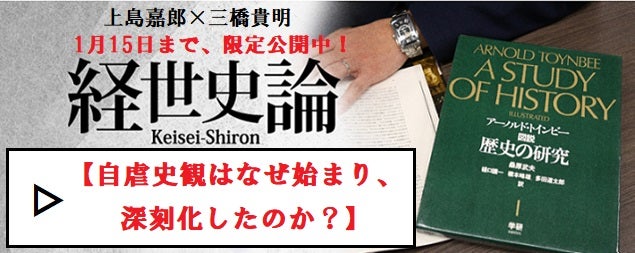株式会社経世論研究所 講演・執筆依頼等、お仕事のご依頼はこちらから
三橋貴明のツイッターはこちら
人気ブログランキングに参加しています。
チャンネルAJER
『日本の少子化をくい止めるにはーその2ー(前半)』三橋貴明 AJER2019.10.22
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
12月21日(土)シンポジウム「令和の政策ピボットは実現可能なのか?」が開催されます。
また、メルマガ「令和ピボットニュース」が始まりました。皆様、是非とも、メルマガ登録を!
一般参加可能な講演会のお知らせ。
年末特別講演会「京都大学大学院教授、元安倍内閣・内閣官房参与 藤井聡様」
2019年12月4日(水) 18:45~ 東京都新宿区
【MMT (現代貨幣理論)を学び、日本経済を展望する】
三橋TV第167回【日本史上最も深い民主制の議論をしてみた】
昨日のエントリー「国民のメモリーである歴史を守り、伝える」と、一昨日の「政策と政治~時が止まった国にて~」、あるいは三橋TVで堀茂樹先生にご教授頂いた「民主制」の話は、全て一つにつながっている話です。
つまりは、我々が国民意識(ナショナリズム)、より具体的に書くと「国民間の連帯意識」を失われつつあり、結果的に民主制で「政策論争」が行われなくなり、政治家は「政治権力」の維持に専念し、国民の豊かさ、安全は置き去りにされていっているという話です。
そして、なぜ日本国民のナショナリズムが失われつつあるのかといえば、「歴史」という国民のメモリーを大東亜戦争敗北後に破壊されていったためです。
横軸のナショナリズムが、現在の日本国民同士のつながり。縦軸のナショナリズムは、先人から未来の日本人へとつながる連帯意識、つまりは歴史です。
【縦軸のナショナリズム・横軸のナショナリズム】
昨日、某大学の学生さん向けに講演をしたのですが、その後のQ&Aで、
「高齢化が進む中、数が多い高齢者の票の影響が大きくなり、若者向けの政治は不可能なのではないか」
と、明らかにメディアに影響を受けているものの、それなりに説得力がある質問がありました。
「高齢化が進む中、数が多い高齢者の票の影響が大きくなり、若者向けの政治は不可能なのではないか」
と、明らかにメディアに影響を受けているものの、それなりに説得力がある質問がありました。
堀先生ではないですが、「一票は一票」です。日本の有権者の中で、一人で多票を持つ人は一人もいません。
となると、数が多い高齢者の「票」の影響力で、高齢者向けの政策が行われ、若い世代や現役世代向けの政策は困難になるように思える。
とは、もちろん「パイが一定」という前提の話です。すなわち、プライマリーバランス、トレードオフ、あるいは「集中と選択」思考であり、間違っています。
というより、わたくし共は、
「パイが一定で、一方に予算を使うと、反対側を削らなければならない」
という、トレードオフ発想をやめなさい、と主張しているのです。
高齢者のための医療・介護の充実と、大学生向けの給付型奨学金。
どちらかをやる、ではありません。両方ともやればいいのです。
高齢者のための政策も推進し、若い世代や現役世代向けの政策も推進する。すべての国民を、誰一人見捨てず、「政治」が守る。この発想が必要なのです。
何しろ、PB目標の下で、トレードオフや選択と集中をやっていると、国民が分断されます。上記の質問には、明らかに「高齢者 対 若い世代」という世代間対立の要素が含まれてしまっているのです。気が付きました?
高齢者も現役世代も、若い世代も子供たちも赤ちゃんも、みんな同じ「日本国民」なのです。健全な国民意識、助け合いの精神、連帯意識、つまりはナショナリズムを前提に、
「誰一人見捨てない」
という発想の政治に転換しない限り、我が国の国民は分断され、最終的には国民国家が壊れるでしょう。
【歴史音声コンテンツ 経世史論】
※11月5日から上島嘉郎先生と三橋貴明の対談「自虐史観はなぜ始まり、深刻化したのか」がご視聴頂けます。
もちろん、PB目標がある限り、トレードオフ、選択と集中、別の書き方をすると「国民の選別」は終わりません。
そして、我が国が「国民の選別」という残酷な政治から脱却するためのカギが、やはりMMTです。
『消費増税「信じがたい」 異端「MMT」の名付け親語る
日本や米国など自国通貨建てで国債を発行できる国は財政破綻(はたん)しないので、もっと財政を拡張し、所得や雇用を増やすべきだ。インフレもコントロールできる――そんな主張の経済理論「MMT」(Modern Monetary Theory=現代貨幣理論、現代金融理論)。経済学の主流派からは異端視される理論だが、中央銀行の金融緩和でも景気回復の実感がなく格差が広がる中、各国で関心が集まる。最近は退任した欧州中央銀行(ECB)のドラギ前総裁が「MMTに注目すべきだ」と発言した。なぜ今MMTなのか。このほど来日した、MMTの「名付け親」とされる豪ニューカッスル大のビル・ミッチェル教授に聞いた。(後略)』
日本や米国など自国通貨建てで国債を発行できる国は財政破綻(はたん)しないので、もっと財政を拡張し、所得や雇用を増やすべきだ。インフレもコントロールできる――そんな主張の経済理論「MMT」(Modern Monetary Theory=現代貨幣理論、現代金融理論)。経済学の主流派からは異端視される理論だが、中央銀行の金融緩和でも景気回復の実感がなく格差が広がる中、各国で関心が集まる。最近は退任した欧州中央銀行(ECB)のドラギ前総裁が「MMTに注目すべきだ」と発言した。なぜ今MMTなのか。このほど来日した、MMTの「名付け親」とされる豪ニューカッスル大のビル・ミッチェル教授に聞いた。(後略)』
エントリー冒頭の質問は、
「予算には「カネ」的な限りがある」
という、主流派経済学の考え方、厳密には「間違った考え方」が前提になっています。
「予算には「カネ」的な限りがある」
という、主流派経済学の考え方、厳密には「間違った考え方」が前提になっています。
高齢者に予算を使うと、若者には使えない。と、普通の人は思いがちですが、この過ちを何とか払しょくし、世代間闘争を起こさずに、全体で成長を目指す必要があります。
もちろん、政府に予算的な財政制約がなかったとしても、供給能力というボトルネックは出てきます。
高齢者「にも」、若い世代「にも」予算を使うのはいいとして、政府がそのために財やサービスを買う際に、きちんと供給ができるのか。あるいは、供給能力が増えるように予算を拡大するには、いかなる知恵を絞ればいいのか。
もっとも、とりあえず今の日本は「その前の段階」です。とにもかくにも、プライマリーバランス目標を破棄しなければ、話にならない。
というわけで、政治家には、トレードオフ的な発想ではなく、
「高齢者も守れ、現役世代も守れ、若者も守れ、子供たちも守れ、国民を誰一人見捨てるな!」
と主張する必要があります。100%、「ザイセイガー」と返してくるでしょうが、そこでMMTなどのツールを活用し、政府に予算的な財政制約がないという現実を認めさせるのです。
正しい知識さえインプットされれば、PB目標がいかに狂っているかが分かるのです。
「国民を誰一人見捨てるな!」にご賛同下さる方は↓このリンクをクリックを!
本ブログへのリンクは以下のバナーをお使いください。

◆関連ブログ
日本経済復活の会のホームページはこちらです。
◆三橋貴明関連情報
新世紀のビッグブラザーへ ホームページはこちらです。
メルマガ「週刊三橋貴明~新世紀のビッグブラザーへ~」はこちらです。