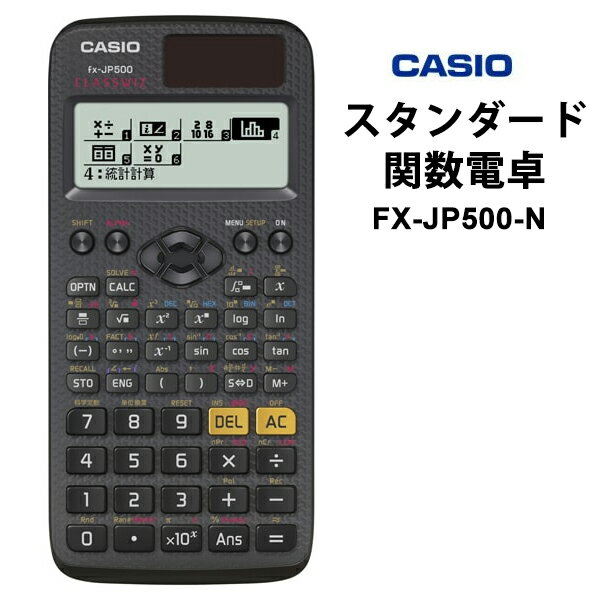久しぶりの数学ネタです。
2次式に関する公式等をまとめました。
⭐︎平方完成は2次式の問題を見ればとりあえず平方完成させる程によく使う手段です。
y=f(x)=ax²+bx+cをy-q=a(x-p)²の形に変形することで、y=ax²のグラフを(p,q)平行移動させたものと分かり、最大値(aが負)または最小値(aが正)とそれを与えるxの値が導けます。
平方完成の方法は、
ax²+bx+c
=a(x²+bx/a)+c 2次の係数で1次と2次の項をまとめる
=a{(x+b/(2a))²-(b/(2a))²}+c
=a{x+b/(2a)}²-{b/(2a)}²+c
です。しかし、天下り式で計算も複雑なのであまり好みではないです。
自然さを求めるなら、
a(x-p)²+qを展開すると、
ax²-2apx+ap²+qで元の形のax²+bx+cと係数を比較すると、
-2ap=b、ap²+q=cであるから、p,qについて解くと、
p=-b/(2a)、q=-b²/(4a)+cなので代入すると
a{x+b/(2a)}²-{b/(2a)}²+cになる。
また、逆にx=pで極値qをとることからq=f(p)であることを積極的に使うのもありだと思います。
⭐︎解の公式
2次方程式の解の公式は係数を公式に代入するだけで解が得られる公式です。
2次方程式の解き方として他にはa(x-α)(x-β)=0の形に因数分解する方法もあります。
どちらかといえば、なるべく解の公式を使わずに因数分解して解く方が良いと言われていますが、個人的には計算演習として解の公式で解かせる方が良いと思います。特に平方根や複号、負の数の代入が難関だと思いますが基本的なルールなので理解すべきです。
公式の導出は平方完成して導きます。普通にやるのも良いですが、4aを掛けてからやると分数の計算が減ります。
ax²+bx+c=0
4a²x²+4abx+4ac=0
(2ax+b)²-b²+4ac=0
(2ax+b)²=b²-4ac
2ax+b=±√(b²-4ac)
2ax=-b±√(b²-4ac)
です。結果論的なので初見では難しいです。初見の場合は平方完成の式の解に代入するとよいと思います。また、解の公式で出た解を方程式に代入して成立するか確認してみましょう。
⭐︎2次式の因数分解
2次式の因数分解といえば襷掛けですが、逆に解の公式から因数分解をすることができます。
⭐︎解と係数の関係
2次方程式の2つの解の和(1次式)と積(2次式)は係数を使った簡単な式で表せます。どちらかというと、2つの数の和と積から2つの数を求める際に使うことが多いです。
⭐︎1/6公式
放物線と直線で囲まれた面積を求める公式です。2つの交点のx座標と2次の係数が分かればすぐに求められます。交点のx座標は2次方程式を解けばすぐに出てくるので簡単です。
置換積分を使わずに導出するとよく分からない工程を踏んでいるように見えますが、置換積分を使うと見通しが良くなります。
結果からわかる通り、交点のx座標の差が分かれば良いので、計算しやすいように片方の解を中心に移動させます。この時、x座標の差であるβ-αが何度も出てくる(他のは出てこないレベル)のでひとつの文字で表すとさらに見やすくなります。
2次の係数が正の時は下に凸なので、積分の値は負になります。面積を出すだけなら絶対値を取るだけで十分です。
⭐︎放物線の頂点と焦点
放物線は線対称な図形で対称軸との交点が頂点です。直感的には尖った所です。
放物線の面白い性質として、軸と平行な線が放物線で反射したものは全てある点を通る性質があり、 その点を焦点と呼びます。さらに、焦点までの行路長は軸と垂直な直線上で一定です。その長さは軸上の点からの距離を求めると、頂点までの距離と頂点と焦点との距離の和になります。
単に対称なものとして扱うのは勿体無いと思います。
頂点の座標を求めるには平方完成するのが一般的ですが、傾きが0になる点を探るのが物理での放物運動との関連が大きいです。
焦点は対称軸上にあるのはほぼ自明であり、y座標はy軸方向からx軸方向に向きが変わるのは傾きが±1の所なのでそのy座標です。
放物線が使われているものとしてパラボラ(放物線)アンテナや電球式の懐中電灯(LEDは指向性が強いので使われてないようです)などがあります。
2次式になるものとして注意すべきなのは速度に関するもので、制動距離や遠心力、運動エネルギーは速度の2乗に比例するので高速域では想像以上に大きくなります。