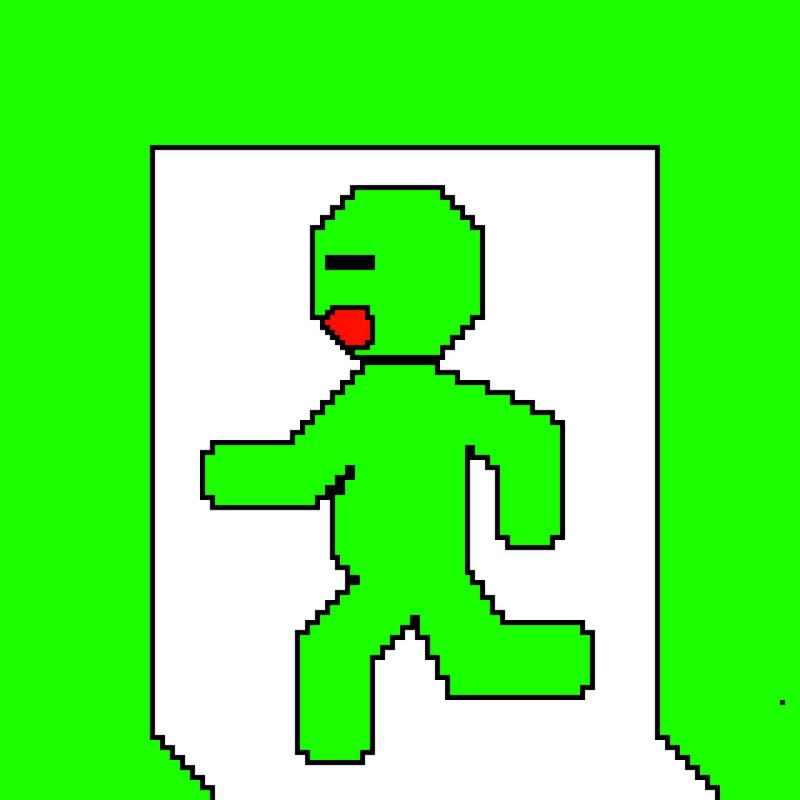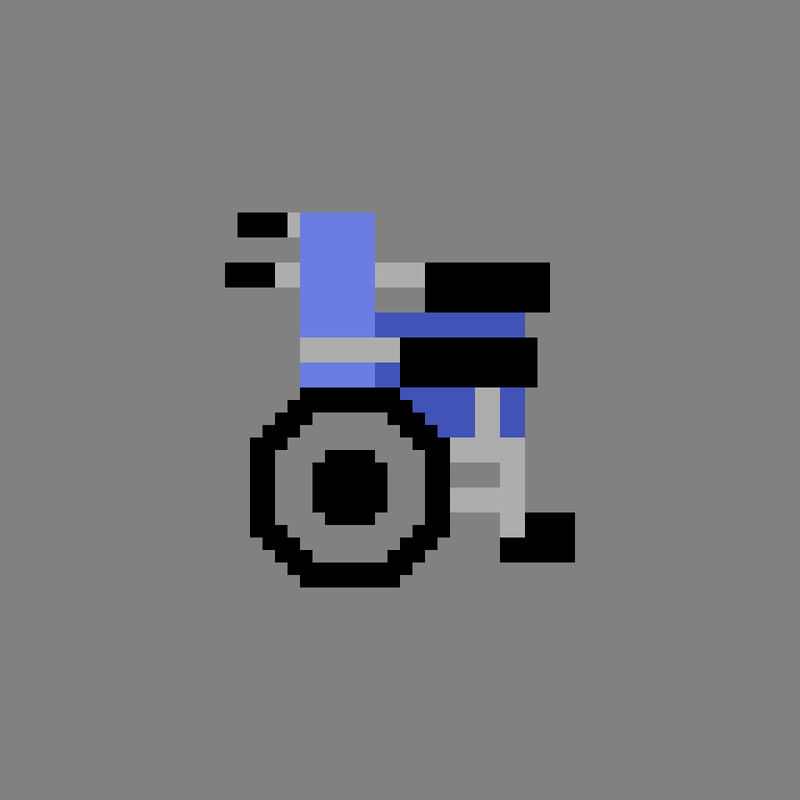この記事を読んで頂きありがとうございます。
はじめての方はこちらをご覧下さい。
あらすじ
子どもたちに〇〇おじさんや✕✕おばさんと言うあだ名で噂されるような、近所に一人はいた不思議で個性的な有名人。
そんな有名人を追う少年たちの青春とその後の物語。
「そろそろ行こか。たっくん、まる、今日こそバーババの住み家を突き止めるで!」
桜舞う中学1年生の春。和真(かずま)は張り切っていた。門限が21時に延びたから今度こそバーババの後を追える。
「サッカーやっとったら、グラウンドの向こうからずっと見てくるばあさんおらん?毎回4時半くらいに絶対おんねんけど。」
最初にバーババの存在に気付いたのはたっくんだった。
そう言われて意識してみると、確かにフェンス越しにこちらをジッと見てくるおばあさんがいる。
しかも毎回ネオンカラーのジャージを着ている。夏でも冬でも変わらず長袖のセットアップだ。
そして不思議なことに色だけ毎日変わっているではないか。
「なんか駅前のバーの看板みたいやな。」
誰かが言い出した言葉から、皆がおばあさんのことをバーババと呼ぶようになっていた。
バーのばあさんでバーババだ。
「あのばあちゃんな。確かに気になるよな。でも、俺がコーチやりだした頃にはもうおったから、3年はああやっとるけど何もしてこうへん。柿澤(かきざわ)監督もほっといて良いって言うからそのままにしとんねん。」
相談した時はコーチにそう言われた。
柿澤監督がそう言うんなら、これ以上は騒げない。
何せ監督はこのサッカークラブを何回も全国大会に導いた名監督で、地元じゃ皆に一目置かれる有名人だ。きっと親に何を訴えても「柿澤監督が大丈夫って言いはるんやったら大丈夫なんやろ。」と言われるに違いない。
「わざわざそんな遠いとこから来とるなんて、何か目的があるに違いないやろ。」というまるの話を聞いて意見が変わっていた。
そこから和真たちのバーババの調査と言う名の、どこから来ているか見つける探検が始まった。
でも、まるの言う通り2時間後を追っても家に辿りつかない。当時小学4年生だった和真の門限は19時だったので慌てて電車で帰ったくらいだった。
全く進まない住み家探し。ただ調査を続けていくういに分かったことがあった。それはバーババはサッカークラブが休みの曜日、火、木、日でもグラウンドに来ている日があるということ、それにバーババが帰るルートは毎回同じということだ。
調査を始めてから2週間後。
「あんたら最近サッカーサボって何やってるん?コーチに言いつけるで!」
いきなり怒鳴られる三人。
「う、うっさいわサチ、こっちだって色々あんねん。」
そう言い返す和真の目は少し泳いでいる。
サチはサッカークラブのレギュラーで児童会に入っている女子だ。成績も良く親も金持ち、そして何より無茶苦茶気が強い。
「はぁ?色々って何やねん!サッカーサボって良いくらいの理由があるんなら聞かせてみぃ!!」
これだけの剣幕で言われると和真もまるも何も言い返せない。
「そうやな、ごめんな。次からは気をつけるわ。でも体調不良とかで休む時もあるから、その時は許してな?」
唯一言い返せるのはこのクラブのエースストライカーたっくんだけだった。
「まぁ、それくらいなら…」
たっくんの言葉にサチも冷静になる。
「次からはバレんように気をつけよう。」
サチが去った後で三人は頷きあった。
それからは、あまりサッカークラブを休むとサチだけでなく親やコーチに怒られるので、月に1、2回程度の調査だったが、和真たちは小学校を卒業するまで行った。
そして中学生の今、門限は2時間も延びた。
「さすがに家見つかるやろ。」ということで集まった三人。
たっくんはサッカー強豪校の私立中学へ行き、まるは親の転勤で地元を離れたので、集まるのは久し振りだ。
「かっちゃんは友達が多い地元の中学校に行けてエエよな。僕はまだ友達おらんわ。」
「いや、お前らおらんと寂しいわ。」
「でも、まるもかっちゃんも学校行くのに時間かからんやろ?俺は行くだけで1時間以上かかるねん。ほんまダルいわ。」
「たっくんはサッカー強いところ行けたから羨ましいわ。」
小学校の前でそんな話をしているとバーババが来た。
「よしっ。今日こそ家を見つけるで!」
結論を言えばバーババの家は分からなかった。より正しく言うとバーババの後を尾けると大きなマンションに入ってしまい、どの家か分からなかった。
マンションはオートロックで無理に入るわけにもいかない。そのマンションは小学校から歩いて4時間のところにあった。
「バーババまじでどんだけ歩くねん!」
汗を手で拭きながらたっくんが言う。
「ほんまにな。そんでオートロックかぁ。折角ここまで来たのにな。」
和真が同意する。
「あれ?待って。たっくん、かっちゃん、ポスト見てみて!」
まるが指した先には『中垣内(なかがいと)』と書いた郵便受けが有った。
「中垣内ってサチの名字やんな?ってことはサチのおばあちゃんやったんか!」
「なるほどな、だからサチがあんな怒ってたんか。」
三人とも興奮している。
「でも、サチに確認できへんな。サチもまると同じで引っ越したもんな。しかも小5の時に。」
残念そうに言うたっくん。
「僕と同じ転勤組やな。でもまだ調査できる方法はあるで。次は別の時間に来てバーババが近所の人になんて呼ばれてるか調べてみようや。」
「それエエな!じゃあそうしよ。」
約束したは良いものの、中々三人の予定は合わない。最初は1週間に一回調査すると決めていたものが、2週間に一回になり、1ヶ月に一回になり、最後の方は3ヶ月に一回になった。
おそらく学年が上がるにつれて「何でこんな子どもっぽいことしてるんやろ。」という気持ちを三人とも持ってきたことも関係しているのだろう。
最早バーババの調査という目的で集まるというよりは、それを口実に定期的に集まることが目的になっていた。
中学3年生の秋。3ヶ月振りに集まった三人。
「結局地元の高校に行くことになってさ、お前らはどこの高校に行くん?」
「高校はかっちゃんと同じ所に行きたかってんけどな。親が受験しろってうるさいから、僕は多分どこかの進学校に行かされるわ。」
「俺はサッカーでスポーツ推薦もらったから、中学校より遠い高校に行く。お前らと会われへんようになるんわイヤやけどな。まあ寮付きで通学時間はほぼないから、そこだけは嬉しいわ。」
「もう集れんようになるんかぁ。」
ボソッと言った和真だけでなく、三人とも寂しそうだ。
「じゃあ行こうか?」
「うん。」
「そうやな。」
3年間で新たにバーババについて分かったことが二つあった。
一つ目はサチがいなくても何故かサッカークラブの練習を見に行くこと。これについては「習慣になってるんやろ。」というまるの意見に二人とも納得した。
二つ目はサッカークラブが休みの曜日のうち木曜日は高確率でバーババが商店街に出かけることで、11時に出ると時間まで決まっている。商店街に出かけると言っても、買い物をすることはほとんどない、かと言って店の人と話すわけでもない。ただブラブラしているだけだ。
最近の和真たちはバーババの商店街に行く時に合わせて集まっていた。今日も商店街で三人で喋りながらバーババのことを遠巻きに眺めるだけだ。
するとこの日はバーババに話しかける人がいた。血統書が付いてそうな犬を連れた上品なおばさまといった感じの女の人だ。
「あら、柿澤のおばあちゃん久し振りですね。」
「!!!」
おばさまの言葉を聞いた瞬間、三人は息を呑む。
「柿澤って!監督のオカンやったんか!」
「だからサチがいなくなってもグラウンド行ってたんや!!」
大興奮だ。
長年の謎が解けた嬉しさを三人でワイワイ話し込んで共有していると、いつの間にか日が暮れていた。
「…じゃあそろそろ帰ろうか。」
「たっくん、まる。高校でも元気でな。」
「また会おう。僕連絡するわ。」
とても名残り惜しいのは、バーババの調査が終わるとともに三人が集まる機会がグッと減るのを、皆が薄々理解しているからだろうか。
結局その日はグダクダと話し続けて、門限を破った和真は親に雷を落とされた。
調査終了から3年後の春。和真は18歳で介護士として就職していた。大学に行って勉強したくなかったし、実家の経済状況が悪かったからだ。まるとたっくんにはもう1年以上会ってない。
「天内(あまうち)和真と申します、どうか宜しくお願いします。」
介護施設の食堂で利用者たちに頭を下げる和真。ふと奥の方を見てみるとなんと!バーババがいた。
「バーババ。」
思わず呟く和真。
気になって仕方がないが覚えることは山程ある。ゆっくり昔話をしている時間はない。何より6年間尾行していただなんてとても本人に言えない。
仕事を覚えているうちに3ヶ月が経っていた。その間にバーババから話しかけられたことはない。こちらから話しかけても一言二言返すだけだ。
先輩職員にも「柿澤さんはあんまり話すの好きじゃないみたいやねん。」と言われた。
入社から1年が過ぎた夜勤の日。珍しく寝られないバーババが食堂に一人で座っていた。すると魔が差したのか和真はこう話しかける。
「柿澤さん。僕のこと覚えてますか?」
するとバーババはうっとうしそうな表情で言う。
「あー。お前あの時のクソガキ三人組やろ。ちょくちょく後を尾けてきて面倒やったわ。」
「本当にすみませんでした。」
土下座をせんばかりの勢いで頭を下げる。
「まぁもう昔のことや。どうでもエエわ。」
「すみません、すみません。」
「エエて。子どものやったことやしな。別に大して被害を受け取らんし。それより何で後を尾けてきたんや?」
「本当に失礼なんですが、当時の柿澤さんは蛍光色のジャージをずっと着てはって、僕たちを睨んでるようで怖かったんです。それで目的を暴いてやろうと思って。でも監督を見てはっただけだったんですよね?」
「ふん。まあ息子がどうしとるか心配だったのもあるけどな、中学校まで行ったのは暇つぶしやった。」
「暇つぶし…ですか。」
「今はこうして老人ホームに入れられとるが、あの頃は息子夫婦にお世話になっとっての、息子が留守の日は嫁に迷惑かけたらアカンと思って、出来るだけ家を出とったんや。」
「あぁ、たまに来はる義理の娘さん良い人ですよね。」
「良い人なことあるかいな。一緒に住んどった頃は嫁にずっとイジメられとった。あのジャージも派手で恥ずかしいのに、お義母さんが事故に合わないように用意しましたよ。って言って着させよる。お陰でこっちは夏でも冬でも同じ格好やで。」
「それは酷いですね。」
「ほんで息子に分からんようにイジメてくるんや。お義母さんはゆっくりして下さい言うて、家におる時はベッドから起きさせてももらえへん。だから家出とったのに、息子にはお義母さんが好きで中学校まで歩いて行ってるけど怪我しないか心配だわ。と抜かしよったんや。」
「すごいお嫁さんですね。」
「ほら、息子の仕事は木曜と日曜だけ休みやろ?日曜はサッカーの試合があっておらんことが多かったんやけど木曜は息子家におったから、そういう日に限ってお義母さん好きなもの買ってくださいね。って小遣い渡すふりしよる。それも私の財布から盗ったお金やで。」
「うわぁ。」
「息子夫婦と一緒に暮らすまで、私は田舎で一人暮らしやったから息子の地元の商店街に知り合いもおらん。たまに話しかけて来るんわ嫁の知り合いばっかりやった。ほんましんどかったわ。」
「そんなことがあったんですね。」
「挙げ句の果てにお義母さんは認知症が酷くなってきたからうちで面倒見れません。やと。兄ちゃん、私に認知症があると思うか?」
「ないと思います。」
「まあ、施設に入れられた後の方が気ぃ遣わんで楽やわ。あんたも仕事頑張り!そんで後の二人にも宜しく言っといて。」
「ありがとうございます。」
バーババ…いや柿澤さんにそんなことが有ったなんて全然知らなかった。たっくんとまるにも教えてやろう。
そういえばあの二人どうしてるかな?
窓の外では桜の花びらが舞っている。久し振りに二人に連絡を取ることにした。