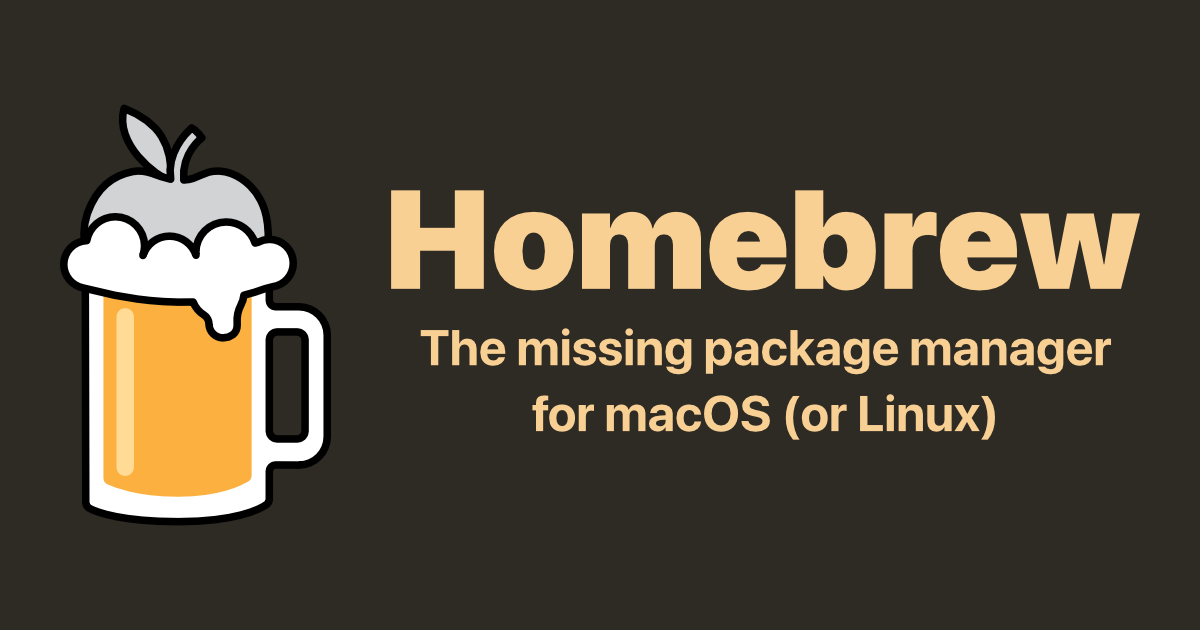書籍
の「第7章 これは便利、Finderスクリプティング」を取り上げます。「仮想MacでAppleScript(失敗談)」で試して一度失敗した「ドロップレット」に改めて「(仮想)漢字Talk7.5」で試してみます。
改めて「ドロップレット」とはこの書籍によると「ドラッグ&ドロップがきっかけで動き出すプログラム」だそうです。詳しくは「ファイルやフォルダを選択してドラッグ、ドロップレット・アプリケーションの上でドロップ」という使い方をします。
実例として「適当に選んだファイルをドラッグ&ドロップして情報(タイプとクリエータ)を見る」スクリプト・アプリケーションを考えます。ドロップレットにするには
「オブジェクトリストを開くとは」
「以上」
と、スクリプトの先頭、末尾にそれぞれ書きます。
また、スクリプトを保存する際に「アプリケーション」の形式を選ぶ必要があります(「ファイル」-「実行専用で保存」)。
(保存したスクリプトのデスクトップ上のアイコン)
アイコンの右上に下向き矢印が付いて、「ドロップレット」とわかります。
(デスクトップにSimpleTextで作った文書ファイルをドロップレットにドロップした時の実行結果(「スクリプト編集プログラム」では、ソースコードを表示))
(以前作った「ゴミ箱を空にする」スクリプトをドラッグ&ドロップした実行結果)
もう1つ「ドロップレット」を取り上げます。
「作成したファイルの名前を作成日を調べ、連番をつけながらファイル名を変更する」ドロップレットです。
(ファイル名の設定スクリプト)
作成日は「文字列として」取り扱います。これを元に年、月、日それぞれ2桁の文字列を求めます。
完成したスクリプトは「構文確認」でエラーを無くしてから、「実行専用で保存...」を行なってドロップレットにします。
実行結果(日付と連番のファイル名になっている)
使ってみての印象ですが、日本語でスクリプトを記述すると、いきなり英語のスクリプトを書くよりも構文が分かりやすいので、これを使って作ってみると「ドロップレット」もやや分かりやすく書くことが出来ました。
#追記(2023/11/14)
ホストのMacOSのバージョンの違いでBasillisk IIが起動できないことがある様です。その場合はAppleScriptを試す前に仮想MacOSの環境を作る必要がありますが、「BasiliskII builds for Mac OS X, links and downloads」でバージョンを確認して使う方が良さそうです。
参考1:「OLD Macを楽しむ。Basilisk II編」
参考2:「Mac Home brewでSDL2.0を簡単に環境設定」
でHomebrewをインストールしてから、
「Mac Home brewでSDL2.0を簡単に環境設定」でSDL2をインストール
|
|
などの環境構築が先に必要になる場合あり。 |